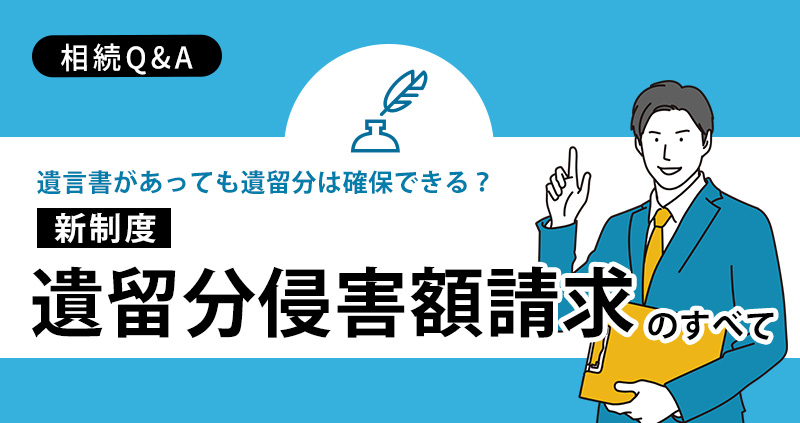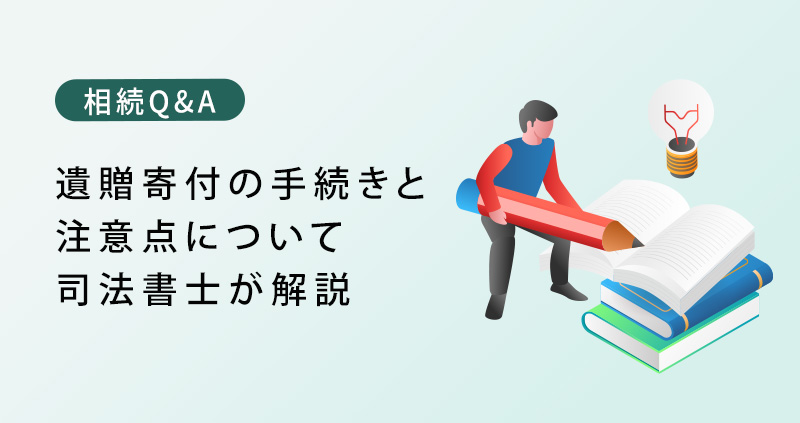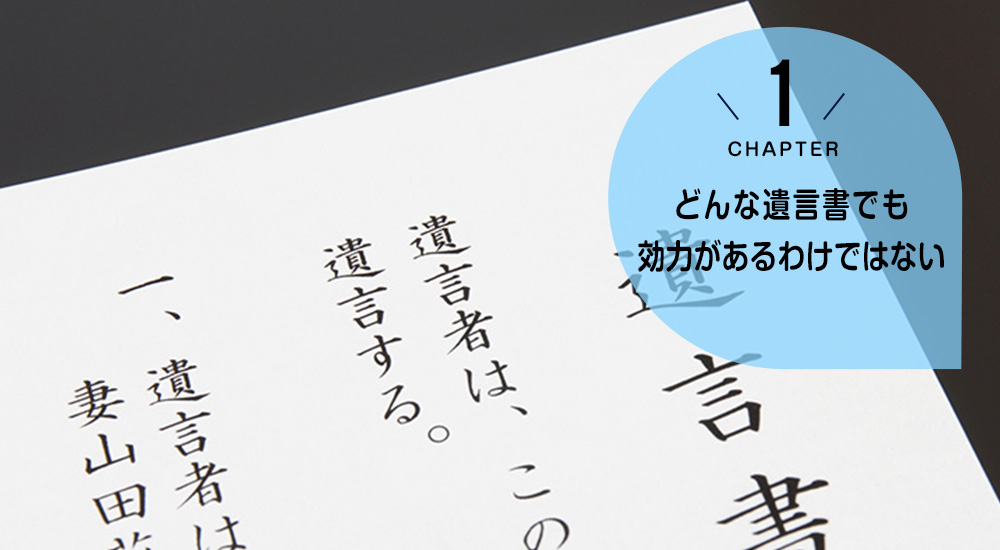死後事務委任契約の費用や流れを司法書士が解説
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
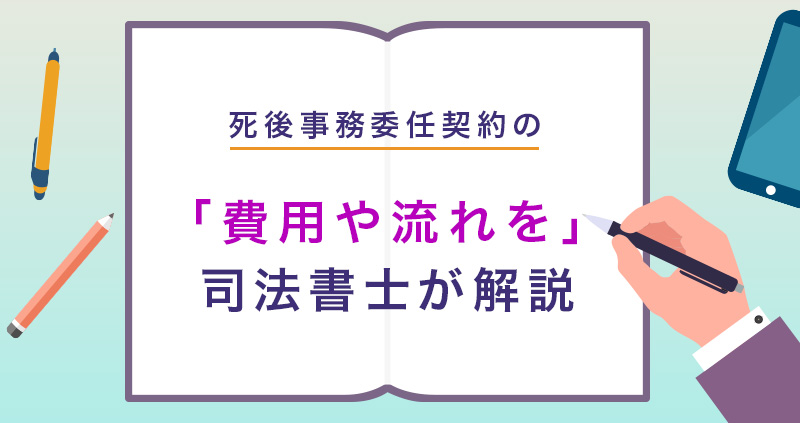

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の葬儀や各種費用の支払い等の事務を委任する契約であり、司法書士等の士業に依頼するのが良い。
契約に必要な費用は、『預託金』と『公正証書作成費用』である。
セットで『遺言者』や『任意後見契約書』なども作成しておくのが安心。
目次
家族や親族がいない人は死後事務委任契約を検討しておこう


死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを依頼する契約です。死後事務としては、『役所への各種届出』や『葬儀の手配』、『各種のサービスの解約手続き』などが考えられます。
死後に発生するこうした手続きは、普通は家族がやることです。しかし、家族がいない人はやってもらうことができません。そこで、死後事務契約という契約を結んで、他人にあらかじめ手続きの代理権を与えておく方法が有効なのです。
死後事務委任契約を結ぶ時期
死後には自分で契約をすることはできないので、死後事務委任契約は生前に結んでおく必要があります。高齢になり、もし認知症になってしまうと契約自体ができなくなるので、早いうちに検討しておいた方がよいでしょう。
死後事務は誰に委任すればいい?
死後事務委任契約は、通常、親族以外と締結します。親族の場合には、わざわざ契約を締結しなくても当然にこうした死後事務ができるからです。親族がいない人や、親族には頼めない事情がある人が、親族以外の第三者と契約するのが通常の形です。
誰に委任するかについて制約はないので、友人や知人などの中で信頼できる人に頼んでもかまいません。ただし、死後事務に含まれる手続きには手間がかかるものや複雑なものもあるので、頼んだ人に負担がかかってしまいます。死後事務は手続きに慣れた専門家に依頼するのがおすすめです。
死後事務を依頼できる専門家としては、弁護士、司法書士、行政書士などが考えられます。専門家には、死後事務委任契約だけでなく、『遺言書』や『任意後見契約』など、他の手続きについてもあわせて相談できるのもメリットです。
死後事務委任契約の方法
死後事務委任契約には決まった形式はありません。極端な話、口頭での契約でも成立します。しかし、口約束では約束した証拠が残りません。死後事務を行う段階では委任者である自分は亡くなっているので、最低限書面にしておくべきでしょう。
できれば、死後事務委任契約は公正証書にしておくのが安心です。公正証書にしておけば、本人が間違いなく自分の意思で契約を結んだことが明らかになります。本人の死後に各種の手続きを行う際にも、公正証書があれば信頼してもらいやすくなるので、手続きがスムーズに進みます。
死後事務委任契約に盛り込んでおく事項は?


委任事項を明記する
死後事務委任契約を結ぶときには、委任したい事項を明記します。どの範囲の事務を委任するかは自由です。一般には、次のような事項を委任します。
- 行政庁への届出
- 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 医療費の支払い
- 家賃の支払い
- 老人ホーム等の施設利用料の支払い、入居一時金等の受領
- 永代供養に関する事務
- 賃借建物明け渡しに関する事務
財産に関する内容は入れられない
死後事務委任契約は、あくまでも事務的な手続きについて代理権を付与するためのものです。よって、契約書に『自分の財産を誰に承継させるか』といった内容を入れることはできません。
自分の財産を、自分が望む人や団体に承継させるためには、別途『遺言書』を書いて遺贈や寄付をしたり、受け取る人と合意して『死因贈与契約』を結んだりする必要があります。
遺言書とは別にしないといけないのか?
遺言書を書くときに、遺言書のなかに死後事務を依頼する内容を入れる人もいると思います。しかし、遺言書は一方的な意思表示なので、お願いした内容が必ず実行されるとは限りません。遺言書が開封されるのは葬儀が終わってからのことが多く、死亡届や葬儀の手配には間に合わない可能性もあります。
死後事務については、遺言書に書くのではなく、受任者と別途契約を結んでおくのが安心です。
死後事務委任契約に必要な費用


- 預託金
- 公正証書作成費用
死後事務委任契約の『預託金』とは?
死後事務を行う際には、様々な費用が発生します。たとえば、依頼者が亡くなった後、死後事務委任契約の受任者は、葬儀費用を払ったり、病院への支払いを行ったりしなければなりません。
しかし、依頼者が亡くなった後は、依頼者の預金口座は凍結され、財産に対する権利は相続人に引き継がれます。こうなると、上記のような『事務処理に必要な費用』を、委任者の財産から支払うことができなくなり、死後事務の遂行に支障をきたしてしまします。
そこで、こうした費用の支払いに充てるため、死後事務契約を締結する際に、『預託金』として予めまとまった金額を、受任者に預けておく方法がとられています。
また、死後事務を専門家に依頼した場合には、受任者としての報酬が発生します。受任者の報酬も、預託金に含めるのが一般的です。
報酬の金額は、委任する事務の範囲によって大きく変わります。役所への届出などそれほど手間がかからない手続きだけなら数万円程度ですむこともありますが、葬儀の手配なども一括してもらう場合には50万~100万円程度かかります。
預託金の金額
預託金の金額は、葬儀の規模などによって変わってきます。一般的には、100~150万円程度を預けるケースが多くなっています。
預託金が足りなくなれば事務処理に支障をきたしてしまうので、必要な額を見積もった上で十分な額を用意しておくべきでしょう。死後事務を行った後、預託金が余った場合には相続財産に返還されることになります。
預託金が〝不要〟になる場合もある
死後事務委任契約とセットで『遺言書』も作成する場合、亡くなった時点の委任者の財産から死後事務費用を賄う方法もあります。
具体的には、死後事務の受任者を、遺言の遺言執行者としても指定しておくことで、預金凍結により死後事務費用を捻出できないといったことを防ぎます。(遺言執行者は、相続手続きのために預金を解約できる。)
これにより、生前に高額な預託金を預けておく必要がなくなるのです。
預託金は受任者の財産とは分けて管理
預託金は委任者のお金なので、受任者は預託金を自分の財産とは分けて管理する必要があります。預託金をきちんと区別して管理するために、信託銀行に預ける方法がとられることもあります。
公正証書作成費用
死後事務委任契約を締結するときには、公正証書を作成する費用がかかります。死後事務委任契約の公正証書を作成するときには、公証人手数料として1万1,000円、謄本手数料等で3,000円程度かかるので、1万4,000円程度の実費がかかります。
公正証書作成の手続きを専門家に依頼した場合には、別途専門家の契約書作成の報酬(10~20万円程度)がかかることになります。この報酬については、死後事務の報酬とセットになって料金が設定されていることもあるので、事前によく確認しましょう。
『任意後見契約』や『見守り契約』もあわせて生前準備を

これまで説明したきたとおり、死後事務委任契約は、亡くなった後の事務手続きを委任するものです。しかし、亡くなる前に認知症になり、自分でさまざまな手続きができなくなることも考えられます。そのような場合に備えて、死後事務委任契約だけではなく、別途『任意後見契約』を結んでおくのが安心です。
なお、任意後見契約は認知症になった後に効力が生ずる契約です。認知症になる前に、定期的に受任者と連絡を取り合い、健康状態の確認等を行ってもらいたい場合には、『見守り契約』もセットで結んでおくべきでしょう。
また、認知症ではなくても、病気などで財産管理ができない場合は、『財産管理等委任契約』を結んでおくこともできます。
死後の財産承継については、『遺言書』を用意しておくのも忘れないようにしましょう。
死後事務委任契約の締結を考えるときには、他の契約も合わせてトータルな生前準備をしておくのがおすすめです。
まとめ

家族や親族など自分の死後に身のまわりの手続きをしてもらう人がいない場合には、死後事務委任契約を検討しましょう。
当事務所では死後事務委任契約のほか、任意後見契約や遺言書など、ご希望に沿った形でのサポートが可能です。
終活をお考えの方に最適なご提案をさせていただきますので、ぜひご相談ください。
お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2026/01/20
代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?