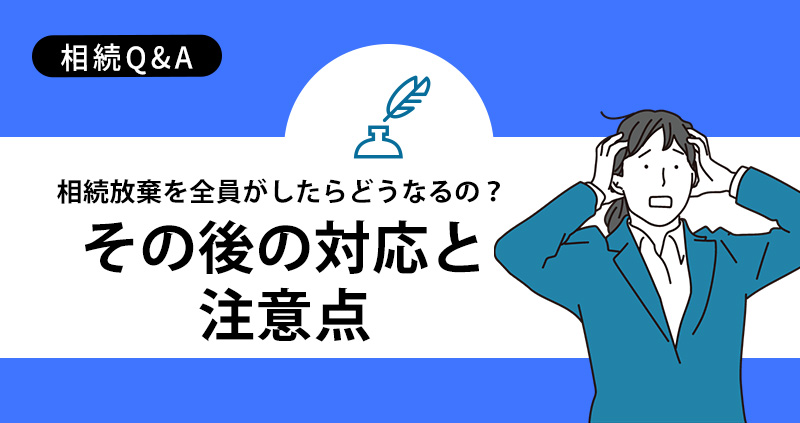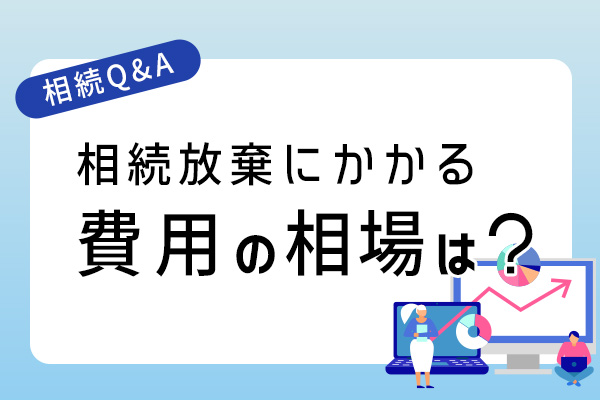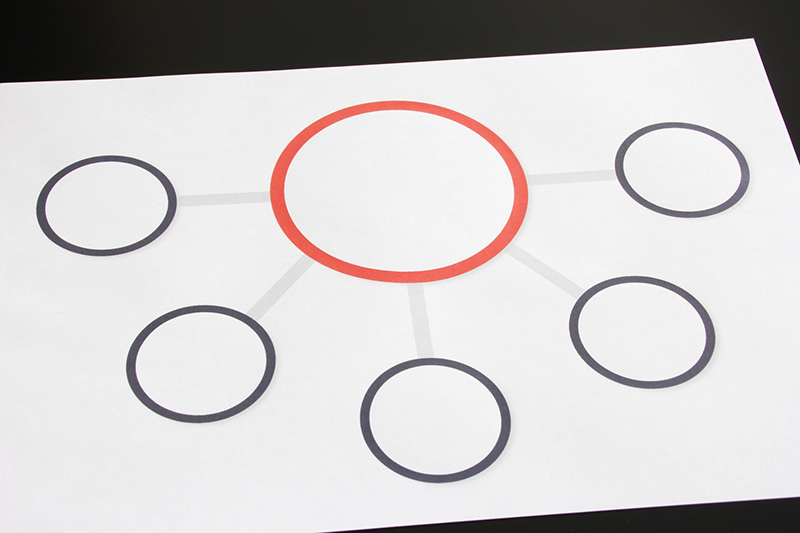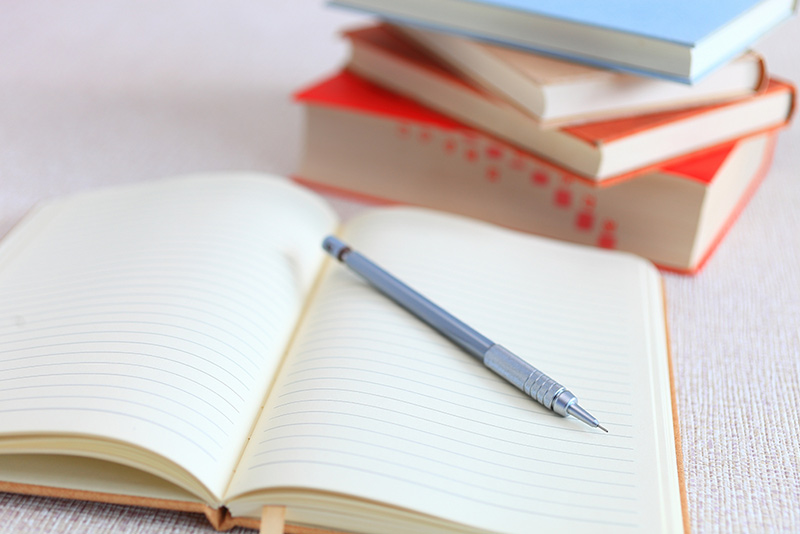相続放棄はしたほうが良い?放棄したほうが得な場合とは
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

相続放棄をすれば相続をせずにすみますが、「本当に相続放棄をして良いものか…」と悩んでしまう方も多いと思います。
そこで、この記事では、どんな場合に相続放棄をすべきか、相続放棄をする際にはどんなことに気を付けるべきかについて説明します。
相続放棄は、親の借金が多い場合や、特定の家族に家業を継がせたい場合など、いくつかの状況で有効な手段です
ただし、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。
一度相続放棄をすると、原則として撤回はできません。後から予期せぬ財産が見つかったとしても、相続できません。

目次
相続放棄は期限があるので要注意


相続の際には3つの選択肢がある
身内が亡くなると、その人が持っていた財産をどう処分するかという相続の問題が発生します。
相続の際には、相続する人(相続人)は亡くなった人(被相続人)のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も引き継ぐことになります。このため、場合によっては相続することによって大きな借金を抱えることにもなってしまいます。
相続による借金等の負担から逃れる機会を得るために、相続人は次の3つの相続方法の中から自分の希望する方法を選んで相続することが可能になっています。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
最もわかりやすい相続方法が単純承認です。「単純承認」は、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法です。相続の際に特に何も手続しなければ、自動的に単純承認したことになります。
次に、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐという方法が「限定承認」です。限定承認すると、相続した財産よりも借金の方が多い場合、相続人は財産を超える分の借金を返済する義務を負いません。
最後に、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないのが相続放棄になります。「相続放棄」をすれば、その人ははじめから相続人でなかった扱いになります。
相続放棄するなら3ヶ月以内に手続きが必要
上記3つの方法のうち、限定承認は相続人全員で手続きする必要があるなど利用しにくい制度となっており、あまり制度として利用されておりません。
ですから、実際には単純承認するか相続放棄するかで悩む方が多くなっています。
単純承認するなら手続きは不要ですが、相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
相続放棄には3ヶ月というタイムリミットがありますから、速やかに決断して手続きをとらなければならないということです。うっかり3ヶ月の期限が過ぎてしまえば、相続放棄ができなくなってしまい、借金を背負わなければならないことにもなってしまいます。

相続放棄をした方がいいのはどんな場合?
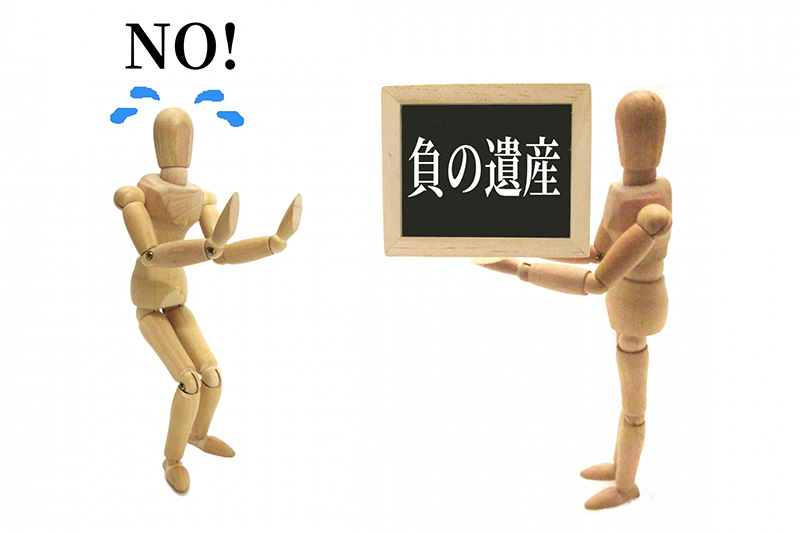

- 財産よりも借金の方が明らかに多い場合
- 被相続人が連帯保証人になっていた場合
- 家業を特定の相続人に引き継がせたい場合
- 他の相続人とかかわりたくない場合
- 借金のほかに生命保険金がある場合
- 被相続人の自宅を手放しても良い場合
財産よりも借金の方が明らかに多い場合
被相続人が多額の借金を残している場合には、相続財産を使っても返済しきれないことが多いでしょう。それほど多額の借金でなくても、財産自体が全くないようなら、借金だけを相続することになってしまいます。
このように、財産よりも借金が明らかに多い場合には、相続放棄をした方が良いでしょう。相続放棄をした後、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」の交付を受け、それを債権者に提示すれば、借金の請求から逃れることができます。
被相続人が連帯保証人になっていた場合
被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっている場合、被相続人自身は借金をしていなくても、連帯保証人としての債務が相続人に引き継がれることになります。
この場合、借金をしている本人が借金を返さなければ、債権者は相続人のところに請求してきますから、相続人が借金を返済しなければならないことになってしまいます。
このような心配がありますので、最初から相続放棄をしておいた方が安心です。
家業を特定の相続人に引き継がせたい場合
被相続人が事業を営んでいた場合、複数の相続人が事業にかかわる財産を相続すると、スムーズな意思決定ができなくなってしまい、事業に支障をきたすことがあります。
このような事態に備えるために、経営者が亡くなった後、事業の承継人以外は相続放棄をするという方法があります。
他の相続人とかかわりたくない場合
相続手続きのためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。自分が相続人となって財産を相続するとなると、自分も遺産分割協議に参加しなければなりません。
他の相続人と全く付き合いがない場合などは、財産分けの話し合いに加わること自体気が重いことがあると思います。特に、叔父・叔母が亡くなり、その兄弟姉妹や甥・姪の複数人が相続人となるような場合には、お互いに付き合いがないケースも多いでしょう。このような場合、相続財産にこだわりがなければ、相続放棄をすることにより煩わしさを避けることができます。
借金のほかに生命保険金がある場合
相続放棄をすれば、「生命保険金も受け取れないのでは…」と相続放棄を躊躇する方も少なくないと思います。
しかし、生命保険金というのは被相続人が死亡時に所有していた財産ではなく、死亡後に保険会社から支払われるものになりますから、相続財産には含まれません。
たとえ相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができますから、相続財産がマイナスになるようであれば相続放棄を考えた方が良いでしょう。
被相続人の自宅を手放しても良い場合
たとえば、被相続人が自分の家で息子一家と同居していた場合、その息子は相続放棄をすれば住む家を失ってしまうことになります。このような場合には、被相続人が多額の借金を残していたとしても、相続放棄には慎重になるべきです。
逆に、被相続人が一人暮らしで誰も自宅を引き継ぐ人がいない場合などは、相続放棄をしても相続人の生活に大きな影響はないことが多いですから、借金があるなら相続放棄をした方が良いでしょう。
相続放棄する場合の注意点


- 既に相続財産に手を付けていたら相続放棄できない
- 次順位の相続人に迷惑がかかる
- 相続放棄は撤回できない
既に相続財産に手を付けていたら相続放棄できない
相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内であれば必ずできるというわけではありません。
法定単純承認といって、民法により単純承認したとみなされるケースがあり、この場合には相続放棄ができなくなってしまいます。
たとえば、被相続人の財産を使い込んでしまった場合などは、法定単純承認となり、相続放棄はできません。
次順位の相続人に迷惑がかかる
相続放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
たとえば、被相続人に配偶者と子がいれば、通常は相続人となるのは配偶者と子のみです。
しかし、このケースで子が相続放棄をした場合、被相続人の親が生きていればその親が、親が亡くなっていたとしても兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人になってしまいます。
自分が相続放棄をすることで他の人が借金を引き継がなければならない可能性もありますので、相続放棄をするなら事前に関係者に通知した上で、全員で行うという形が良いでしょう。
相続放棄は撤回できない
一度行った相続放棄は、たとえ相続開始から3ヶ月以内でも撤回できません。被相続人に思わぬ財産が見つかった場合でも、相続放棄した後であれば、それを引き継ぐことができなくなってしまいます。
相続放棄するなら、相続財産の調査を十分行ってからにすべきでしょう。
相続放棄は一度すると撤回できません。借金があるから直ちに相続放棄するというのではなく、よく考えた上で手続した方が安心です。
すぐに相続財産の詳細がわかりそうにない場合には、本来の3ヶ月の期限内であれば相続放棄の期限の延長も申請できます。
まとめ
相続放棄は、多額の借金を引き継ぐリスクを回避するための有効な手段です。しかし、手続きには「相続開始を知ってから3ヶ月以内」という厳格な期限があり、一度受理されると原則として撤回はできません。
相続放棄をするかどうかは、財産と借金のどちらが多いかだけでなく、他の相続人への影響や、大切な自宅を手放すことになる可能性など、様々な要素を考慮して慎重に判断する必要があります。
安易な判断は後々の大きな問題につながる可能性があるため、迷った場合は専門家への相談を検討することも重要です。この記事が、相続放棄について考える際の判断材料となれば幸いです。

お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2026/01/20
代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?