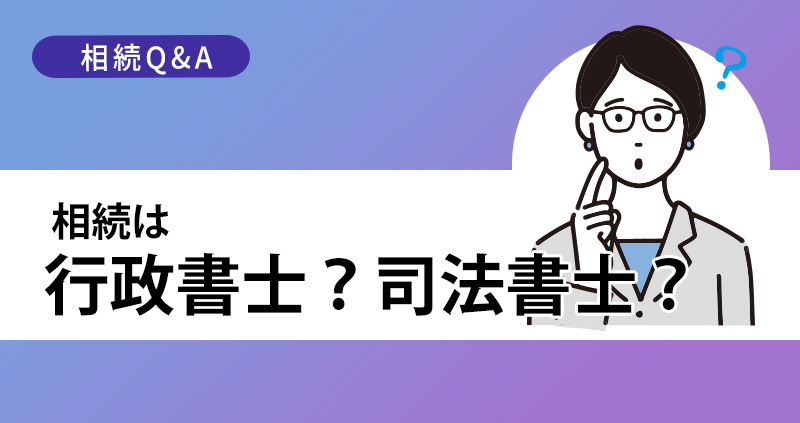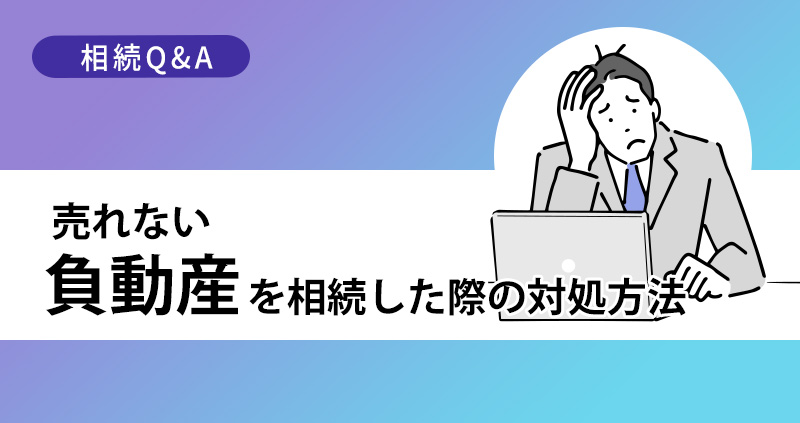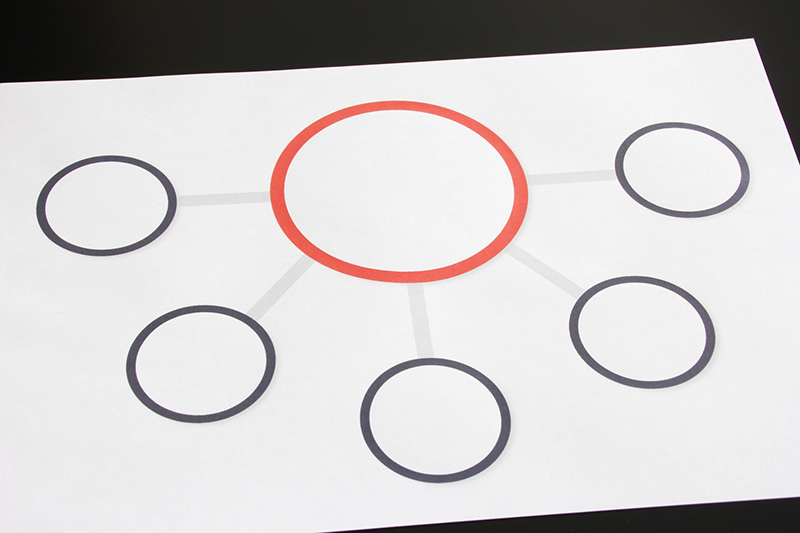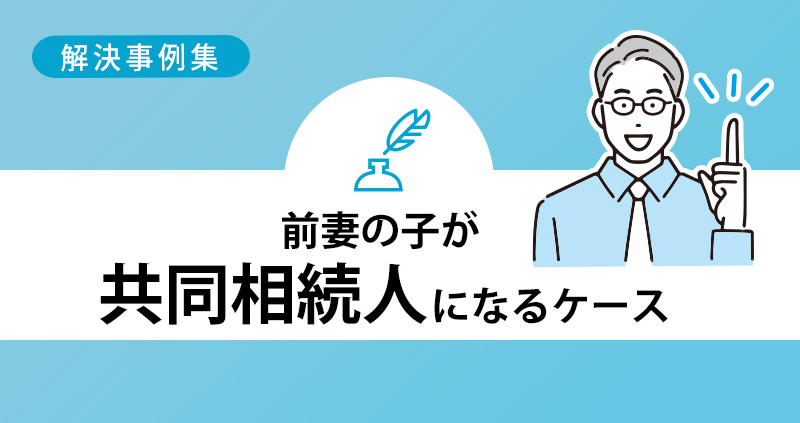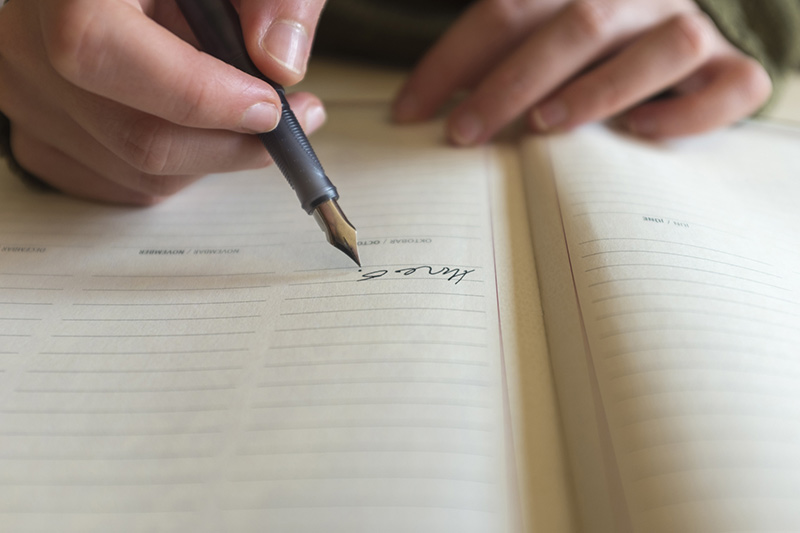相続手続きの代理人選びで重要なこと。あなたにあった代理人とは?
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
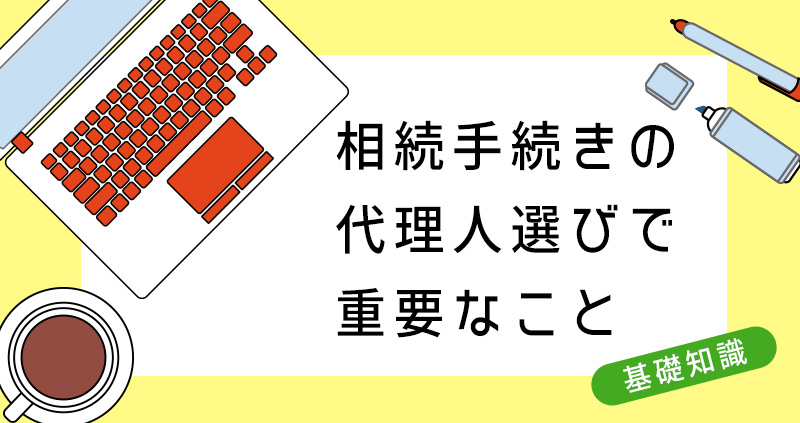
相続の際には、様々な手続きが発生するため、代理人に頼みたいと思うことも多いでしょう。代理人として相続手続きをしてもらえる専門家はたくさんいます。ただし、相続手続きの内容によって依頼できる専門家が違ってきますので、注意しておかなければなりません。
ここでは、相続の際に必要な手続きごとに、代理人に依頼するならどういった人になるのか、何に注意しておくべきかなどをまとめています。相続手続きの代理人を選ぶ場合の参考にしていただければ幸いです。
相続手続きは代理人に依頼できる

面倒な相続手続きは代理人に任せるのがおすすめ
家族や親戚など、身近な人が亡くなると、遺産を相続する手続きが必要になります。相続手続きの種類は多く、手間がかかってしまいますが、避けては通れません。相続手続きの中には期限が設けられているものもあり、うっかりしていると手続きができなくなってしまうこともあります。
相続手続きを全部自分たちでやろうとすると、労力もかかり、時間のロスになってしまいます。法律知識をもっていて、書類作成等の手続きにも慣れた専門家に相続手続きの代理人となってもらえば、うっかりミスすることもなく、スムーズに相続手続きを完了させることができます。
手続きによって依頼できる専門家が異なる
相続に関する法律的な手続きについては、職業上代理人となれる人が法律によって決まっています。相続手続きを専門家に依頼する場合には、それぞれの専門家ができる業務の内容について知っておくと便利です。
相続手続きを依頼できる主な専門家としては、弁護士、司法書士、行政書士、税理士があります。各専門家が代理人となれる業務の違いは、大まかには次のとおりです。
弁護士
相続手続き全般の代理人となることができます。裁判所の手続きで代理人となれるのは、弁護士のみになります。
司法書士
司法書士は、「遺産整理受任者」として相続手続き全般の代理人となることができます。相続登記の代理人になることができるのも司法書士と弁護士のみです。他の専門家に相続の手続きを依頼した場合にも、通常、相続登記については司法書士を紹介してもらうことになります。また、司法書士は、裁判所提出書類を作成することもできます。
行政書士
遺産分割協議書などの「権利義務に関する書類」を代理人として作成することができます。
税理士
税務申告の代理人となれるのは、税理士のみになります。相続税の申告手続きを依頼したいなら、税理士に頼む必要があります。
信託銀行が相続手続きの代理人となってくれるサービスもある
信託銀行では、相続手続きの一切を任せられる遺産整理のサービスを行っています。信託銀行の遺産整理サービスを利用すれば、信託銀行が代理人となって相続手続きを行うことになります。
ただし、上にも書いたとおり、相続手続きの中には特定の専門家しかできないものもあります。相続手続きを信託銀行に依頼した場合でも、通常は提携している司法書士や税理士が、相続人の代理人として相続登記や相続税申告を行うことになります。
また、信託銀行の遺産整理サービスは、一般的に富裕層向けのサービスのため費用が割高になるというデメリットがあります。
代理人は誰に依頼すればいいの?
相続人調査の代理人

相続人調査とは?
相続が起こったら、まず、相続人を確定します。相続人の確定のためには、役所から戸籍謄本を取り寄せる作業が必要になります。相続に必要な戸籍謄本は膨大になることがあり、自分で必要な戸籍謄本をすべて取り寄せしようとすると、大変な時間と労力がかかってしまうこともあります。古い戸籍は読み取るだけでも困難なため、役所に問い合わせなければならないこともあります。
相続人調査を代理人に依頼するには?
相続人調査を代理人に依頼したい場合、通常は、行政書士、司法書士、弁護士になります。行政書士、司法書士、弁護士が役所に戸籍謄本を請求する場合には、職務上請求といって職務上与えられている権限により請求ができますので、委任状も不要です。
相続人調査だけを依頼したい場合には、どの専門家に依頼しても特に違いはありません。一般的には、弁護士に依頼するよりも、行政書士や司法書士に依頼した方が費用を抑えることができます。行政書士、司法書士、弁護士には、相続関係説明図も作成してもらえます。
他の相続手続きと合わせて依頼したい場合には、他にどんな相続手続きが必要になるかによって依頼先を考えた方がよいでしょう。たとえば、不動産の相続登記が必要になる場合、対応できる専門家は司法書士のみになりますから、司法書士に依頼するのがおすすめです。また、遺産分割で紛争になることが予想されるなら、弁護士に依頼すれば、代理人として他の相続人と交渉してもらうことができます。
- 行政書士
- 司法書士
- 弁護士
相続財産調査の代理人

相続財産調査とは?
相続財産調査とは、被相続人の身の回りを調べ、相続財産としてどんなものがあるのかを確定させる作業になります。相続財産調査も、相続手続きの前提として、必ずしなければならない作業です。
相続財産調査では、役所や法務局で不動産の状況を確認したり、金融機関で預金の残高証明を取得したりする手間がかかってしまいます。また、被相続人に負債がある場合には相続放棄を検討しなければなりませんから、速やかに調査を行わなければなりません。
相続財産調査が終わり、相続財産が確定したら、相続財産目録を作成しておくと後の相続手続きがスムーズです。
相続財産調査を代理人に依頼するには?
相続財産調査を代理人に依頼するなら、通常は、行政書士、司法書士、弁護士になります。相続人調査と同様、他にどんな相続手続きが必要になるかによって依頼する専門家を検討するとよいでしょう。
行政書士、司法書士、弁護士に代理人を依頼すれば、金融機関で預貯金の残高証明書を取得してもらったり、法務局で登記事項証明書を取得してもらったりすることもできます。
- 行政書士
- 司法書士
- 弁護士
遺言の検認の代理人
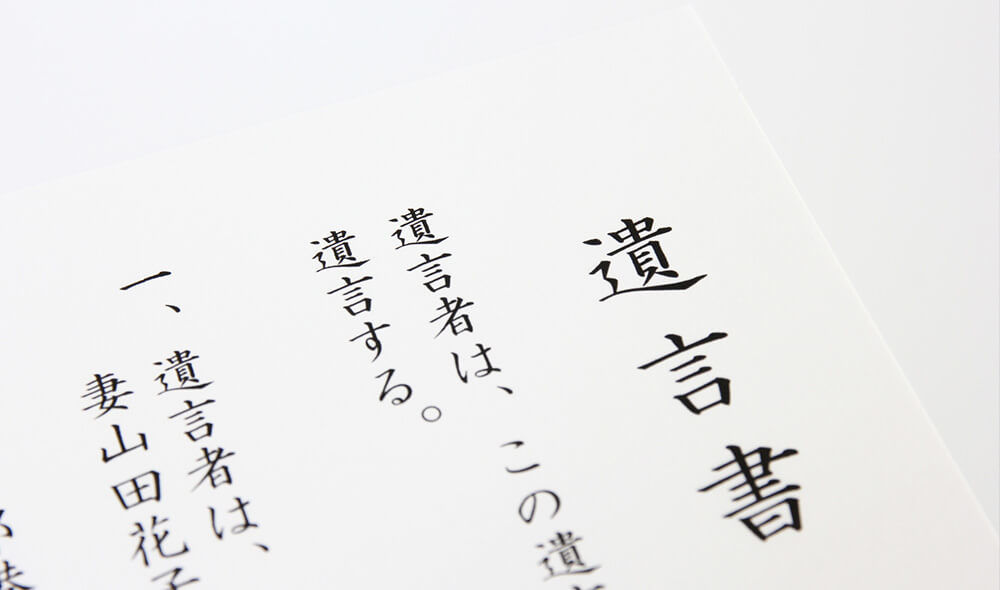
遺言の検認とは?
被相続人が遺言を残している場合には、遺言に従って相続手続きを行うことになります。ただし、被相続人の残している遺言が自筆証書遺言である場合には、相続手続きを行う前に、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
検認とは、遺言書の偽造や変造を防止し、遺言書の記載を確認するための手続きになります。検認を受け、家庭裁判所に検認済証明書を付けてもらうと、遺言書にもとづく相続手続きが可能になります。
遺言の検認を代理人に依頼するには?
自筆証書遺言の検認を受けるには、家庭裁判所に検認申立てをする必要があります。検認申立ての代理人になれるのは弁護士のみになります。なお、検認は遺言の有効性を判断する手続きではありません。相続人は検認期日に必ず立ち会わなければならない義務はなく、検認期日に出席できない場合でも、代理人に依頼する必要はありません。
遺言の検認は、司法書士に依頼することも可能です。司法書士には裁判所提出書類の作成権限がありますので、司法書士に依頼して検認申立書を作成してもらい、検認済証明書を取得してもらうことも可能です。
- 弁護士
- 司法書士
公正証書遺言の調査の代理人
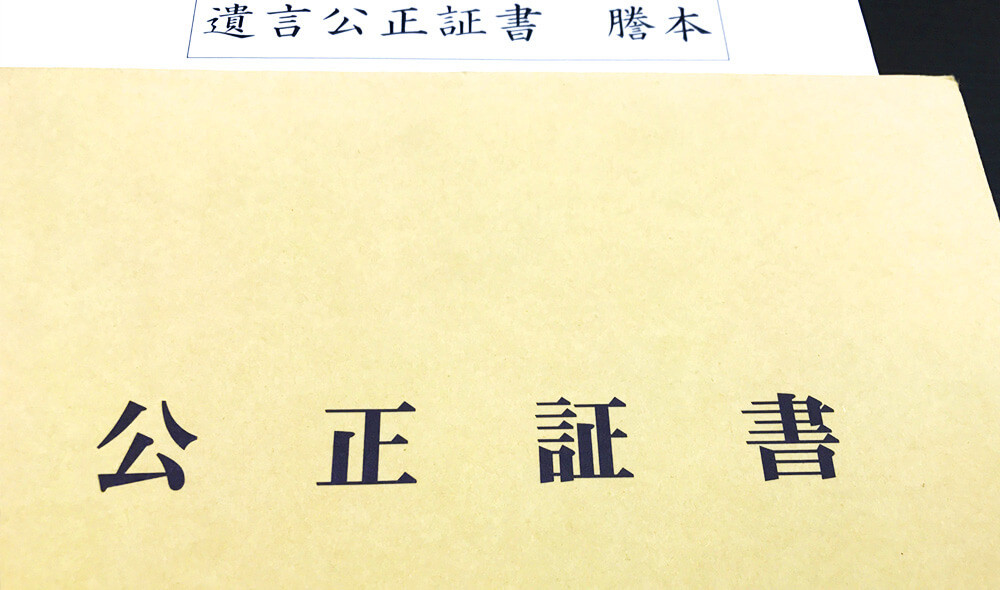
公正証書遺言の調査とは?
全国各地の公証役場で作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会の遺言検索システムを利用して検索することができます。被相続人が遺言を残しているかどうかわからない場合には、相続人は公証役場へ行って公正証書遺言の有無を確認できます。
公正証書遺言の調査を代理人に依頼するには?
相続人が自ら公証役場に行って公正証書遺言の調査ができない場合には、代理人に依頼することも可能です。公正証書遺言の調査をするのに必要な資格などはありませんが、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家に代理人を依頼するのが安心です。
- 行政書士
- 司法書士
- 弁護士
相続放棄の代理人

相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人としての立場を放棄し、被相続人の残した財産も負債も一切引き継がないことを表明する手続きです。被相続人に多額の借金がある場合には、相続放棄をすることで、相続人は借金の負担を逃れることができます。
相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で「相続放棄の申述」の手続きをとらなければなりません。何もしないまま3か月の期限が過ぎてしまうと、それ以降相続放棄はできなくなってしまうため、期限には十分注意する必要があります。
相続放棄を代理人に依頼するには?
相続放棄の申述は、弁護士に代理人として手続きしてもらうことができます。また、司法書士も家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成ができますので、司法書士に相続放棄を依頼することも可能です。
相続財産調査に時間がかかり、相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄をすべきかどうか判断できない場合には、相続放棄ができる期間を延長することも可能です。この場合にも、弁護士または司法書士に依頼すれば、家庭裁判所に書類を提出し、期間延長の手続きをとってもらえます。
- 弁護士
- 司法書士
相続放棄で代理人が必要なケースとは?
未成年者である相続人が相続放棄をする場合、未成年者は自分一人で法律行為(権利の変動などの法律上の効果を生じさせる行為)をすることができないため、代理人が必要になります。未成年者の代理人となるのは、原則として法定代理人である親権者になります。
ただし、親権者と未成年者の両方が相続人になっていて、次のi)、ii)に該当する場合には、親権者と未成年者の利益が相反することになるため、特別代理人の選任が必要になります。
親権者のみ相続放棄するケース
複数の子(未成年者)のうち一部の子だけが相続放棄するケース
特別代理人とは、本来の代理人が代理権を行使できない場合や代理人がいない場合に、裁判所が選任する代理人のことです。未成年者の相続放棄のために特別代理人が必要になる場合には、親権者が家庭裁判所に申し立てをすると、家庭裁判所が特別代理人を選任します。
限定承認の代理人

限定承認とは?
限定承認は、相続によって得た財産を限度として被相続人の負債を受け継ぐ相続方法です。被相続人に借金などの債務がどれくらいあるかわからず、財産が残る可能性がある場合に、限定承認をすれば相続人は残った財産を引き継ぐことができます。
限定承認も、相続放棄と同様、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に「限定承認の申述」をして手続きします。限定承認は、相続放棄と違い、相続人全員で手続きしなければなりません。また、限定承認の申述をした後、相続人または相続財産清算人が、相続財産を清算する手続きを行う必要があります。
限定承認を代理人に依頼するには?
相続の際に限定承認をしたい場合には、弁護士に代理人になってもらうことができます。また、司法書士に依頼して限定承認申述書を作成してもらい、家庭裁判所で限定承認の手続きをすることも可能です。
- 弁護士
- 司法書士
遺産分割協議の代理人

遺産分割協議とは?
相続人が複数いる場合、相続財産は相続開始時には相続人全員が法定相続分で共有している状態となっています。相続財産を各相続人固有の財産に分けるには、遺産分割の手続きを行わなければなりません。
遺産分割は、原則的に相続人全員の話し合いによって行うこととなっており、この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議が成立すれば、「遺産分割協議書」を作成しておく必要があります。
遺産分割協議を代理人に依頼するには?
他の相続人と直接話したくない場合などには、代理人に遺産分割協議を行ってもらうことも可能です。遺産分割協議において、代理人として他の相続人と交渉ができるのは、弁護士のみになります。遺産分割協議の代理人を依頼したい場合には、弁護士に頼む必要があります。遺産分割協議が成立した場合、遺産分割協議書は、行政書士が代理人として作成することができます。
- 弁護士
- 行政書士
遺産分割協議で代理人が必要なケースとは?
遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。しかし、相続人の中には、法律の定めなどにより、遺産分割協議に自らが参加できない人がいます。本人が遺産分割協議に参加できないケースでは、代理人が参加することになります。遺産分割協議で、代理人の参加が必要なケースは、次のようなケースになります。
相続人の中に未成年者がいる場合
遺産分割協議は法律行為に該当しますので、未成年者は遺産分割協議に参加できません。相続人が未成年者の場合には、法定代理人である親権者が遺産分割協議に参加することになります。
ただし、親権者と未成年者のどちらもが相続人になるケース(夫が亡くなって妻と子が相続人になるケースなど)では、親権者と未成年者の利益が相反するため、親権者は未成年者を代理して遺産分割協議を行うことができません。この場合には、親権者は家庭裁判所に申し立て、特別代理人を選任してもらう必要があります。
相続人の中に認知症の人がいる場合
認知症の人は、判断能力が低下しているため、自分で法律行為ができないと考えられています。相続人の中に認知症の人がいる場合、その人は遺産分割協議に参加できませんので、代理人が必要になります。認知症の人に代理人(後見人)をつけるには、成年後見制度を利用する必要があります。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。任意後見は、本人が判断能力のあるうちに後見人候補者を選び、後見人となってもらう契約を結ぶ方法です。一方、法定後見は、本人の判断能力が低下してしまった後で、本人や親族が家庭裁判所に申し立てて、後見人を選任してもらう方法です。
遺産分割協議が必要になったとき、認知症の相続人に既に任意後見人がついている場合には、任意後見人が遺産分割協議に参加します。認知症の相続人に任意後見人がついていない場合には、法定後見を利用することになりますので、家庭裁判所に後見開始申し立てをし、法定後見人を選任してもらう必要があります。この場合、法定後見人が選任されたら、法定後見人を認知症の相続人の代理人として、遺産分割協議を行います。
相続人の中に行方不明の人がいる場合
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ有効にはなりませんから、連絡先のわからない相続人がいる場合でも、可能な限り探し出して連絡をとる必要があります。しかし、相続人の住民票上の住所を突き止めたけれど、その住所に住んでおらず、連絡も全くとれないといったケースもあります。
相続人が行方不明で連絡がとれない場合には、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人を行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議を行うことができます。不在者財産管理人選任の申立ては、共同相続人などの利害関係人が行います。
遺産分割調停・遺産分割審判の代理人

遺産分割調停とは?
遺産分割協議を行ったけれど、相続人間で合意に至らない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停では、調停委員と裁判官から構成される調停委員会が、相続人の意見を聞きながら、話し合いで合意に至るよう調整を行ってくれます。
遺産分割審判とは?
遺産分割調停を行っても相続人全員の合意による遺産分割ができない場合には、調停不成立となり、遺産分割審判に移行します。遺産分割審判とは、裁判官(家事審判官)があらゆる事情を考慮したうえで、相続分に応じた遺産分割の方法を決定する手続きです。
遺産分割事件では、必ずしも調停から申し立てる必要はないので、審判の申し立ても可能です。ただし、審判を申し立てた場合にも職権で調停に付されるケースが多いため、結局は調停から審判という流れになるのが一般的です。
遺産分割調停・審判を代理人に依頼するには?
遺産分割調停や審判の手続きを代理人に依頼したい場合、家庭裁判所での調停や審判手続きを代理できるのは弁護士のみですから、弁護士に頼む必要があります。家庭裁判所に提出する遺産分割調停申立書や遺産分割審判申立書の作成については、司法書士に依頼することも可能です。
- 弁護士
- 司法書士
相続登記の代理人
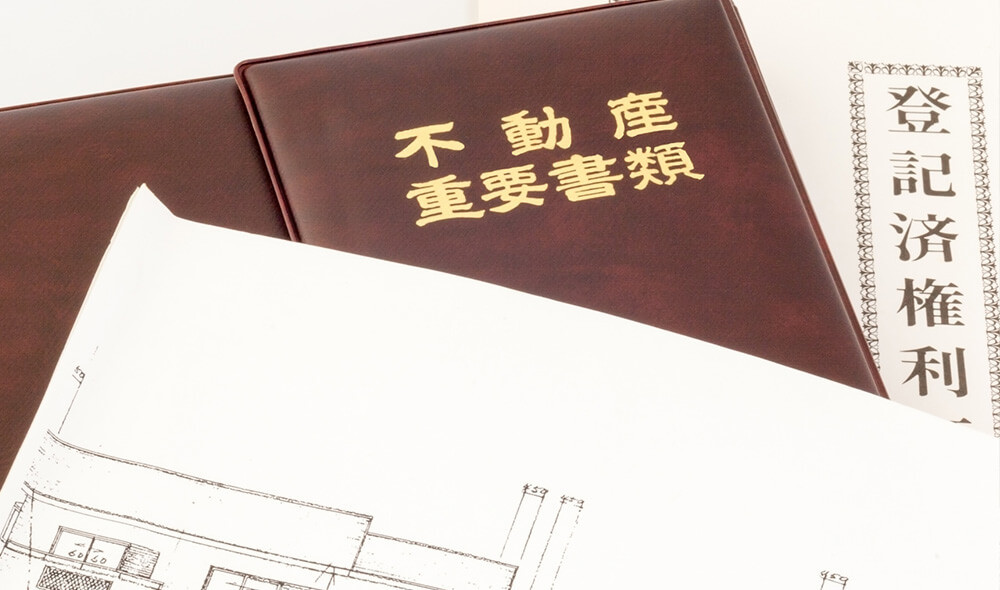
相続登記とは
相続財産の中に不動産がある場合には、法務局で不動産の名義を相続人に変更する手続きが必要になります。相続の際の不動産の名義変更は、相続登記と呼ばれます。
相続登記には期限はなく、必ず相続登記をしなければならない法律上の義務もありません。しかし、相続登記をしていなければ、不動産を相続して所有者となったことを第三者に対して主張することができないので、不動産を相続したら必ずしておくべき手続きです。相続した不動産を売却したいという場合でも、売却の前提として相続登記は必要です。
相続登記を代理人に依頼するには?
法務局での登記申請の代理人になれるのは、司法書士になります。相続登記を代理人に依頼したい場合には、司法書士に頼む必要があります。
- 司法書士
相続税申告の代理人

相続税の申告とは?
相続により財産を取得した場合には、相続税の課税対象になることがあります。相続税を計算するときには、相続財産の額から無条件で差し引きできる基礎控除額が設けられています。相続財産の額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額は、次の計算式で算出します。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人数
相続税がかかる場合には、相続開始を知った日の翌日から10か月に相続税の申告を行い、税額が発生する場合には納税を行う必要があります。
相続税申告を代理人に依頼するには?
相続税申告の代理人になれるのは、税理士のみになります。相続税では、財産の評価方法によって税額が大きく変わることもありますので、相続税の申告は相続に詳しい税理士に任せるのが安心です。
- 税理士
預貯金の相続手続きの代理人
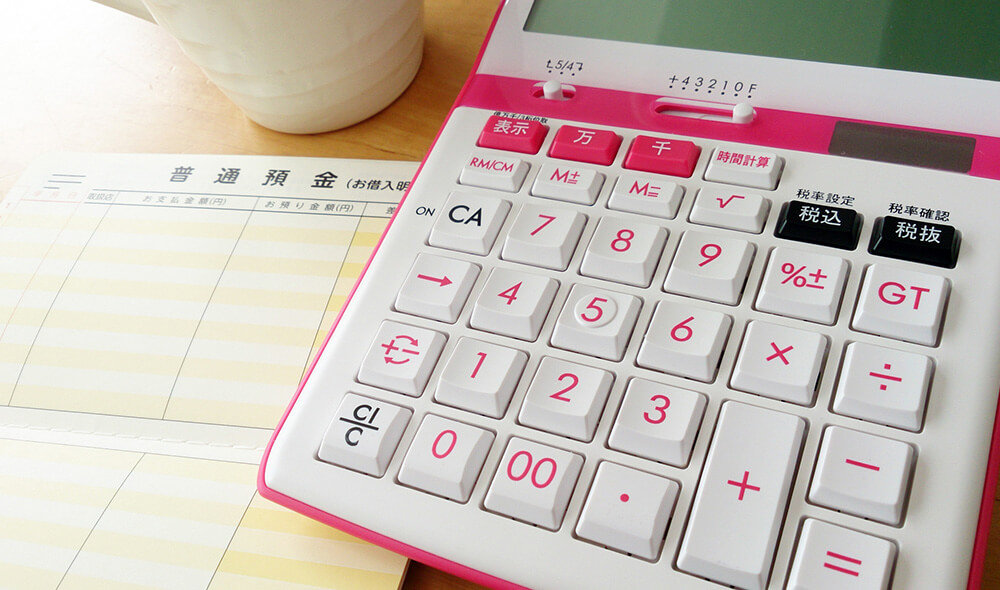
預貯金の相続手続きとは?
被相続人の預貯金口座は、金融機関が死亡を知った時点で凍結され、一切の入出金ができなくなります。口座の凍結を解除するには、金融機関に必要書類を提出して、預貯金の相続手続きを行わなければなりません。
被相続人が預貯金に関して遺言を残していない場合には、遺産分割協議で預貯金を相続する人を決めたうえで、遺産分割協議書を添付して預貯金の相続手続きを行います。遺言がある場合には、遺言書を添付して手続きすることになります。預貯金の相続手続きを行えば、預貯金を解約したり、相続人名義の口座に入金してもらったりすることができます。
預貯金の相続手続きを代理人に依頼するには?
預貯金の相続手続きの代理人となるのに、必要な資格などはありません。専門家に依頼する場合には、行政書士、司法書士、弁護士のいずれにも依頼ができます。預貯金の相続手続きを代理人に依頼する場合の必要書類などは、金融機関によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
- 行政書士
- 司法書士
- 弁護士
株式の相続手続きの代理人

株式の相続手続きとは?
被相続人の保有していた株式は、遺言により指定された人もしくは遺産分割協議で決まった相続人が相続することになります。株式の相続手続きでは、株式の名義変更を行います。上場株式については証券会社で名義変更手続きを行いますが、非上場株式については名義変更の方法を発行会社に確認する必要があります。
上場株式は電子化されており、株式を保有するには証券口座が必要になります。証券口座を持っていない人が上場株式を相続する場合には、証券口座の開設の手続きも必要になります。
株式の相続手続きを代理人に依頼するには?
株式の相続手続きを代理人に依頼する場合、代理人となってもらう人に必要な資格などはありません。親族以外に依頼する場合には、行政書士、司法書士、弁護士などの専門家または信託銀行などになります。株式の相続手続きを代理人に依頼する場合に必要な書類などは、証券会社によって異なりますので、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
- 行政書士
- 司法書士
- 弁護士
自動車の相続手続きの代理人

自動車の相続手続きとは?
被相続人名義の自動車がある場合には、自動車の相続手続きが必要になります。自動車に関する遺言があれば遺言に従いますが、自動車に関する遺言がない場合には、遺産分割協議で自動車を相続する人を決めます。
自動車の相続手続きでは、遺産分割協議書または遺言書を添付して、運輸支局または自動車検査登録事務所で名義変更を行います。なお、査定価格が100万円以下の自動車を1人の相続人が相続する場合には、遺産分割協議書のかわりに遺産分割協議成立申立書を提出して簡易な手続きができるようになっています。
相続した車を利用するつもりがなく、廃車にしたり売却したりする場合にも、自動車の相続手続きが必要になります。自動車の相続手続きをしていない場合でも、自動車税の納税義務は相続人が引き継ぐことになります。被相続人の自動車を使う予定がない場合には、速やかに相続手続きを行って処分した方がよいでしょう。
自動車の相続手続きを代理人に依頼するには?
自動車の相続手続きを専門家に依頼する場合には、行政書士に頼むことになります。自動車の登録や名義変更は、行政書士の代表的な業務の一つです。自動車の相続手続きを行政書士に依頼すれば、代理人となって自動車の名義変更を行ってくれます。
- 行政書士
相続不動産の売却の代理人

相続不動産の売却とは?
相続した不動産を利用する予定がないので売却したいというケースも多いと思います。相続不動産をすぐに売却する場合でも、売却前に相続手続き(相続登記)が必要です。相続登記完了後、買主を探して売却の手続きを進めることになります。
相続不動産の売却を代理人に依頼するには?
相続不動産の売却の代理人は、不動産会社のほか、司法書士にも依頼することができます。ただし、不動産の買主が特定していない場合には、不動産会社が仲介業務を行うことになります。通常、司法書士に不動産売却を依頼した場合には、不動産会社と提携して売却手続きの一切をサポートしてもらえます。
- 司法書士
遺留分減殺請求の代理人
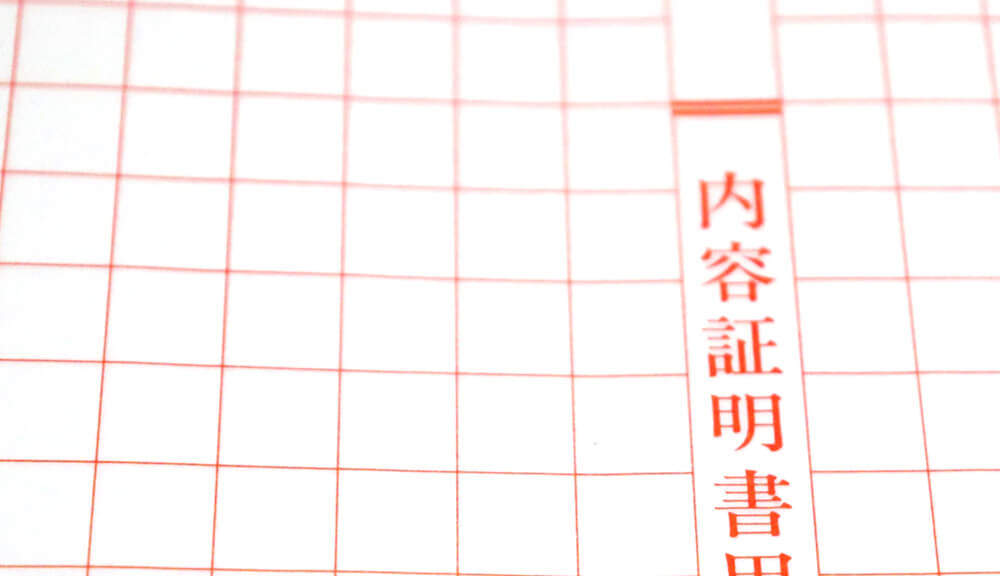
遺留分減殺請求とは?
被相続人が遺言を残している場合、遺言の内容によっては、相続人が本来相続できたはずの財産も相続できなくなってしまうことがあります。兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」という最低限の取り分が民法上保障されています。遺言により遺留分を相続できなくなった相続人は、遺留分減殺請求を行って、遺留分の取り戻しができます。
遺留分減殺請求を代理人に依頼するには?
遺留分減殺請求には、法律上定められている方式などはありませんが、請求したことの証拠を残すために、内容証明郵便を利用するのが一般的です。
遺留分減殺請求の内容証明郵便作成は、行政書士に依頼することもできます。ただし、行政書士には内容証明郵便を作成してもらうことはできますが、代理人となって相手方と交渉してもらうことはできません。代理人として相手方との交渉まで任せたいなら、弁護士に依頼する必要があります。
内容証明郵便を送った後も、相手方が話し合いに応じてくれない場合や、任意の返還に応じてくれない場合には、家庭裁判所に遺留分減殺請求調停(遺留分減殺請求による物件返還請求調停)を行うことができます。遺留分減殺請求調停の代理人は、弁護士に依頼する必要があります。調停申立書の作成だけなら、司法書士に依頼することも可能です。
- 行政書士
- 弁護士
法定相続情報証明制度の代理人
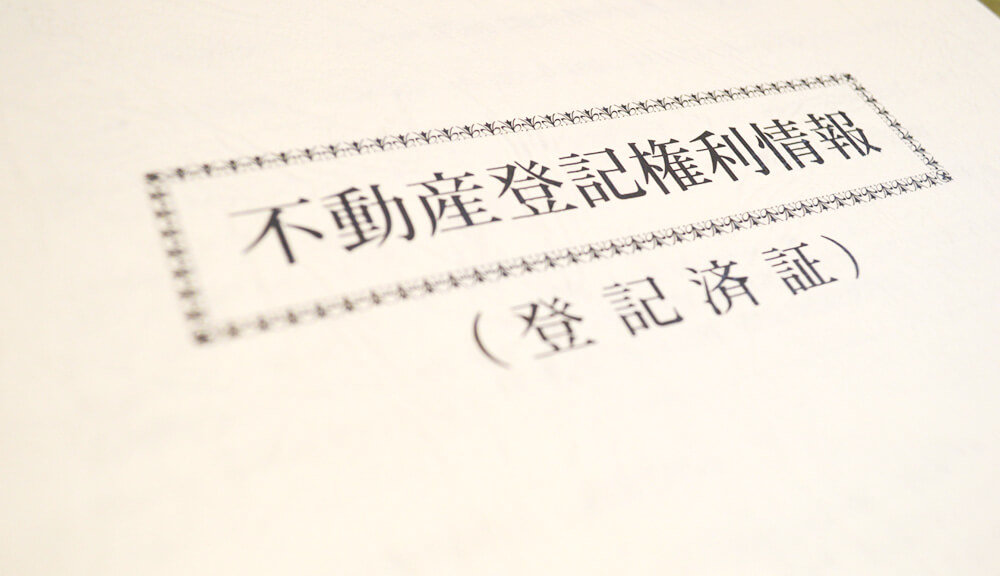
法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度は、相続手続きの便宜のために、平成29年度から始まった制度です。法定相続情報証明制度では、相続関係がわかる戸籍謄本一式と「法定相続情報一覧図」(相続関係説明図と同様のもの)を法務局に提出して保管を申し出ることにより、申出して以降5年間、法務局から法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらえます。
従来は、相続登記や預貯金の相続手続きなどの各種の相続手続きを行う際には、その都度役所や金融機関などに相続関係がわかる戸籍謄本一式を提出しなければなりませんでした。法定相続情報証明制度を利用すれば、法務局から交付してもらった法定相続情報一覧図の写しを添付するだけで相続手続きができるというメリットがあります。
法定相続情報証明制度の代理人を依頼するには?
法定相続情報一覧図の保管等の申出ができるのは相続人になりますが、代理人に依頼することも可能です。相続人の代理人として申出の手続きができるのは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の有資格者に限られます。
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
- 行政書士
まとめ

相続の際に必要となる手続きは種類が多く、煩雑になっています。相続手続きは専門知識をもった代理人に依頼するのがおすすめです。行政書士、司法書士等の専門家に相続手続きの代理人を依頼すれば、他の専門家とも提携して広い範囲の手続きを任せられるので、手間を省いて確実に手続きを完了させることができます。
お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2026/01/20
代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?