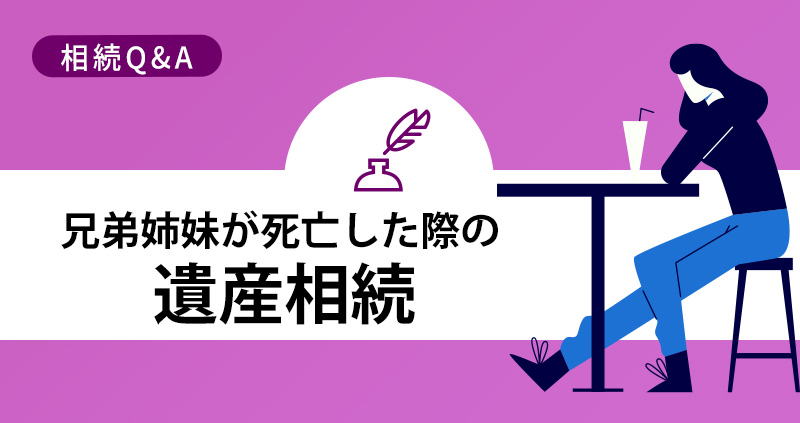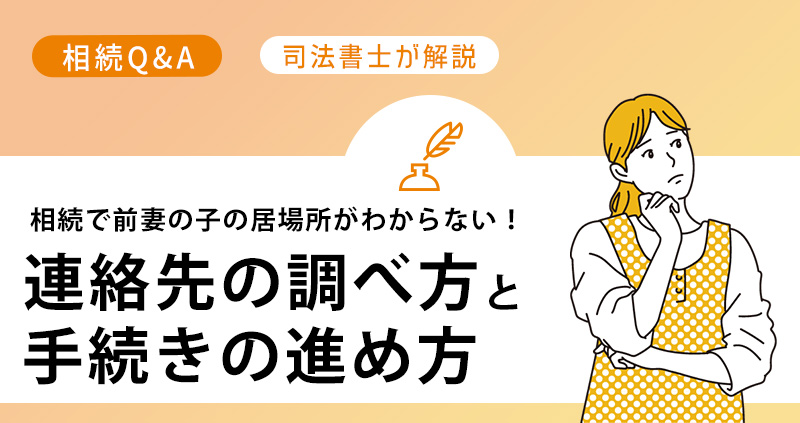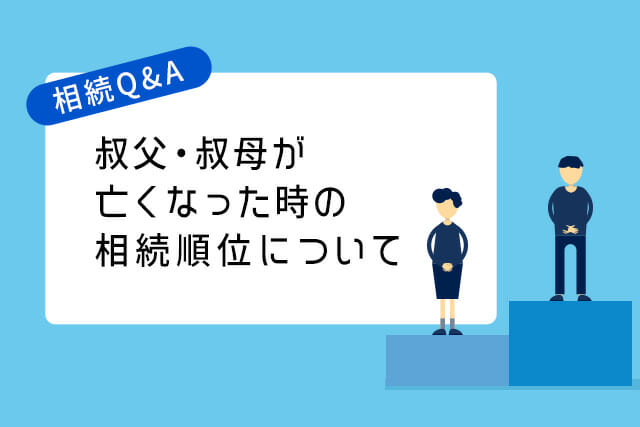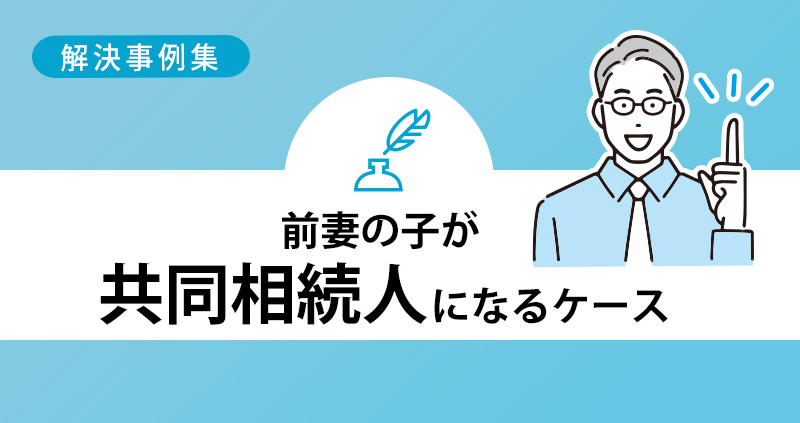【最新版】相続した不動産の名義変更(相続登記)を自分で!手続きの流れ・必要書類・義務化の注意点
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
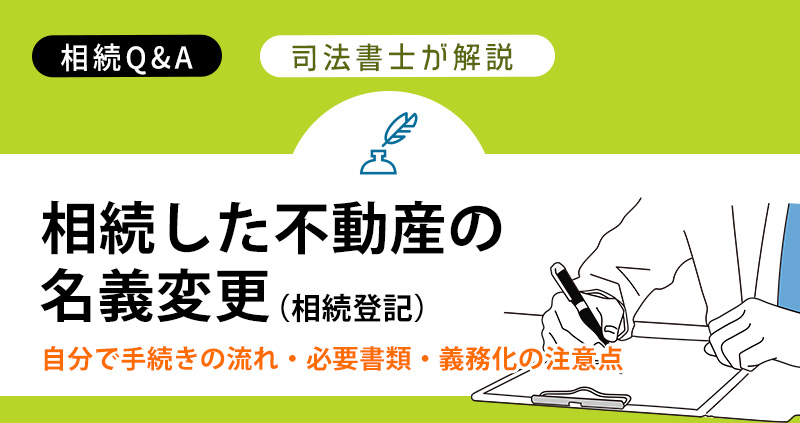

【義務化の要点】相続登記は2024年4月1日から義務化。不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必須で、違反すると10万円以下の過料リスクがあります。
【自分でできる】手順をしっかり理解すれば、費用を抑えて自分で申請は可能です。この記事で全手順と必要書類を詳しく解説します。
【注意点】戸籍収集や書類作成は複雑です。期限(3年)が設けられたため、ミスや遅延が過料につながるリスクも考慮し、不安なら専門家へ。


目次
知っておきたい「相続登記の義務化」について【法改正】


これまでの不動産の名義変更(相続登記)は任意でしたが、2024年4月1日から義務化されます。
義務化の背景には、所有者不明の土地が増加し、公共事業や災害復旧の妨げになっているという社会問題があります。
【義務化のポイント】
| 期限 | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要。 |
|---|---|
| 罰則 | 正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。 |
| 適用開始日 | 2024年4月1日 |
| 過去の相続 | 義務化開始前の相続についても適用されます。その場合、2027年3月31日までに申請が必要です。 |
義務化により、手続きの期限と罰則が設けられました。相続で不動産を取得したら、放置せずに速やかに名義変更を行うことが、これまで以上に重要になります。
相続した不動産の名義変更が必要な理由(義務化以前から重要)
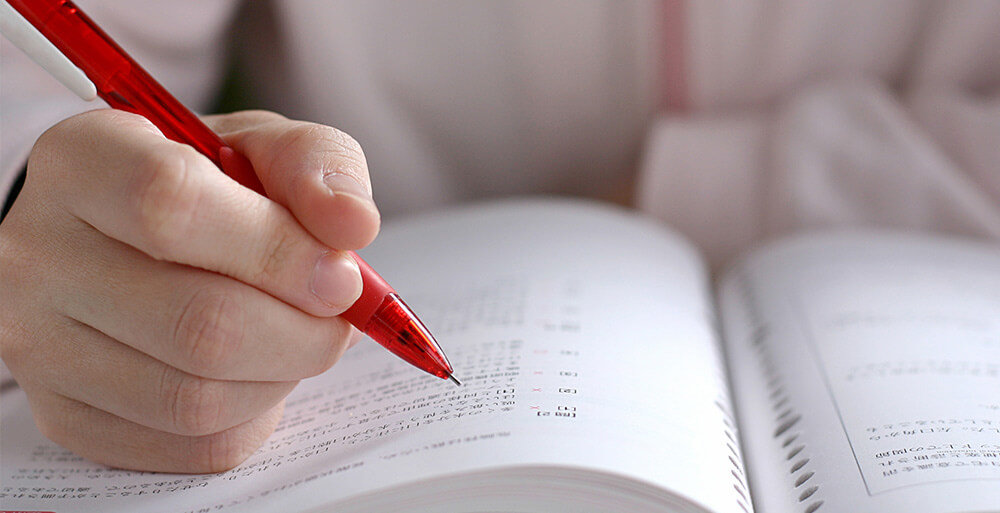

不動産は高額な資産ですが、外見だけでは誰の所有物か分かりません。そこで、国は登記記録というデータで所有者などの情報を公開し、不動産取引の安全を守る仕組みを設けています。
所有者が亡くなり、相続人に所有権が移転しても、法務局の登記記録を書き換えなければ、第三者からは誰が真の所有者か判断できません。
名義変更(相続登記)を行うことで、自分がその不動産の新しい所有者であることを公的に示し、売買や担保設定(ローンなど)を可能にするほか、後々の相続人間でのトラブルを防ぐ役割も果たします。
自分で名義変更(相続登記)をする具体的な手順
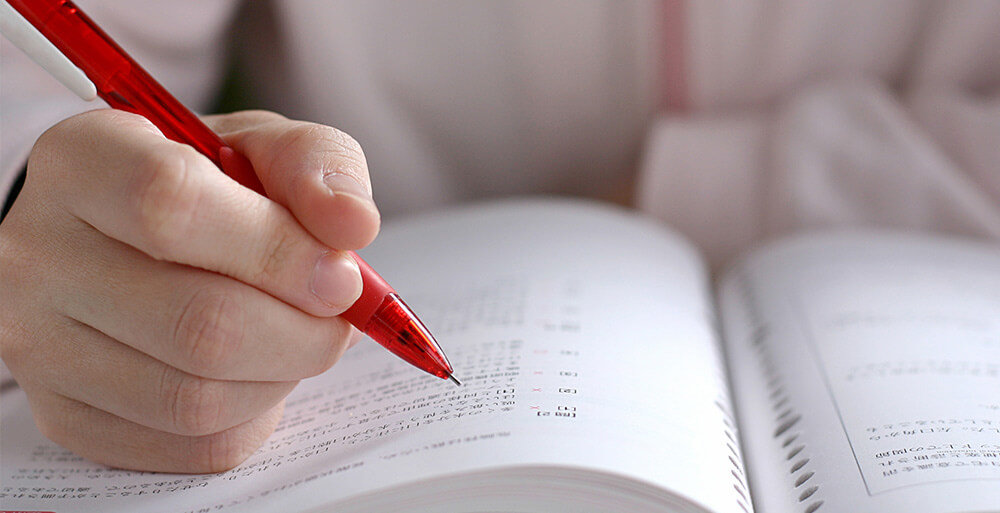

STEP1.不動産の登記事項証明書を取得して名義を確認
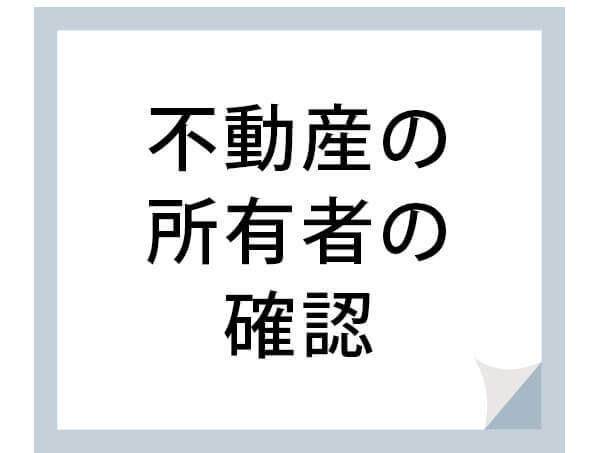
まず、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、現在の所有者名を確認します。
過去の相続で名義変更が漏れており、亡くなった方(被相続人)ではなく、さらにその前の代の所有者名義のままになっているケースも少なくありません。もしそうであれば、現在の相続登記の前に、前の代からの名義変更(数次相続登記)が必要になります。
登記申請のやり直しを防ぐためにも、必ず最初に名義の確認をしましょう。
| 取得場所 | 全国どこの法務局でも取得可能。 |
|---|---|
| 費用 | 不動産1個につき600円(窓口交付の場合)。土地・建物の両方なら1,200円。 |
STEP2.相続人を確定する(戸籍謄本などの収集)
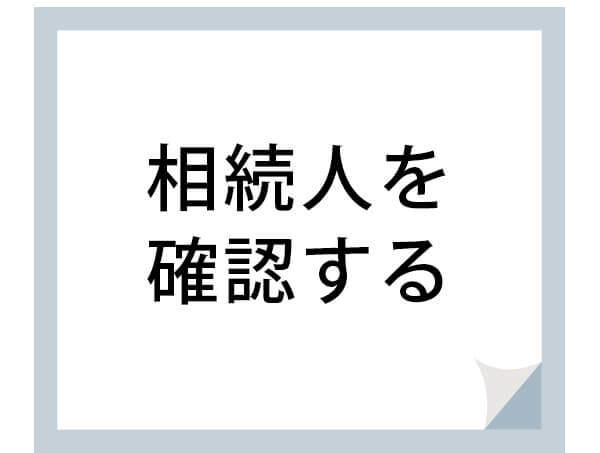
遺言書がない限り、相続人全員が不動産に対して権利を持ちます。そのため、手続きには法定相続人全員の関与が必要です。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍含む)を集めることで、民法上の法定相続人が誰なのかを確定します。
法定相続人とは?
法定相続人になる人は、被相続人の配偶者(夫・妻)と血族(血のつながった親族)の一部の人です。配偶者は常に相続人になりますが、血族は次の第1順位~第3順位の人が、先順位の人がいない場合に相続人になります。
| 第1順位 | 子(先に亡くなっていれば孫等が代襲相続) |
|---|---|
| 第2順位 | 直系血族(父母、祖父母等のうち最も世代が近い人) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(先に亡くなっていれば甥姪が代襲相続) |
戸籍謄本を取る手順
戸籍謄本を取るときには、大まかには次のような手順になります。
- STEP.01
- 被相続人の住所地の役所で本籍地入りの住民票(除票)を取得し、本籍を確認します。
- STEP.02
- 本籍地の役所に被相続人の死亡時の戸籍謄本を請求します。窓口に直接行く以外に郵送で請求することも可能です。請求の際には、本人確認書類が必要です。また、直系血族以外の戸籍謄本を取る場合には、相続人であることを証明できるものも必要になります。
- STEP.03
- 死亡時の戸籍謄本を見ると、1つ前の戸籍がわかりますので、その戸籍謄本を取り寄せます。こうして被相続人の出生時までの戸籍謄本を集めます。被相続人に子供がいない場合には、親や兄弟姉妹の生存確認のため、出生時より前の戸籍謄本が必要になることもあります。
- STEP.04
- 被相続人の戸籍謄本から、法定相続人に該当する人を突き止め、その人の現在の戸籍謄本までをたどって生存を確認します。
戸籍謄本の種類
戸籍謄本には、厳密には次の3種類があります。
| 戸籍謄本 | 現在有効な戸籍の写しです。コンピュータ化されて横書きになってからは「戸籍全部事項証明書」と呼ばれることもあります。取得手数料は1通450円になります。 |
|---|---|
| 除籍謄本 | 除かれた戸籍の写しのことです。結婚、離婚、死亡、転籍などにより、戸籍が空になれば、その戸籍は除籍となります。除籍謄本の取得手数料は1通750円です。 |
| 改製原戸籍謄本 | 戸籍はこれまでに何度か様式の変更(戸籍の改製)が行われています。改製時にはその時点で有効な内容のみが新しい戸籍に反映され、従前の戸籍は改製原戸籍として保存されます。改製原戸籍謄本の取得手数料は1通750円です。 |
STEP3.遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
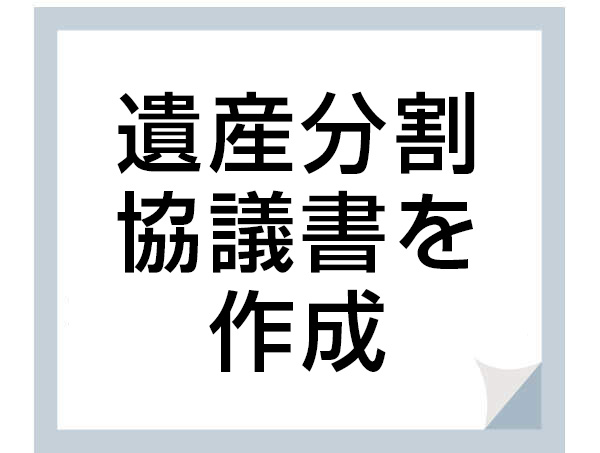
相続人が確定したら、誰が不動産を相続するのかを相続人全員で話し合って決めます(遺産分割協議)。
話し合いで合意した内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。名義変更手続きに必須の書類であり、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書が必要です。
- 協議書には不動産を特定できる情報(所在地、地番など)を正確に記載し、内容があいまいにならないよう注意しましょう。
相続人の連絡先がわからない場合
現在の本籍から戸籍の附票を取れば住民票上の住所がわかります。住所宛てに手紙を出すなどして連絡を試みましょう。
STEP4.名義変更に必要な書類の準備
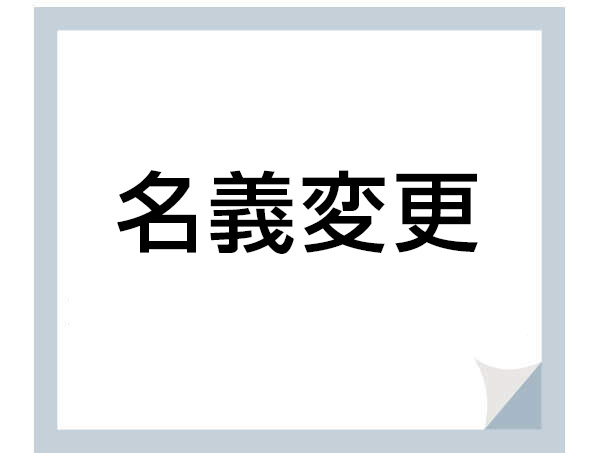
法務局で名義変更をする際には、次の書類が必要になりますので準備しておきましょう。
相続した不動産の名義変更手続きに必要な書類
・戸籍謄本
・被相続人の除票
・遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)
・不動産を相続する人の住民票
・固定資産評価証明書
(STEP.2)で揃えた戸籍謄本すべてが必要です。戸籍謄本を他の手続きにも使いたい場合、相続関係説明図をあわせて提出すれば、原本還付してもらえます。法定相続情報証明制度(※あらかじめ法務局に戸籍謄本一式を預けておく制度)を利用し、法定相続情報一覧図の交付を受けて提出する方法もあります。
被相続人が登記上の所有者と同一人物であることの確認のため、(STEP.2)で取得した除票も提出します。除票の代わりに戸籍附票を提出してもかまいません。
(STEP.3)で作成した遺産分割協議書が必要です。相続人全員の印鑑証明書もあわせて提出します。この印鑑証明書は3か月以内のものでなくてもかまいません。
遺産分割協議で不動産を相続することに決まった人の住民票が必要です。住民票の代わりに戸籍附票を提出してもかまいません。
法務局で登記申請する際には、登録免許税を払う必要があります。登録免許税の確認のため、不動産の固定資産評価証明書を提出します。固定資産納税通知書に付属している課税明細のコピーを提出してもかまいません。
STEP5.登記申請書の作成
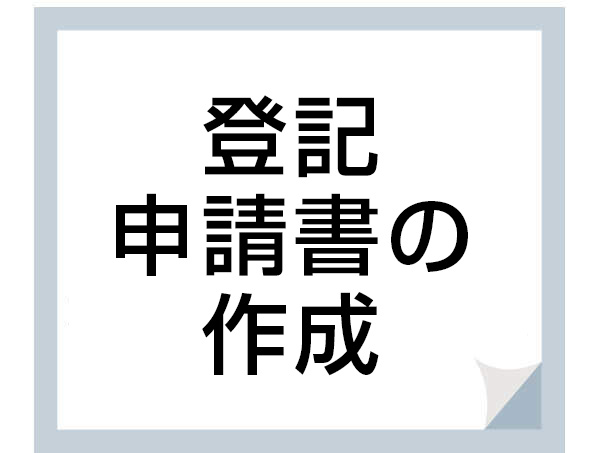
不動産の名義変更(相続登記)は、書面(登記申請書)を作成し、法務局に提出して行います。以下の流れに従って進めて行きましよう。
書式を入手する
登記申請書の書式(ひな形)は、法務局のホームページからダウンロードできます。 (例:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html)
適切な書式を選ぶ
相続のケース(遺産分割協議、遺言、法定相続など)に応じて、適切な書式を選んで作成します。たとえば、遺産分割協議で決めた場合は「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」を参考にします。
登録免許税の納付(収入印紙の貼付)
計算した登録免許税額に相当する収入印紙を用意し、登記申請書の所定の場所に貼り付けます。
提出
作成した登記申請書に、STEP 4で準備した必要書類一式をすべて添付し、不動産の所在地を管轄する法務局窓口に提出すれば申請完了です。
- 登録免許税は、固定資産評価証明書に基づいて計算した金額になります。申請書に印紙を貼り忘れたり、金額が不足したりすると補正(やり直し)が必要になるため、十分注意しましょう。
STEP6.法務局での申請手続き
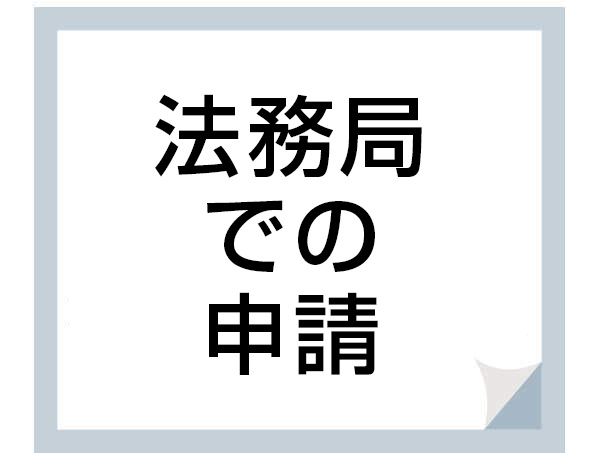
申請先の確認
登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局でのみ可能です。全国どこの法務局でも良いわけではないので注意が必要です。
申請方法
主な申請方法は以下の2つです。
| 窓口申請 | 平日の受付時間内に管轄法務局の窓口に提出。 |
|---|---|
| 郵送申請 | 書留等の追跡できる方法で郵送。 |
申請後の流れ
書類に不備がなければ、通常2~3週間程度で審査が完了します。
| 補正の指示 | 書類に不備があった場合、法務局から連絡があり、補正(訂正)のため法務局へ出向く必要があります。 |
|---|---|
| 完了 | 登記が完了すると、登記完了証と、権利証に代わる登記識別情報通知書が交付されます。 |
自分で名義変更をするメリット・デメリットと専門家への相談
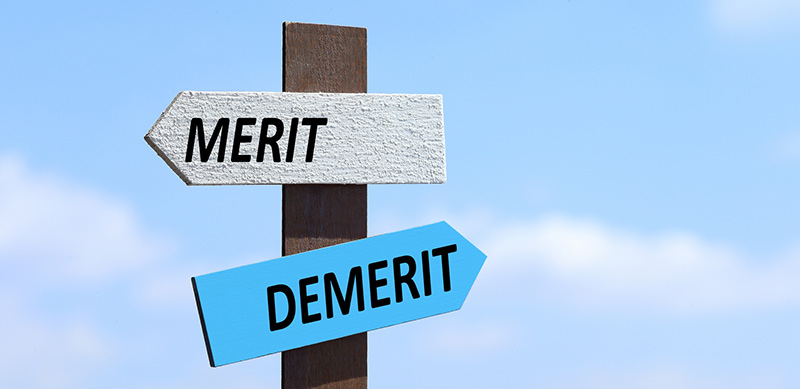

メリット:費用を抑えられる
自分で手続きをすれば、司法書士に依頼する場合の司法書士報酬がかかりません。費用は、登録免許税と各種証明書の取得費用といった実費のみとなります。
デメリット:時間と手間がかかり、リスクもある
主なデメリットは以下のとおりです。
| 平日昼間の時間確保 | 書類提出や完了書類の受領、そして不備があった場合の補正対応などで、平日の昼間に何度も法務局へ行く必要があります。 |
|---|---|
| 知識と調査の負担 | 戸籍の収集や登記申請書の作成は専門知識が必要で、特に複雑な相続(数次相続など)では時間がかかり、ミスが発生しやすいです。 |
| 義務化によるリスク | 義務化で3年以内の期限が設けられたため、手続きのミスや遅れが過料(罰則)につながるリスクが発生しました。 |
司法書士への相談は「期限と確実性」の解決策
相続登記の義務化により、3年以内という期限内で正確に手続きを完了させることの重要性が増しています。
自分で手続きを試みて期限に間に合わなかったり、不備が多くて手間取ったりするリスクを避けるためにも、司法書士に依頼するのが確実です。
司法書士は、戸籍収集、遺産分割協議書の作成サポート、登記申請まですべて代行でき、複雑な案件でもスムーズに、かつ正確に手続きを完了させることが可能です。
名義変更にかかる費用の目安


| 費用項目 | 概要 | 相場の目安 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 国に納める税金 | 固定資産評価額の0.4% |
| 実費 | 戸籍謄本、住民票、証明書等の取得費用 | 郵送費など含め数千円〜数万円程度 |
| 司法書士報酬 | 専門家への手数料 | 約10万円〜20万円程度(案件の複雑さによる) |
まとめ
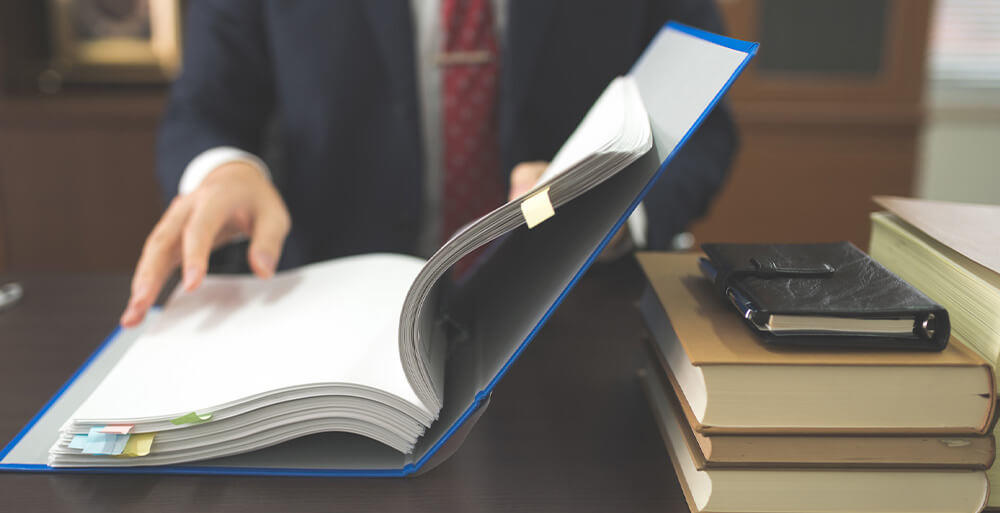
2024年4月1日から相続登記が義務化され、期限内に名義変更を完了させることが必須となりました。
自分で手続きをする場合は費用を抑えられますが、戸籍収集や書類作成に時間と手間がかかり、手続きの不備が期限オーバーにつながるリスクがあります。
期限が迫っている場合や、手続きに不安がある方は、まず相続登記の専門家である司法書士にご相談ください。


お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2026/01/20
代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?