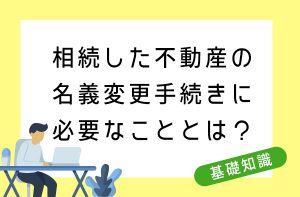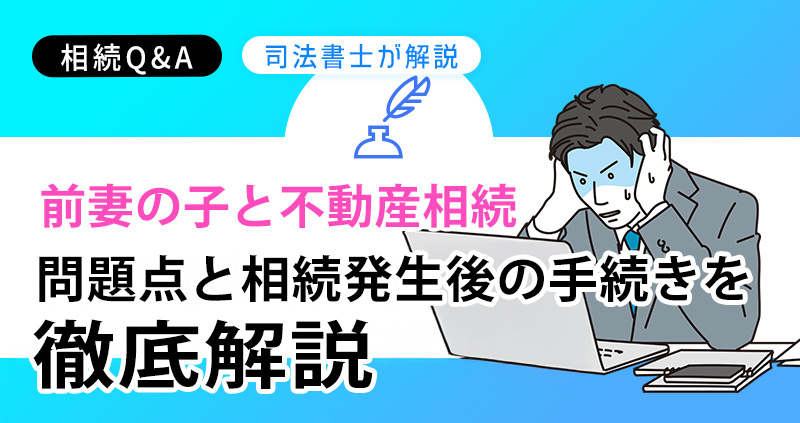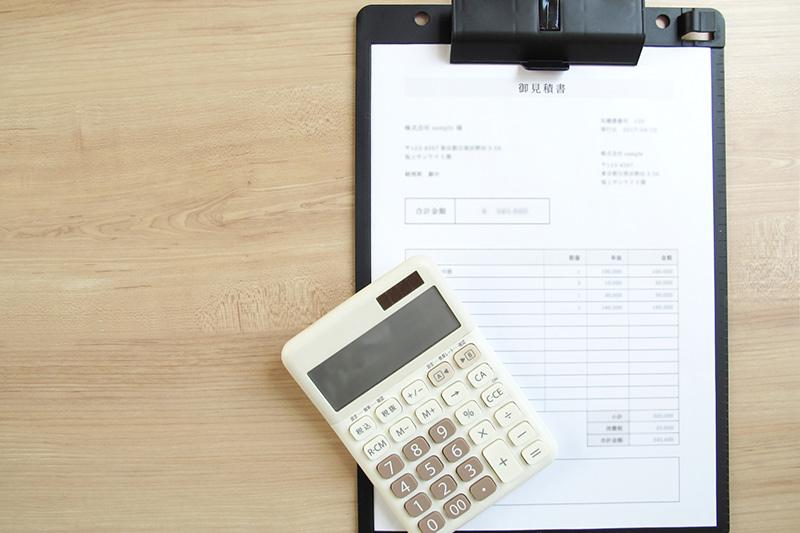死因贈与と仮登記手続きの注意点
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
亡くなったときに特定の相続人などに財産を譲り渡す方法として、遺言以外に、死因贈与という方法があります。
不動産の死因贈与では、仮登記を行うとメリットがあります。ここでは、死因贈与と仮登記について説明しますので、参考にしてください。
目次
死因贈与とは何か?

死因贈与とは
「死因贈与」とは、死亡したときに効力が生じる贈与です。たとえば、土地を死因贈与したい場合には、生きている間に、「私が死んだらこの土地をあなたにあげます」という契約を、土地を譲りたい相手との間で交わします。
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与とよく似たものに、「遺贈」があります。遺贈とは、遺言により財産を譲ることです。
死因贈与は、死亡したときに財産の所有権が相手に移るという点では、遺贈と共通しています。両者の違いは、契約か単独行為かという点です。
死因贈与は契約なので、相手と合意しなければ成立しません。これに対し、遺贈は単独行為なので、自分一人の意思ですることができます。
単独行為である遺贈は、受け取る側の意思を確認せずに行われますので、受け取る側は放棄することができます。一方、死因贈与は最初から当事者双方が合意していますから、受け取る側は簡単に放棄することができません。
死因贈与には遺贈の規定が準用される
死因贈与と遺贈には、上に書いたような違いはありますが、共通している点が多くなります。そのため、死因贈与にはその性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されることになっています(民法554条)。
死因贈与と遺言はどちらが優先する?
相続については、遺言優先と思っている人が多いでしょう。けれど、同じ財産について死因贈与と遺言の両方が残されており、それぞれで内容が違う場合には、基本的には日付の新しい方が優先します。
遺言を書いてもらえば、確実に財産がもらえるというわけではありません。
死因贈与は贈与者が撤回することもできる
争いのあるところですが、死因贈与には、遺贈の撤回の規定(民法1022条)も準用されると考えられています。そのため、死因贈与を行った人(贈与者)は、基本的にはいつでも死因贈与を撤回できると考えられています。
通常、贈与を書面で行った場合には撤回できませんが、死因贈与については例外的に書面で行っていても撤回が可能です。
なお、遺言の撤回は遺言の方式に従って行わなければなりませんが、死因贈与の撤回には特別な方式は必要なく、口頭での撤回もできます。
死因贈与が撤回できないケースとは?
死因贈与は原則的に撤回できますが、例外的に撤回できないケースもあります。それは、負担付死因贈与の場合です。
負担付死因贈与とは、財産を贈与する代わりに、受け取る人(受贈者)に何らかの負担を課す形の贈与です。たとえば、「自分が死んだらこの預金をあげるから、同居して面倒をみてほしい」といった贈与になります。
負担付死因贈与については、受贈者が既に負担を履行した場合には、撤回できません。撤回すれば受贈者に負担だけを強いることになりますから、当然のことと言えるでしょう。
死因贈与の仮登記とは?
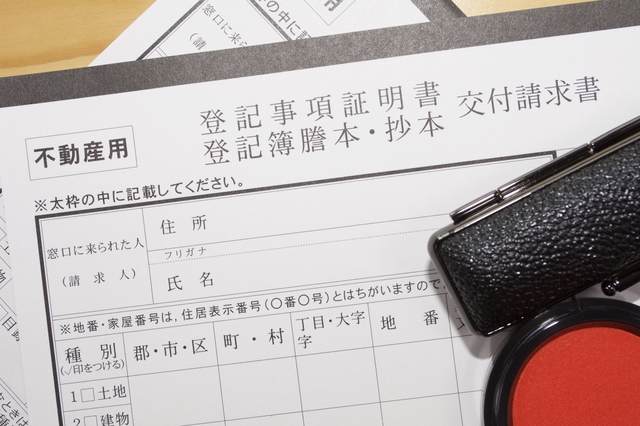
贈与者が財産を二重譲渡する可能性もある
死因贈与は、贈与者が死亡しなければ効力が生じません。そのため、受贈者は財産をもらうことを約束していても、実際に贈与者が亡くなるまでは不安定な立場に置かれてしまいます。
たとえば、贈与者が「自分が死んだら土地をあなたにあげる」と約束したにもかかわらず、生きている間に別の人に土地を譲渡してしまう心配もあるでしょう。
土地を譲渡された人が自分名義で登記すれば、土地はその人のものになってしまう可能性があります。
仮登記をすれば権利を保全できる
不動産の死因贈与については、仮登記を行って権利を保全する方法があります。仮登記をしておけば、将来行われるであろう本登記に備えて、順位を保全することが可能です。
遺贈の場合には、仮登記を行うことはできません。亡くなったときに不動産をもらいたい場合、遺贈ではなく死因贈与の形にし、仮登記をしておくとより確実です。
死因贈与の仮登記の方法
仮登記は、仮登記権利者と仮登記義務者の共同申請で行のが原則になります。死因贈与の仮登記は、受贈者が仮登記権利者、贈与者が仮登記義務者となります。
死因贈与の仮登記は、贈与者の承諾があるときは、受贈者が単独申請することも可能です。この承諾書には、贈与者が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要がありますが、死因贈与契約が公正証書で行われていて、公正証書に贈与者が仮登記申請を承諾している旨の記載がある場合は、贈与者の印鑑証明書の添付は不要となります。
死因贈与の仮登記の必要書類
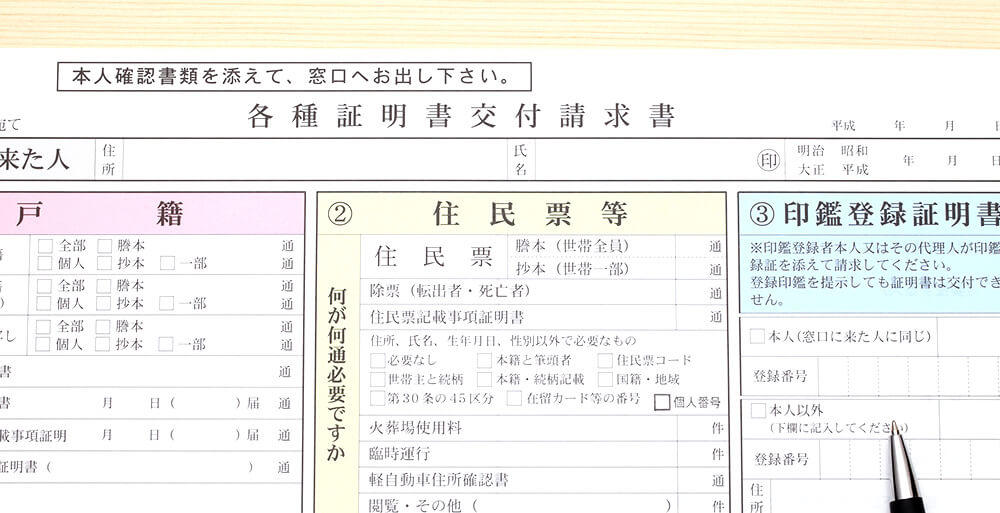
登記原因証明情報
死因贈与契約書(公正証書等)を添付するか、当事者(贈与者及び受贈者)、死因贈与契約を締結した旨、契約日、目的不動産等を記載した報告形式の登記原因証明情報を作成して添付します。
贈与者の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
仮登記義務者である贈与者の印鑑証明書が必要です。
固定資産評価証明書または課税明細
登録免許税の計算のため、不動産の固定資産評価額がわかる書類を添付します。
死因贈与の仮登記の登録免許税
死因贈与の仮登記申請をするときには、不動産の固定資産評価額の1000分の10の登録免許税がかかります。
死因贈与の本登記手続き
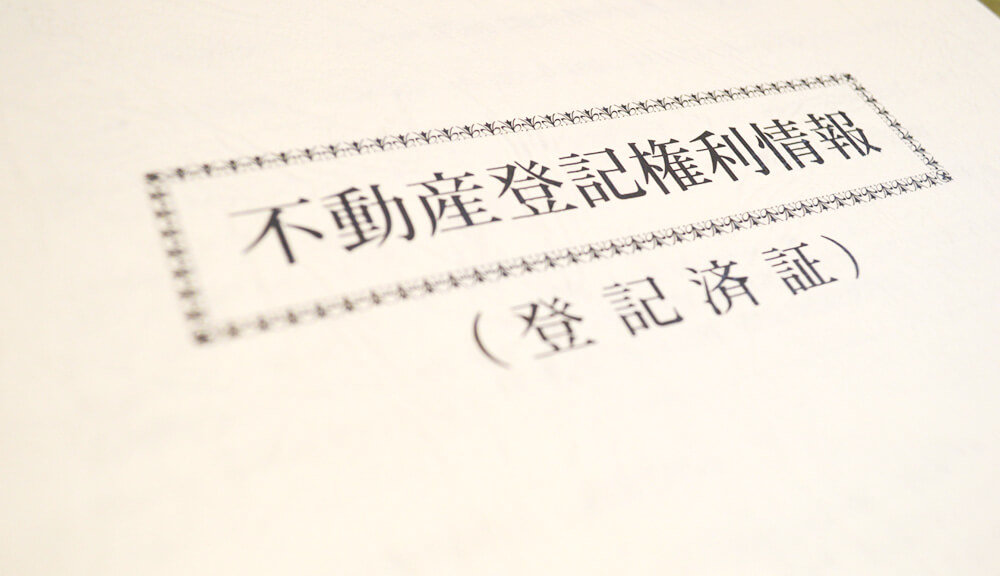
死因贈与の本登記の申請者
死因贈与は、贈与者の死亡により効力を生じます。そのため、死因贈与の仮登記の本登記は、贈与者の死亡後に申請します。
死因贈与の本登記手続きは、登記権利者である受贈者と、登記義務者である贈与者の相続人全員の共同申請になるのが原則です。ただし、死因贈与契約の執行者が指定されている場合には、執行者が登記義務者になります。
死因贈与の本登記の必要書類
死因贈与の本登記では、次のような書類が必要になります。
登記原因証明情報
死因贈与契約書(または報告形式の書面)と、仮登記義務者死亡の記載のある戸籍謄本の両方が登記原因証明情報となります。
なお、死因贈与契約書が公正証書でない場合には、贈与者の印鑑証明書、相続人全員の承諾証明情報(印鑑証明書添付)、相続人が誰であるかがわかる戸籍謄本が必要です。
登記識別情報または登記済証
登記識別情報が発行されていれば登記識別情報通知を、登記識別情報が発行されていない場合には登記済証を添付します。
相続証明情報
執行者が指定されていない場合には、相続人が誰であるかがわかる戸籍謄本を添付します。
執行者または相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)
執行者が指定されている場合には執行者の印鑑証明書、執行者が指定されていない場合には相続人全員の印鑑証明書を添付します。
執行者の権限を証する書面
執行者が指定されている場合には、それを証明する書面(公正証書など)を添付します。
受贈者の住所証明書
受贈者の住民票または戸籍附票が必要です。
固定資産評価証明書または課税明細の写し
登録免許税の計算のため添付します。
その他の必要書類
仮登記権利者が住所変更している場合や仮登記権利者死亡の場合などは、さらに手続きが複雑になり、他にも必要書類が発生します。
死因贈与の登記の登録免許税
死因贈与の登記を行うときには、不動産の固定資産評価額の1000分の20の登録免許税がかかります。
まとめ
死因贈与は当事者間の契約なので、死亡時に財産をもらう場合、遺言よりも確実性があります。不動産の死因贈与では、仮登記をしておくことで、権利を保全することも可能です。
死因贈与するときには、公正証書を作成しておくのがおすすめです。当事務所では、死因贈与の公正証書作成や仮登記の手続きを代行いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?