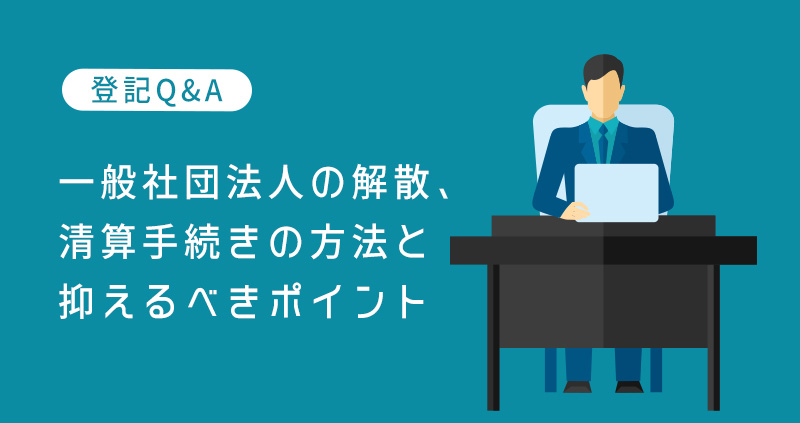一人社長が死亡した後の会社清算・廃業と相続手続き【司法書士監修】完全ガイド
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。


本記事では、相続専門の司法書士が、必要な手続きの流れ、書類、注意点を徹底解説します。
複雑な手続きをスムーズに進めるための完全ガイドです。
会社の行く末は相続人が決める: 相続人が株式を相続し、会社を続けるか畳むかを判断する。
廃業は解散→清算の手順で進める: まず株主総会で解散を決め清算人が財産を整理。債務超過の場合は破産も検討する。
社長が保有していた株式や不動産は相続の対象: 遺言書がなければ、遺産分割協議で誰が何を受け継ぐかを決める。
中小企業の中には、従業員を雇わず、社長一人で運営されている会社も少なくありません。しかしながら、その一人社長が突然死亡した場合、親族は会社の経営状況について詳しく分からず、会社をたたむという選択肢を考えることも多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、一人社長が不慮の事態で亡くなられた場合を想定し、相続の手続きと、会社を廃業する際の流れについて詳しく解説いたします。

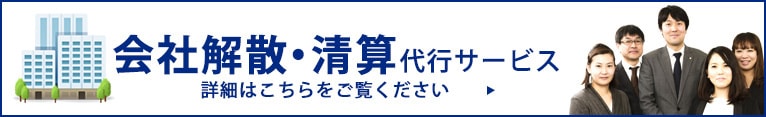
目次
一人社長が死亡した場合、会社はどうなるのか?


したがって、たとえ社長が死亡しても、会社そのものは存続し続けることになります。
相続人が会社の存続または廃業を決定する必要がある
一人社長が亡くなった後、会社を存続させるか、それとも廃業するかの判断は、原則として相続人が行わなければなりません。
一人社長の会社では、社長自身が代表取締役であり、かつ株主として会社の意思決定を行っていたはずです。そのため、その立場を引き継いだ相続人が、会社の今後の方向性を決める必要が出てきます。
社長が保有していた株式は相続人に承継される
一人社長の会社では、社長が会社の株式の全部または大部分を保有しているケースが一般的です。この場合、社長が保有していた株式は、社長個人の財産として扱われるため、相続の対象となります。そして、誰がその株式を相続するかは、遺言書の有無によって手続きが異なります。
ア.遺言書がある場合
相続が発生した際、遺言書が存在すれば、原則として遺言書の内容が優先されます。もし社長が株式などの財産について遺言書を残していれば、遺言書で指定された方が株式を相続することになります。
イ.遺言書がない場合
遺言書がない場合には、民法に定められた相続人(法定相続人)全員が、社長の財産を相続する権利を持つことになります。したがって、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が株式を承継するかを決定する必要があります。
代表取締役の地位は相続されない
社長が死亡した場合、代表取締役という地位は相続の対象にはなりません。つまり、相続人が当然に代表取締役になるわけではありません。なぜなら、会社と取締役の関係は法律上「委任契約」とされており、取締役の死亡によってその委任契約は終了すると解釈されるためです。そのため、一人社長が死亡すると、会社には取締役が誰もいない状態になってしまいます。
この場合、会社を存続させるためには、株主総会を開催し、新たな取締役を選任する必要があります。ただし、会社を廃業する場合には、新たな取締役を選任する必要はなく、会社を解散すると同時に清算人を選任し、会社の清算手続きに入ります。
以下では、一人社長が死亡した場合に、どのような流れで会社を廃業すればよいのかを詳しく解説していきます。
まずは株式の相続手続きを行う

一人社長が死亡すると、会社の代表者が不在となり、会社の意思決定を行うことができなくなってしまいます。特に、社長が全株式を保有していた場合には、株主も不在の状態となり、株主総会を開くことすらできません。
会社の重要な決定を行うためには、株主総会の決議が不可欠です。したがって、まずは株式の相続手続きを完了させ、新たな株主を明確にする必要があります。
遺言書がある場合は、遺言書で指定された方が株式を相続し、株主となります。一方、遺言書がない場合には、以下の手順で株式の相続手続きを進めることになります。
1.相続人の確定
相続人となるのは、「配偶者」と「血族の一部の方々」です。血族については、①子供、②直系尊属(父母や祖父母)、③兄弟姉妹の順に優先順位が定められています。社長の死亡時の戸籍謄本から過去の戸籍謄本を遡り、相続人を確定する作業を行います。
【血族の順位】
- 子供
- 直系尊属(父母や祖父母)
- 兄弟姉妹
2.遺産分割協議
相続人が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が株式を相続するかを決定します。遺産分割協議がまとまったら、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
3.株式の名義変更
株式を相続する人が決定したら、会社の株主名簿にその氏名や住所を記載する名義変更の手続きを行います。非上場会社の場合、会社自身が株主名簿を管理しているため、遺産分割協議書などの必要書類を会社に提出し、株主名簿を書き換えてもらいます。
株式相続後は会社廃業手続きを行う


会社を廃業するためには、まず会社を解散させ、その後、清算手続きを行う必要があります。
その大まかな流れは以下の通りです。
株主総会で会社の解散決議をする
会社の解散とは、会社の事業活動を停止することを意味します。会社を解散するには、株主総会の特別決議を経る必要があります。株式を相続した新たな株主で株主総会を開催し、会社の解散を決議します。
また、会社解散後は清算手続きに入るため、解散決議と同時に清算人の選任も行います。清算人とは、会社の財産を整理し、債務を弁済するなど、会社の清算業務を行う人のことです。清算人になるための特別な資格は必要ないため、親族や会社の関係者などが就任しても差し支えありません。
会社解散・清算人選任の登記をする
会社の解散と清算人の選任が決議されたら、その決定から2週間以内に、法務局で解散・清算人選任の登記を行う必要があります。登記申請の際には、株主総会議事録や会社の定款、清算人の就任承諾書などの書類を提出します。
解散の届出をする
法務局での解散登記が完了したら、税務関係の各種届出を行います。具体的には、管轄の税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に解散届を提出します。
財産目録・貸借対照表の作成
清算人は、会社の解散時の財産状況を明らかにするため、財産目録と貸借対照表を作成し、株主総会の承認を受ける必要があります。
解散公告・催告
会社の債権者に対して、債権の申し出をするよう促すために、官報に「解散公告」を掲載します。さらに、会社が把握している特定の債権者に対しては、個別に債権の申し出を促す「催告」を行います。
解散確定申告
会社の解散日から2ヶ月以内に、解散事業年度(事業年度開始日から解散日まで)の確定申告を行います。
残余財産確定・分配
清算人は、会社の売掛金や貸付金などの債権を回収し、買掛金や借入金などの債務を支払います。その結果、会社に残った財産(残余財産)があれば、株主に対し、その持ち株数に応じて分配します。
清算確定申告
残余財産が確定した後、原則として1ヶ月以内に清算確定申告を行います。
決算報告書の作成・承認
清算事務がすべて終了した後、清算人はその結果をまとめた決算報告書を作成し、株主総会に提出して承認を得ます。
清算結了の登記をする
株主総会で決算報告書が承認されたら、その承認日から2週間以内に法務局で清算結了の登記を行います。この登記をもって、会社が法的に消滅したことが公示されます。登記の際には、株主総会議事録などの書類が必要になります。
清算結了の届出
法務局での清算結了登記が完了したら、最後に税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に清算結了届を提出します。

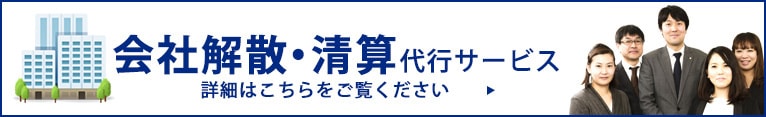
会社が債務超過の場合には注意が必要


このような場合、通常の解散・清算手続きとは異なる対応が必要になります。
一人社長を相続すると借金を引き継いでしまうことも
会社に負債がある場合、通常は社長がその連帯保証人になっていることが多く見られます。その場合に、相続人が単純承認という形で社長の相続手続きを行うと、その連帯保証債務も引き継ぎ、借金を支払う義務を負うことになります。
もし債務を引き継ぎたくない場合には、「相続放棄」を検討する必要があります。 相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所で申述する必要があります。
ただし、相続放棄をした場合、借金などのマイナスの財産を承継することはなくなりますが、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切相続できなくなります。特に、社長が自宅不動産などの個人資産を持っていた場合には、それらも相続できなくなるため、相続放棄の判断は慎重に行うべきでしょう。
なお、相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。そのため、次順位の親族がいる場合には、その親族が新たに相続人となります。次順位の親族が何も知らずに債務を引き継いでしまうことのないよう、相続放棄に至った経緯を連絡しておくことも大切です。
会社は倒産の手続きが必要となる
会社に多額の負債があり、債務超過の状態にある場合には、通常の解散・清算結了の手続きを行うことはできません。この場合、新たな代表取締役を選任し、裁判所に申し立てて「破産」や「特別清算」といった倒産手続きを行う必要があります。
なお、相続人が相続放棄をした場合、会社の株式を相続することもないため、会社を動かすことができなくなってしまいます。
このように、相続放棄は債務を免れる有効な手段となり得る一方で、債務超過の会社を放置することにも繋がりかねません。いずれにしても、一人社長が死亡した後の会社や相続の手続きは複雑なため、早めに専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
具体的な事例・ケーススタディ

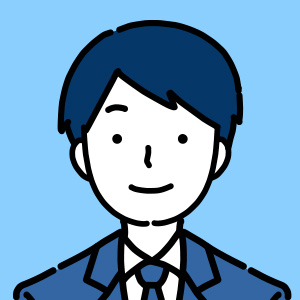
- 円満な相続とスムーズな廃業
- 相続・廃業
故人: 田中一郎さん(70歳)、従業員なし、長年一人で営んできた機械部品製造業の株式会社を所有。
家族構成: 妻・花子さん(68歳)、長男・健太さん(40歳・会社員)、長女・美咲さん(35歳・パート)。
状況: 一郎さんが急病で逝去。会社には目立った資産・負債はなく、後継者もいない。妻の花子さんは高齢であり、会社経営の知識もないため、廃業を希望。一郎さんは遺言書を残していなかった。
1. 相続人の確定
花子さん、健太さん、美咲さんが法定相続人として確定した。
2. 遺産分割協議
花子さん、健太さん、美咲さんの間で遺産分割協議が行われた結果、一郎さんが保有していた会社の全株式を妻の花子さんが相続することで全員が合意した。他の相続財産についても円満に分割協議が成立し、遺産分割協議書が作成された。
3. 株式の相続(名義変更)
遺産分割協議書に基づき、一郎さんが保有していた会社の全株式が花子さんの名義に変更された。
4. 株主総会での解散決議
花子さんが唯一の株主として株主総会を開催し、会社の解散を決議。同時に、花子さんが清算人に選任された。
5. 解散・清算人選任登記
法務局に解散と清算人選任の登記を申請。
6. 解散公告
官報に解散公告を掲載した。既知の債権者は存在しなかったため個別催告はしていない。特に債権者から異議の申し出はなかった。
7. 残余財産の確定・分配
会社の財産を整理した結果、わずかな現預金が残ったため、花子さんに分配された。
8. 清算結了登記
法務局に清算結了の登記を申請し、会社は消滅した。
遺言書がなかったものの、相続人間で会社の株式の承継について円満な遺産分割協議が成立したため、その後の廃業手続きもスムーズに進んだ。会社に複雑な債権債務関係がなかったことも、清算手続きを容易にした要因である。遺産分割協議がまとまらない場合、手続きが長期化する可能性があることに注意が必要である。
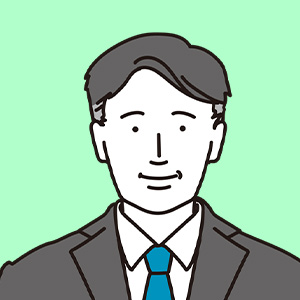
- 債務超過の会社破産と個人資産の相続
- 相続・廃業
故人: 井上誠さん(68歳)、従業員2名の小規模なイベント企画会社を所有。近年、業績が悪化し、多額の借入金を抱える債務超過の状態だった。誠さん個人名義で自宅と賃貸用マンションを所有。
家族構成: 妻・美紀さん(65歳)、長男・大輔さん(40歳・会社員)。
状況: 誠さんが病気で逝去。会社の立て直しは困難と判断し、美紀さんと大輔さんは会社の破産手続きを進めることを検討。幸い、誠さんは会社の借入金に対して個人保証をしていなかった。誠さんは遺言書を残しており、会社の全株式と自宅は美紀さんに、賃貸用マンションは大輔さんに相続させる旨が記載されていた。
1. 相続の開始と債務の確認
美紀さんと大輔さんは、会社の債務状況を確認。個人保証がないことを確認し、相続放棄はせずに、会社の破産手続きを進める方針を決定。
2. 遺言書の確認と執行
美紀さんと大輔さんが遺言書を発見し、家庭裁判所で検認手続きを行った。
3. 株式の相続
遺言に基づき、誠さんが保有していた会社の全株式は美紀さんが相続した。
4. 不動産の相続
同じく遺言に基づき、誠さん個人名義の自宅は美紀さんに、賃貸用マンションは大輔さんにそれぞれ相続され、相続登記も完了した。
5. 株主総会の開催
会社の破産申し立てを行うためには、会社の代表者がいる必要があったため、相続により唯一の株主となった美紀さんが株主総会を開催し、自身を代表取締役に選任した。
6. 会社の破産申し立て
代表取締役となった美紀さんが、弁護士に依頼し、裁判所に会社の破産申し立てを行った。
7. 破産手続きの開始と破産管財人の選任
裁判所が破産手続きの開始を決定し、破産管財人が選任された。破産管財人は会社の財産(もしわずかに残っていれば)を換価し、債権者への配当手続きを進める。代表取締役である美紀さんは、破産管財人の指示に従い、必要な情報提供や手続きに協力する。
8. 相続税の申告・納税
美紀さんと大輔さんは、相続した自宅と賃貸用マンションに対して相続税の評価を行い、申告・納税を行った。
•会社は債務超過で破産したが、社長個人が借入金の個人保証をしていなかったため、相続人は会社の債務を個人的に引き継ぐ必要がなかった。
•相続人の一人である美紀さんが、会社の破産手続きを進めるために、一時的に代表取締役に就任した。
•社長個人のプラスの財産(自宅と賃貸用マンション)は、遺言に基づき、それぞれ相続人に承継された。
•会社の破産手続きと、個人の相続手続きは並行して進められる。
•債務超過の会社の存在は、相続財産の評価や相続税の計算に影響を与える可能性があるため、専門家への相談が重要となる。
まとめ

一人社長が死亡しても、会社は自動的に消滅するわけではありません。会社を廃業するには、法律に定められた手順に従って手続きを進める必要があります。まずは株式の相続手続きを行い、その後、会社の解散・清算の手続きを行うことになります。
当事務所では、会社の解散・清算手続きに関するご相談やサポートを承っております。経営者の方が亡くなられ、会社をどのようにすればよいかお困りのご親族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

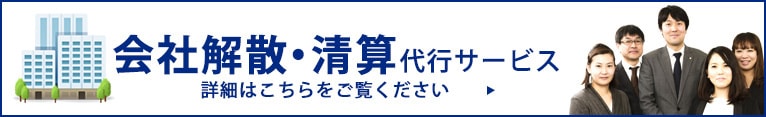
お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2026/01/20
代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?