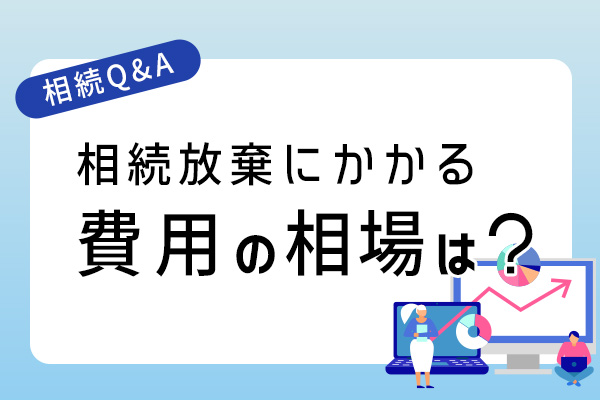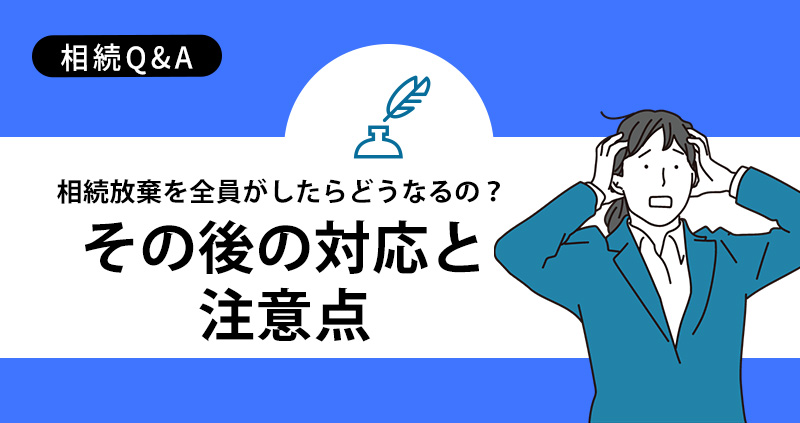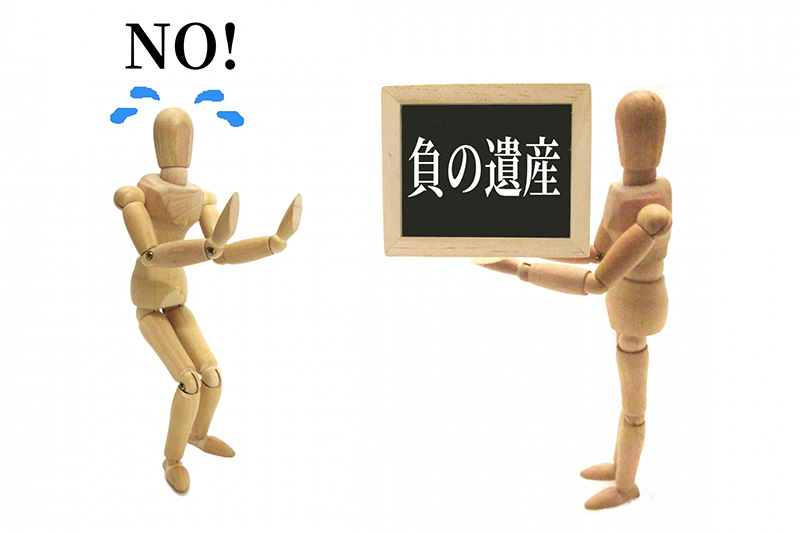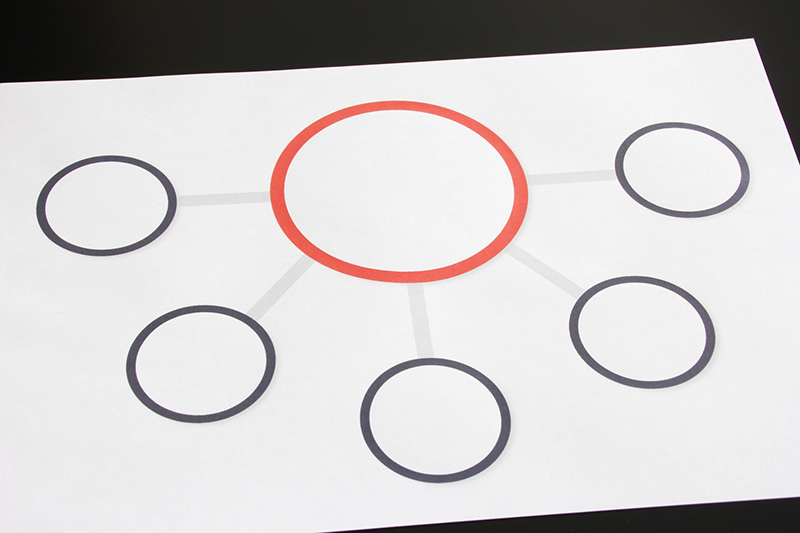単純承認とは?法定単純承認の注意点と相続放棄ができなくなる行為を司法書士が解説
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

単純承認のリスク: 特別な手続きをしなければ、借金も含め全て相続(単純承認)することになります。
期限の重要性: 相続放棄や限定承認は、原則として3ヶ月以内にしなければなりません。
最大のNG行為: 財産を勝手に処分・売却すると、法定単純承認とみなされ、相続放棄できなくなります。
例外的な許容される行為: 葬儀費用の支払いや通常の形見分けは、単純承認にはあたりません。


目次
単純承認の基本:3つの相続方法と選択期間


| 相続方法 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| ⑴ 単純承認 | プラス・マイナス全ての財産を引き継ぐ | 不要(何もしなければこれになる) |
| ⑵ 限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ | 家庭裁判所への申述が必要 |
| ⑶ 相続放棄 | ラス・マイナス全ての財産を一切引き継がない | 家庭裁判所への申述が必要 |
相続方法の選択期間(熟慮期間と伸長)
相続人は、相続が開始したことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に、上記3つのどの方法で相続するかを決めなければなりません。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。
期日・期限の重要ポイント
財産調査に時間がかかるなどの事情がある場合、この熟慮期間は家庭裁判所に申立てることで延長が可能です。延長の申立ては、熟慮期間が満了する前(原則として3ヶ月以内)に手続きする必要があります。この期間内に判断できない場合は、必ず家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間伸長」の申立てを行いましょう。
単純承認のメリット・デメリットと手続き
単純承認のメリット:手続きの簡便さと時間の節約
単純承認の最大のメリットは、手間や費用がかからないことです。
- 特別な手続きが不要:限定承認や相続放棄のように、家庭裁判所へ申述したり、複雑な書類を作成したりする必要が一切ありません。
- 迅速な財産承継:手続きが不要なため、すぐに遺産分割協議を進めたり、預貯金を引き出したりして、相続財産を自由に利用できます。
相続財産がプラス(資産)を明確に上回っており、相続人間に争いがない場合には、この簡便さが大きな利点となります。
単純承認のデメリット:借金(負債)の全てを承継するリスク
一方、単純承認のデメリットは、マイナスの財産(借金)も全て引き継ぐ義務が生じることです。
- 負債の承継:被相続人に借金があった場合、単純承認をすると、相続人はその借金を全額返済する義務を負います。
- 財産調査の省略によるリスク:手続きが不要だからといって財産調査を怠ると、後になって高額な負債が発覚しても、相続放棄できなくなる場合があります。
このリスクを避けるため、単純承認を選択する前には、必ず被相続人の財産状況(プラス・マイナス双方)を正確に把握することが極めて重要です。
要注意!相続放棄できなくなる「法定単純承認」

上記のように何もしなかった場合の単純承認とは別に、相続人がとった特定の行動により、本人の意思とは関係なく単純承認をしたとみなされる制度があります。これを「法定単純承認」と呼びます。
法定単純承認が成立すると、それ以降は限定承認や相続放棄の手続きをすることが一切できなくなります。
民法921条により、相続人が以下の行為を行った場合に法定単純承認が成立します。
相続財産の全部または一部を処分したとき
相続財産を売却したり、誰かに譲ったり、自分のものとして使い込んだりする行為は、「その財産を相続する意思がある」とみなされます。
ただし、財産の現状を維持するための保存行為(例:建物の小規模な修繕)は処分にあたりません。
熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき
前述のとおり、熟慮期間が経過すると、自動的に単純承認したことになります。
限定承認・相続放棄後であっても、相続財産を隠匿、私的に消費、悪意で財産目録に記載しなかったとき
相続放棄後も、残された財産を適切に管理し引き継ぐ義務があります。これに背き、意図的に財産を隠したり、自分のものとして消費したりする背信的な行為があった場合、相続放棄は認められなくなります。


法定単純承認の具体的な判断基準

法定単純承認にあたる可能性が高い行為(相続放棄ができなくなる行為)
相続人が以下のような行為をした場合、「相続財産を処分した」として法定単純承認とみなされる可能性が高く、相続放棄ができなくなるため、特に注意が必要です。
| 行為の例 | 理由等 |
|---|---|
| 遺産の譲渡 | 被相続人名義の不動産や車などを売却等して他人に譲渡すること。 |
| 物の取り壊し | 被相続人名義の建物を取り壊した場合にも、処分となってしまします。 |
| 遺産分割協議に参加する | 財産を相続する意思があるからこそ行う行為であるため。 |
| 被相続人の預金から借金を返済する | 相続財産(預金)を処分した行為とみなされる可能性が高い。 |
| 被相続人の債権の取り立て | 被相続人の権利を相続したからこそ、借金を取り立てることができるため。 |
| 高価な財産の持ち帰り(形見分けを超えるもの) | 経済的価値の高い宝石や貴金属などを取得した場合。 |
法定単純承認にあたる可能性が低い行為(相続放棄しても問題ない行為)
以下の行為は、法定単純承認には該当しないとされることが多く、相続放棄をしても問題ないと判断される可能性が高いものです。
| 行為の例 | 理由等 |
|---|---|
| 葬儀費用の支払い、墓石・仏壇の購入 | 【重要】社会儀礼として当然に発生する費用であり、相続財産の範囲内で支払ったとしても、単純承認とみなされないという判例や実務が多い。 |
| 被相続人の債務を自分の財産で支払う | 相続人自身の固有の財産から支払った場合は、相続財産を処分したことにはあたらない(判例あり)。 |
| 建物の修繕(現状維持のためのもの) | 保存行為にあたり、処分行為とはみなされない。 |
| 生命保険金の受け取り | 生命保険金は受取人固有の財産となります。相続人が受取人となっている生命保険の死亡保険金を受け取っても単純承認にはなりません。(※) |
| 通常の形見分け | 経済的価値がそれほど高くないものを分ける行為。 |
(※)死亡保険金の受取人が被相続人になっている場合には、相続財産となるので、受け取ると単純承認になります。
相続放棄しても受け取れるもの
相続放棄をしても、被相続人の死亡を原因として発生する財産の中には、相続財産に含まれず、相続人が固有の権利として受け取れるものがあります。これらを受け取っても、単純承認とはみなされません。
相続人が受取人に指定されている生命保険金(死亡保険金)は、民法上の相続財産には含まれず、受取人固有の財産をなります。相続放棄をしても、自分が受取人に指定されている生命保険金を受け取れます。
被相続人の勤務先から支払われる死亡退職金も、生命保険金と同様、受取人である遺族固有の財産になります。相続放棄をしても、死亡退職金は受け取れます。
被相続人によって生計を維持されていた遺族が受け取れる遺族年金は、相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取れます。
年金受給者が亡くなった場合、亡くなった月までの年金を受け取れます。被相続人がまだ受け取っていない年金がある場合、法律で定められた遺族は相続放棄をしていても未受給年金を受け取れます。
被相続人が加入していた健康保険から支払われる葬祭費や埋葬料は、遺族に対して支払われるものなので、相続財産ではありません。相続放棄をしていても、受け取ることができます。
葬儀に参列した人から受け取る香典は喪主に対して払うものですから、相続放棄するかどうかに関係なく受け取れます。
【新法対応】遺贈の放棄に関するルール
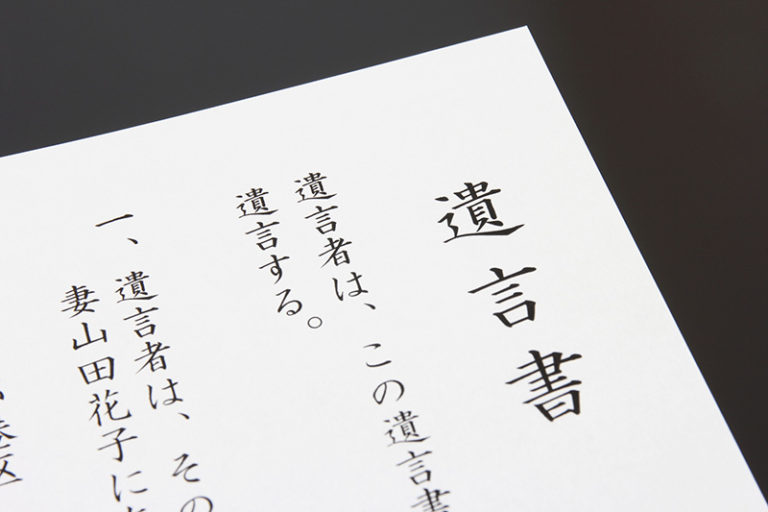
単純承認、限定承認、相続放棄を選択しなければならないのは相続人だけではありません。遺言によって財産を受け取った人(受遺者)も、受け取りを放棄するかどうかを選択する必要があります。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、それぞれ放棄の手続きが異なります。
包括受遺者と特定受遺者の手続きの違い
| 遺贈の種類 | 内容 | 借金(債務)の承継 | 放棄の手続き |
|---|---|---|---|
| 包括遺贈 | 遺産の全部またはその一定割合を譲る | 承継する(相続人と同一の権利義務) | 遺贈を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での相続放棄が必要 |
| 特定遺贈 | 特定の財産(不動産、預金など)を譲る | 原則承継しない | 期間の制限なく、相続人や遺言執行者への意思表示で足りる |
特定遺贈の放棄は柔軟
特定遺贈の放棄は、包括遺贈や相続放棄と異なり、家庭裁判所での手続きは必要ありません。受遺者は、指定された財産を受け取らない意思を相続人などに示せばよく、柔軟に選択できます。
まとめ
相続放棄を検討しているにもかかわらず、故人の遺産にうっかり手を付けてしまうと、「法定単純承認」とみなされ、借金まで引き継がざるを得なくなる可能性があります。
- 相続する意思がない場合は、熟慮期間(原則3ヶ月)内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うこと。
- 期間内に判断できない場合は、熟慮期間満了前に家庭裁判所へ期間伸長の申立てを行うこと。
- 財産の処分行為(売却、換価、自分の借金返済への充当など)は、絶対に避けること。
相続手続きは専門的な知識が必要になることが多いため、不安な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家への相談を強く推奨します。


お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2026/01/20
代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?