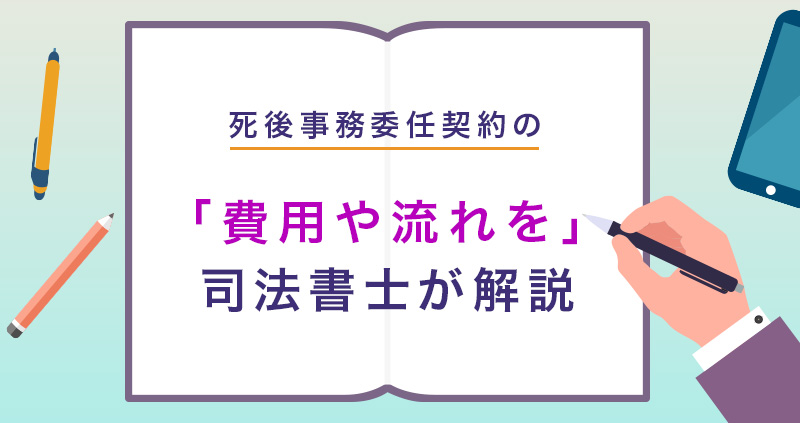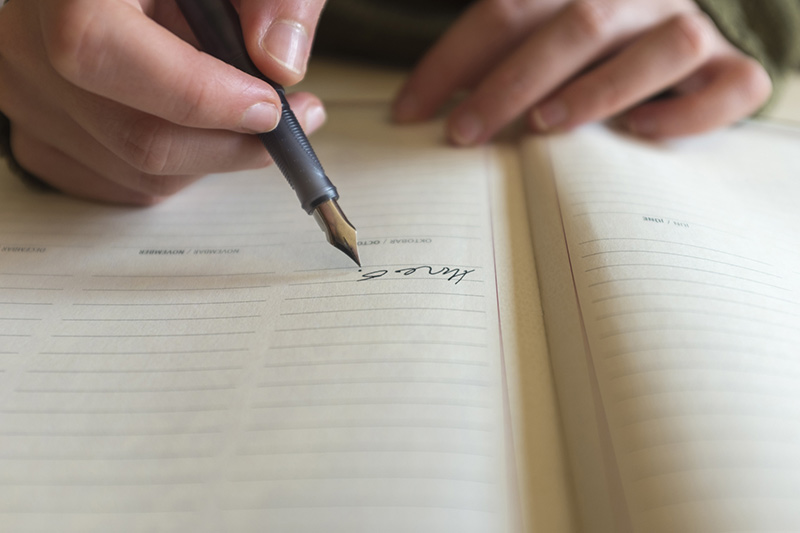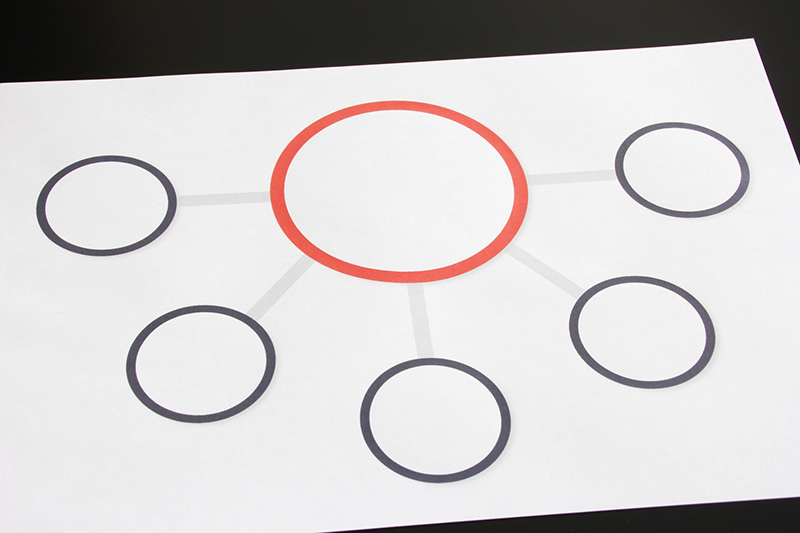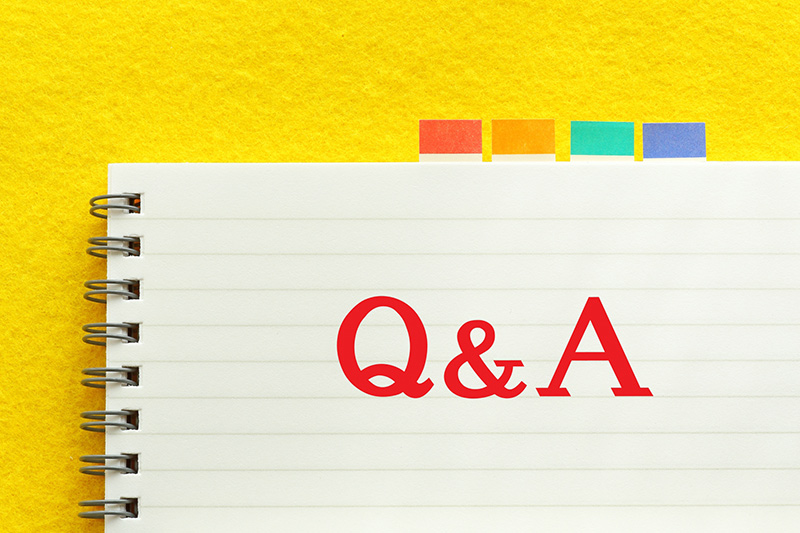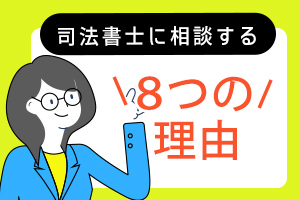遺言書作成前に知っておきたい「遺贈」と「相続」の違い
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
「遺贈」と「相続」は、どちらも亡くなった人の財産を引き継ぐことになる点では同じですが、基本的な意味が違います。遺言書を作成するときにも、「遺贈する」と書くか「相続させる」と書くかで大きな違いが出てくることがあります。「遺贈」と「相続」の違いについて知っておきましょう。
目次
「遺贈」と「相続」の基本的な違いは?
「相続」と「遺言」は意味が違う
相続とは、人が亡くなったときに、その人(被相続人)が持っていた財産をはじめとする権利や義務を、一定の身分関係の人(相続人)が引き継ぐことです。一方、遺贈とは、遺言によって、財産の全部又は一部を無償で贈与することを言います。相続が当然に発生するものであるのに対し、遺贈は遺言書を作成しなければできないものになります。
財産を引き継ぐのは相続人か?相続人以外か?
相続では、被相続人の財産を引き継ぐのは、相続人のみになります。一方、遺贈では、贈与する相手(受遺者)は、相続人であっても相続人以外であってもかまいません。
欠格や廃除に違いはある?
推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき人)が、被相続人に対して著しい非行を行った場合(被相続人を殺害しようとした、被相続人の遺言を偽造・変造・隠匿したなどの場合)には、「欠格」事由に該当するとされ、相続人の資格がなくなります(民法891条)。また、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた場合には、被相続人は生前にまたは遺言によって、家庭裁判所にその相続人の「廃除」を請求し、相続権を剥奪することができます。
受遺者には相続人の欠格事由の規定が準用されており(965条)、891条の欠格事由に該当する人は、遺贈は受けられません。一方、廃除された相続人であっても、遺贈を受けることは可能となっています。
遺言での「遺贈」と「相続」の使い分け
相続人以外に「相続させる」はNG
遺言で財産を贈与する場合に、「遺贈する」と書く方法と、「相続させる」と書く方法があります。財産を引き継がせたい相手が相続人の場合には、「遺贈する」と書いても「相続させる」と書いてもOKです。一方、財産を引き継がせたい相手が相続人以外の場合には、「相続させる」と書くのは本来間違いということになります。
なお、遺言の内容が不明確である場合には、遺言者の意思を尊重して可能な限り有効となるよう解釈するというのが判例の立場ですから、相続人以外に「相続させる」と書いても、実際には遺贈と読み替えられるのが通常です。ですが、これから遺言を書く場合には、できるだけ正確な表現をするよう心がけた方が良いでしょう。
「遺贈する」のと「相続させる」のとでは違いがある
上述のとおり、遺言で相続人に財産を贈与する場合には、「遺贈する」ことも「相続させる」こともできます。ここで、「遺贈する」と書くのと「相続させる」と書くのとでは、違いが出てきます。それぞれの違いについて、以下に説明していきます。
「相続させる」旨の遺言とは?
「相続させる」旨の遺言の効果
「相続させる」旨の遺言の解釈については、説が分かれています。現在の判例・通説では、特定または全部の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があった場合には、原則として、遺産分割の方法を指定(民法第908条)したものと扱われています。
この場合、相続開始と同時にその遺産は遺産分割されたことになり、当然に所有権が移転しますから、被相続人の死後に遺産分割協議を行う必要がありません。
「相続させる」旨の遺言のメリット
「相続させる」遺産が不動産である場合、上述のとおり被相続人の死亡と同時に指定された相続人に不動産の所有権が移転することになり、その相続人が単独で所有権移転登記(相続登記)を行うことができます。遺言執行者がいる場合にも、遺言執行者の協力は不要です。
また、相続登記を行う前に他の相続人が不動産を第三者に譲渡して所有権移転登記を行った場合、その第三者は無権利者から不動産を譲り受けたことになるため、遺言で指定された相続人は登記の抹消を請求できます。
このほかに、農地の所有権移転の際には原則として農地法の許可が必要ですが、農地を「相続させる」とした場合には、許可が不要になるというメリットもあります。
割合を指定して「相続させる」場合
たとえば、「長男に遺産の2分の1を相続させる」というふうに、遺産のうちの一定割合を相続させる旨の遺言を書いた場合には、どの財産が長男に帰属するのかが不明です。この場合には、「相続させる」旨の遺言は相続分の指定(民法第902条)とされ、別途遺産分割協議が必要になります。
「遺贈する」旨の遺言とは?
遺贈の種類
遺贈には、大きく分けて包括遺贈と特定遺贈の2つがあります。また、負担付遺贈というような、条件付きの遺贈も可能となっています。
<包括遺贈>
相続財産全体に対する割合を指定して遺贈する方法です。たとえば、「遺産の3割をAに遺贈する」のように書くのが包括遺贈です。
<特定遺贈>
個別の財産を特定して遺贈する方法です。たとえば、「○○市○○町○丁目○番○号の土地をBに遺贈する」のように書くのが特定遺贈です。
<負担付遺贈>
たとえば、「土地・建物を遺贈するので、妻が生存中は同居して扶養してほしい」というように、一定の義務の負担を条件に遺贈を行うことです。
「遺贈する」旨の遺言の効果
遺贈の場合にも、遺贈の効力は遺言者が死亡したときに発生します。ただし、不動産の遺贈の効果を第三者に対して主張するためには、所有権移転登記を行って対抗要件を備えておかなければならないとされています。
「遺贈する」旨の遺言がある場合には、遺言者の遺贈義務を相続人全員が引き継ぐことになります。登記手続きの際にも、受遺者が登記権利者となり、相続人全員(または遺言執行者)が登記義務者となって、共同申請する必要があります。なお、この場合の登記原因については「遺贈」となるのが原則ですが、相続人への移転登記である限り、登録免許税は相続と同じく固定資産税評価額の1000分の4の税率となります。
なお、農地については、包括遺贈の場合には農地法の許可は不要ですが、特定遺贈の場合には許可が必要とされています。
受遺者や相続人が遺言者より先に死亡したら?
民法994条では、「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」とされており、受遺者が先に死亡していれば、遺言そのものが無効になります。
一方、相続には代襲相続という制度があり、相続する予定だった人が被相続人より先に亡くなった場合でも、その子が相続できる場合があります。「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解釈するのが通説ですから、代襲相続が起こり得ると考えられます。
判例では、「相続させる」旨の遺言も、遺言者が代襲相続させる意思を持っていたとみるべき特段の事情がなければ効力は生じないという立場をとっています。これは言いかえると、特段の事情があるときには代襲相続が認められるということにもなります。
「相続させる」旨の遺言を書くときにも、「遺言者は○○を長男Aに相続させる。遺言者より前にまたは遺言者と同時に長男Aが死亡していた場合、遺言者は前記○○を遺言者の孫Bに相続させる」など、代襲相続させるのかどうかを明確に記載しておいた方が良いでしょう。
遺言書では、「遺贈」や「相続」という言葉の使い方1つとっても、効果が変わってくることがあります。遺言書を書くときには、専門家に相談し、できるだけメリットになる書き方をされることをおすすめします。当事務所でも遺言書のご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2026/01/20
代表速水が『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?