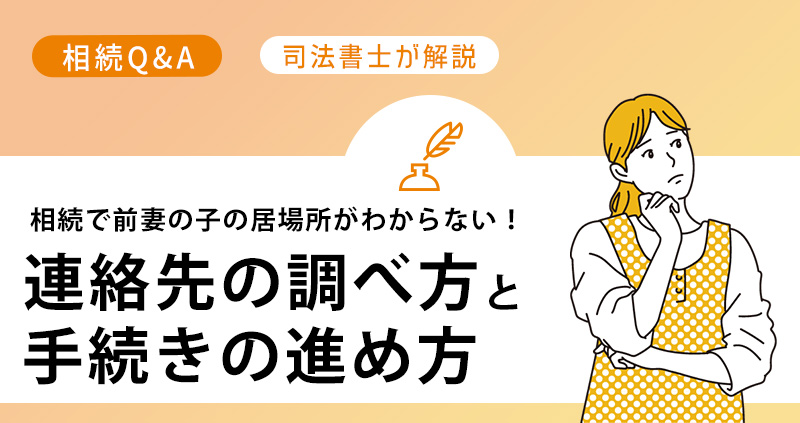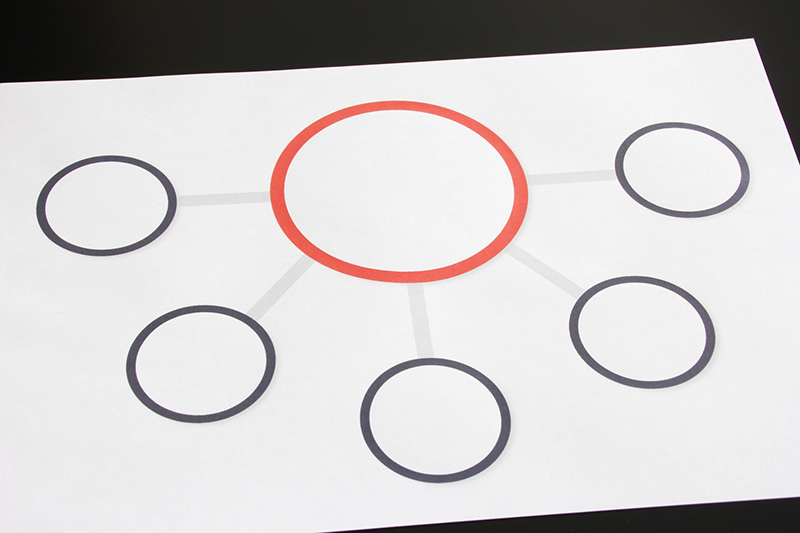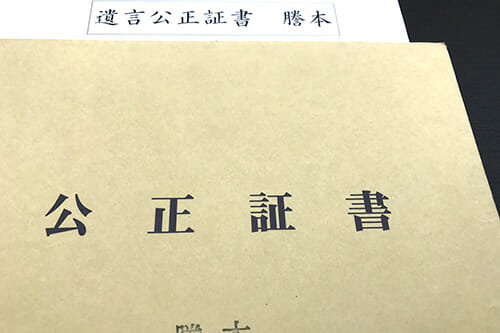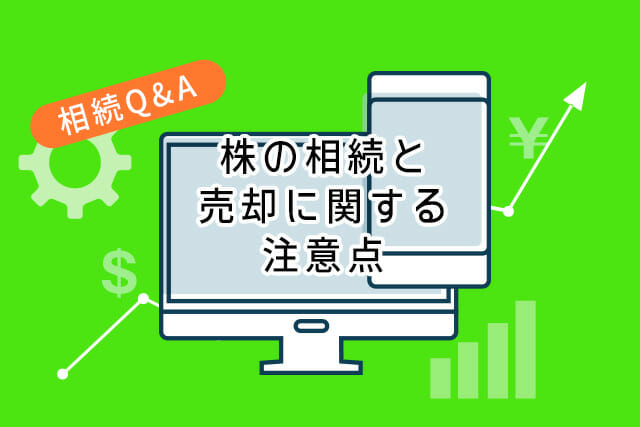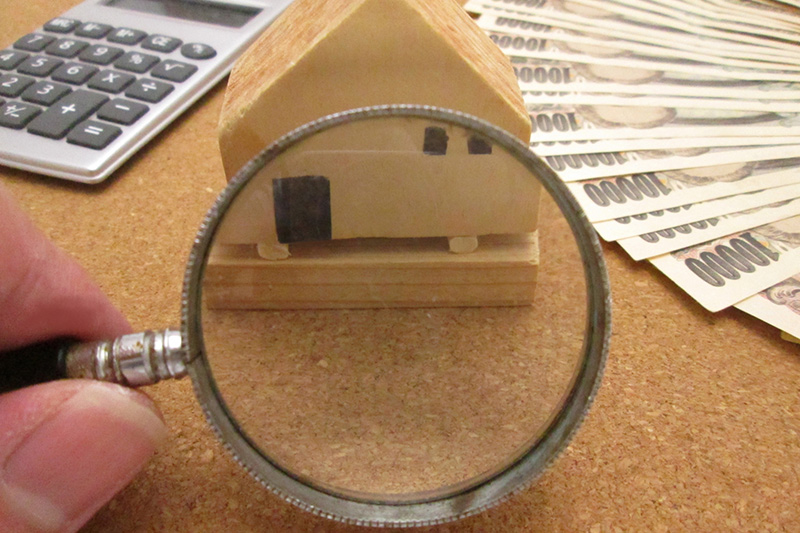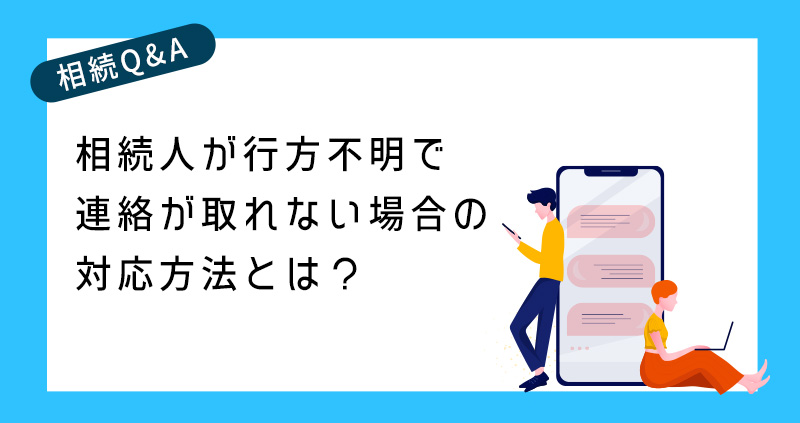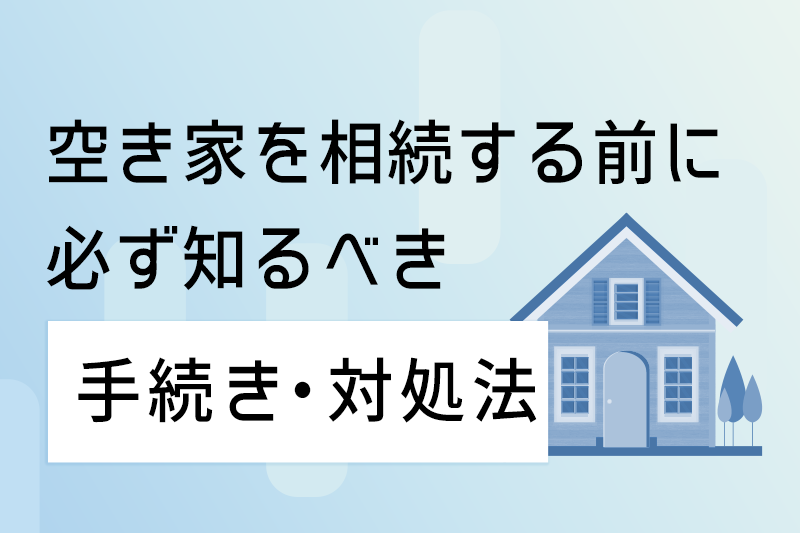財産を相続する権利がある人の範囲と種類
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
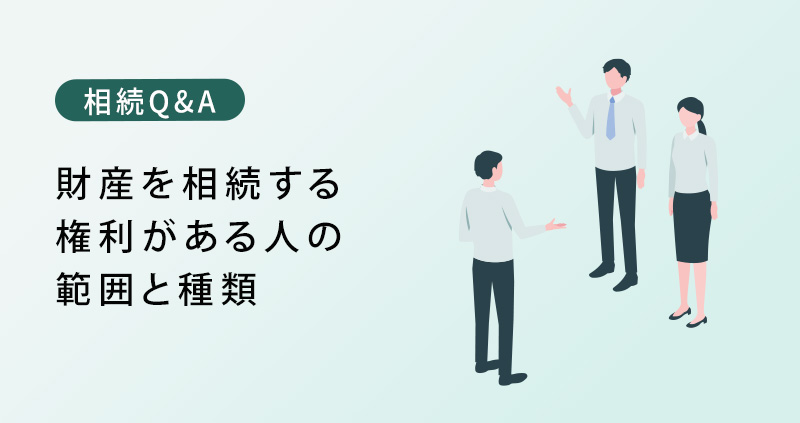

相続する権利を持つのは基本的に「法定相続人」


法定相続人とは
「法定相続人」とは、民法上相続人として定められている人です。財産を相続する権利がある人は、基本的には法定相続人になります。法定相続人は、亡くなった人の親族のうち、一定の範囲の人です。
被相続人が遺言書を残している場合を除き、財産を相続する権利は、基本的には法定相続人が持つことになります。
法定相続人の範囲
法定相続人になるのは、被相続人の配偶者と血族(血のつながりのある親族)です。配偶者はどんな場合でも必ず相続人になりますが、血族には優先順位があります。
| 配偶者 | 常に相続人となる |
|---|---|
| 血族 | 先順位の人が相続人となる |
血族の相続順位は、次のとおりです。
①第1順位:子
被相続人に子供がいれば、子供が優先的に相続人になります。子供には、実子のみならず、養子も含まれます。婚姻関係にない相手との間に生まれ被相続人が認知している子供(非嫡出子)も、第1順位の相続人です。
もし被相続人より先に子供が亡くなっていれば、「代襲相続」が起こります。代襲相続とは、相続権が下の世代に引き継がれることです。子供が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていればひ孫と、順次相続権は移ります。
第1順位では、直系卑属のうち最も世代の近い人が相続権を持つということです。
なお、被相続人の養子が亡くなっている場合、養子縁組後に生まれた子供は代襲相続しますが、養子縁組前に生まれた子供は代襲相続しないとされています。
②第2順位:直系尊属
被相続人に子供などの直系卑属がいない場合には、第2順位として、直系尊属のうち最も世代の近い人が相続人になります。直系尊属とは、親や祖父母など直系でつながる自分より上の世代の人のことです。
父母のうちどちらか一方でも生きていれば、父母が相続人です。この場合、祖父母が生きていても相続人にはなりません。祖父母が相続人になるのは、父母とも亡くなっている場合です。
③第3順位:兄弟姉妹
被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合には、第3順位として、兄弟姉妹が相続人になります。
第3順位でも代襲相続が発生するため、兄弟姉妹が亡くなっていて、その子供(被相続人の甥・姪)がいれば相続人になります。第3順位の代襲相続は甥・姪までで、その下の世代には代襲相続しません。
法定相続人が相続する財産の割合
各法定相続人の相続できる割合についても民法で定められており、これを「法定相続分」といいます。法定相続分は、相続人の組み合わせによって変わり、具体的には次のとおりです。
| 相続人の組み合わせ | 相続割合 |
|---|---|
| 配偶者だけ | 配偶者が全部 |
| 配偶者と子供 | 配偶者が1/2、子供が1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者が2/3、直系尊属が1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4 |
| 血族(子供、直系尊属、兄弟姉妹)だけ | 複数いる場合には均等に分割(※代襲相続人については被代襲者を基準にする) |
相続手続きには法定相続人全員が参加しなければならない
法定相続人が複数いる場合、一部の人だけで相続手続きを行うわけにはいかず、相続人全員の関与が必要になります。相続人全員が相続する権利を持つため、相続人全員で遺産分割協議を行って、相続財産の分け方を決めなければなりません。
遺言書がある場合「受遺者」が相続する権利を持つことがある
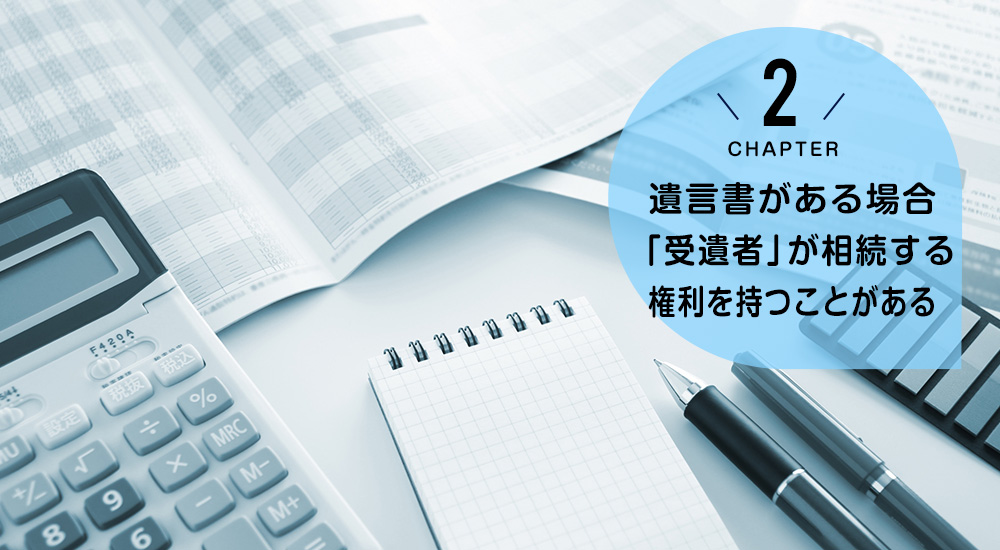

遺言書があれば遺言書が優先
被相続人が遺言書を書いていれば、相続は遺言書に従って行われます。亡くなった後の財産の処分方法については、本人の意思を優先するからです。
遺言書では相続する人や割合を自由に決められる
生前に遺言書を作成しておけば、誰にでも財産を引き継がせることができます。たとえば、子供が生きていれば孫は相続人にはなりませんが、遺言書を書いて孫に財産を相続させることは可能です。遺言書を書けば、親族以外に財産を譲ることもできます。
法定相続人に財産を引き継がせたい場合でも、遺言書で指定するときには、法定相続分に従う必要はありません。相続させる具体的な財産や相続させる割合は、遺言者が自由に指定できます。
法定相続人以外の受遺者が相続権を持つことがある
「受遺者」とは、遺贈を受ける人という意味です。遺贈とは、遺言により財産を無償で譲ることで、遺贈を行う人を「遺贈者」といいます。遺贈者は、遺言者と同じです。
受遺者という場合には、通常、法定相続人以外を指します。遺言によって法定相続人以外に遺贈が行われている場合には、受遺者も財産を相続する権利を持つということです。
死因贈与の受贈者が財産をもらうことも
被相続人が死因贈与の契約をしている場合、受贈者(贈与を受ける人)が財産をもらう権利を持ちます。死因贈与とは、死亡時に財産を贈与する契約です。
遺言は被相続人の一方的な意思によるものですが、死因贈与は被相続人と受贈者との契約にもとづくものです。死因贈与については、原則として遺贈の規定が準用されるため、遺贈と同様に扱います。
遺言書がある場合でも遺留分権利者には相続する権利がある
被相続人が遺言書を残している場合には、相続人全員の関与は必要ありません。遺言書によって財産を相続する権利を持つ人だけで相続手続きができます。
ただし、「遺留分権利者」がいる場合には、注意が必要です。遺留分権利者とは、最低限の相続割合(遺留分)を確保されている法定相続人のことで、具体的には兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)になります。
遺言書により遺留分権利者の遺留分が奪われてしまった場合、遺留分権利者は取り戻しの請求(遺留分侵害額請求)が可能です。遺留分侵害額請求された場合には、遺留分権利者に遺留分相当の金銭を支払わなければなりません。
「特別縁故者」が相続する権利を持つ場合もある


特別縁故者とは
特別縁故者とは、相続人以外で被相続人と特別な関係にあった人です。被相続人と生計を同じくしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人が特別縁故者になります。
特別縁故者は、法律上の相続人にはなりません。しかし、特別縁故者が財産を相続できるケースがあります。
相続人がいない場合に特別縁故者が相続権を持つ
特別縁故者が財産を相続できるのは、法定相続人が一人もいない場合です。相続人不存在の場合、相続財産は原則的に国庫に帰属します。しかし、特別縁故者がいるケースでは、例外的に特別縁故者が財産を相続できることになっています。
特別縁故者の要件をみたしている場合でも、自動的に相続する権利が発生するわけではありません。特別縁故者が財産を相続するには、まず家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらうところから始まり、最終的に家庭裁判所に特別縁故者であることを認めてもらう必要があります。
裁判所に認められれば相続権が得られる
特別縁故者に該当する場合、相続人不存在が確定した後、家庭裁判所に相続財産分与の申立てをすることができます。裁判所が特別縁故者への財産分与を認める審判を出した場合には、特別縁故者が財産の一部または全部を相続する権利を持つことになります。
まとめ

遺言書が残されていない場合には、相続する権利を持つのは法定相続人です。一方、遺言書が残されている場合には、法定相続人以外の人が相続する権利を持っていることがあります。
相続手続きをするときには、他に相続権がある人がいないかどうかに注意しておきましょう。
お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2026/01/20
代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?