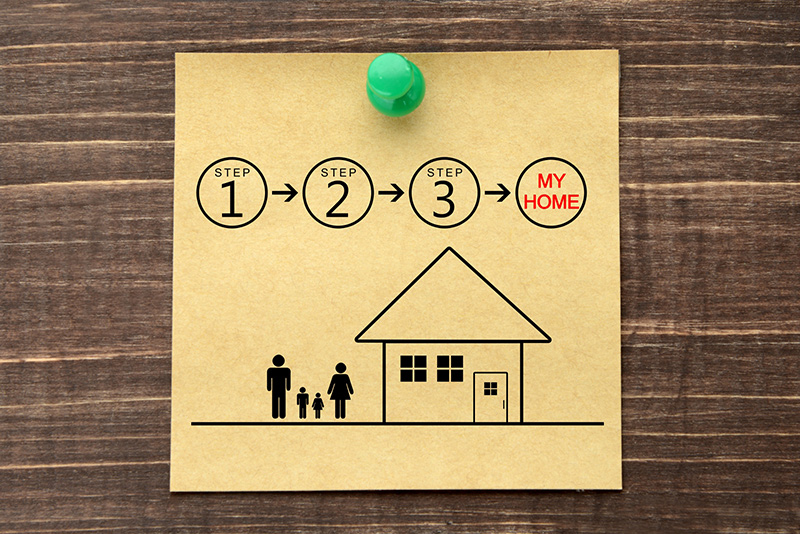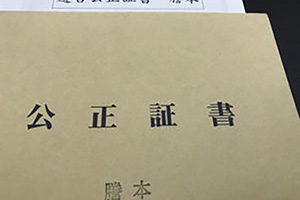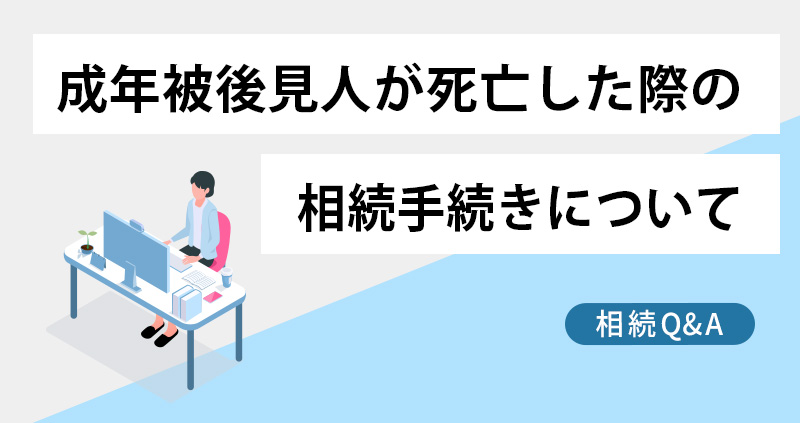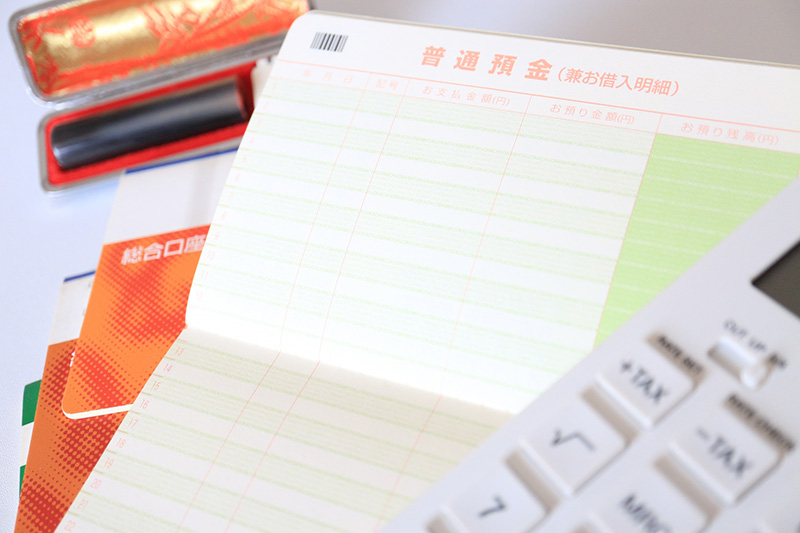家族信託(民事信託)と任意後見の違いついて|併用すべきケースを司法書士がわかりやすく解説
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

家族信託は、財産管理を柔軟に行うことができるが、身上監護(医療や介護に関する手続きや施設入所の手続き等)に対応できない。
任意後見は、身上監護に対応できるが、財産管理の方法が限定されている。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、両者を併用すべき場合がある。

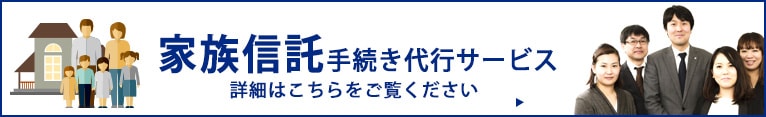
目次
家族信託(民事信託)と任意後見にはどんな違いがある?

任意後見とは?
任意後見とは、将来自分が認知症などにより判断能力がなくなったときに備え、あらかじめ後見人になってほしい人との間で、将来後見人になってもらう契約をする制度のことです。
成年後見制度は、認知症などで判断能力の衰えた人に、「後見人」と呼ばれる財産管理や身上監護の支援者を付けることができる制度で、2000年にスタートしました。
この成年後見人制度には、後見人を裁判所が選任する「法定後見」と、自らが後見人になってもらう人をあらかじめ選任しておく「任意後見」の2種類があります。
| 法定後見 | 家庭裁判所が後見人を選任する制度 |
|---|---|
| 任意後見 | 後見人になってほしい人と、あらかじめ契約を結んでおく制度 |
任意後見は後見人をあらかじめ選んで契約しておく
法定後見は、通常、本人が認知症などになった後、親族などが申し立てます。これに対し、任意後見では、認知症などになる前に、自分で後見人になってもらう人を選び、契約(任意後見契約)を結んでおくことができます。
任意後見人になってもらう人は親族でもかまいませんが、親族以外の人に任意後見人を頼んでもかまいません。弁護士や司法書士に任意後見人になってもらうこともできますが、この場合には報酬を払う必要があります。
任意後見は認知症などにならなければスタートしない
任意後見を利用すれば、自分が信頼できる支援者を選んで、将来の財産管理を任せることができます。ただし、任意後見で、実際に支援者(後見人)に財産管理を任せられるのは、あくまで自分が認知症などになった後です。
任意後見をスタートさせるには、本人の判断能力が低下した後、本人や親族が家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立てなければなりません。後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じることになっています。
そのため、任意後見契約を結んでいても、本人が認知症などにならなければ、支援者が後見人になって財産管理を行うことはありません。たとえば、病気で寝たきりになったとしても、判断能力がある状態なら、任意後見契約がスタートすることはないということです。
家族信託とは?
家族信託は、信頼できる家族・親族と契約(信託契約)を結び、財産管理を任せる方法です。
家族信託で、自らの財産管理を家族に委ねようとする人を委託者、委託者に頼まれて財産管理を行う人を受託者といい、管理を委ねられた財産を信託財産といいます。この信託財産は、委託者や受託者の財産とは分けて管理されることになります。
なお、家族信託には、委託者、受託者以外に、受益者もかかわってきます。受益者とは、信託財産から得られる利益を受ける人です。たとえば、信託財産が賃貸アパートである場合に、賃料を受け取ることができる人です。委託者自らが受益者となる場合が多いですが、第三者を受益者にすることも可能です。
家族信託と任意後見の違い
家族信託と任意後見は、どちらも契約を結ぶことで、誰かに財産の管理を任せるという点は同じですが、契約の効力が発生する時期に違いがあります。
上で説明したとおり、任意後見契約をスタートさせるには、契約を結んだ本人が認知症などになった後、本人や親族が任意後見監督人の選任を申し立てなければなりません。任意後見管理人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。つまり、契約を結ぶだけで、すぐに財産管理を任ることができないのです。
一方、家族信託は、財産管理を任せる人が認知症になったかどうかに関係なく、すぐに始めることができます。家族信託では、裁判所が関与することもありません。自分が信頼できる受託者を選び、すぐに財産管理をしてもらうことができます。

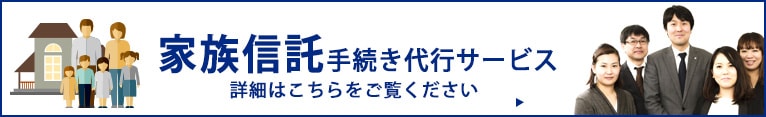
家族信託(民事信託)の方が財産管理は柔軟に対応できる

任意後見人のできることは限られている
成年後見制度における後見人の権限は、財産管理、法律行為(契約行為)の代理、身上監護に限られます。任意後見の内容は契約で定めることができますが、あくまで法律で許容されている前記の権限の範囲内になります。
成年後見制度は、あくまで本人の財産の維持管理を目的とする制度です。支出についても、認められるのは基本的に必要最小限のものになります。
任意後見人は投資や運用はできない
任意後見人は、たとえ本人の財産を増やす目的であっても、積極的な投資や運用をすることはできません。また、任意後見人の行う財産の処分(売却など)にも制限があります。任意後見人は、合理的な理由がなければ、財産を処分することもできません。
たとえば、被後見人が不動産を所有している場合には、任意後見人が付いても、原則的にはその不動産をそのまま維持することになります。土地に賃貸用のアパートを建てるといった不動産投資はできません。土地を売却してお金に換えることも、困難な場合が多くなります。
任意後見人は裁判所の監督を受ける
成年後見制度は、法律にもとづき厳格な運用がされています。後見人はその職務について家庭裁判所の監督を受けることになり、勝手に何でもできるわけではありません。
たとえば、後見人は、定期的に裁判所や後見監督人に後見事務の内容を報告する義務を負います。後見人が問題のある行為をしていれば、解任になってしまうこともあるということです。
家族信託なら任意後見でできないこともできる
家族信託では、受託者の権限は契約で自由に設定することができます。そのため、家族信託を利用すれば、後見人ではできないような積極的な財産活用を受託者に任せることも可能です。
たとえば、後見人には相続税対策をしてもらうことはできませんが、家族信託なら、受託者に生前贈与を行ってもらい、相続税を軽減するといったこともできます。
また、成年後見人が被後見人の居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。一方で、家族信託の受託者にはこのような制限はなく、受託者自身の責任と判断で不動産を売却することもできます。
身上監護が必要な場合は家族信託(民事信託)よりも任意後見

身上監護とは
任意後見人は、被後見人の身上監護を行うことができます。身上監護とは、被後見人の身のまわりの手続き、つまり、生活、治療、療養、介護などに関する手続きを行うことです。
たとえば、次のような手続きが身上監護に該当します。
- 医療に関する手続き
- 介護に関する手続き
- 療養看護に関する手続き
- リハビリに関する手続き
- 施設の入退所に関する手続き
- 住居の確保に関する手続き
なお、被後見人の介護そのものは身上監護に含まれません。任意後見人の行う身上監護とは、あくまで法律行為になります。
家族信託では身上監護を行ってもらうことはできない
家族信託の受託者には、身上監護を任せることはできません。家族信託で任せられるのは、財産の管理や処分に関することのみになります。
老後の対策を考える場合、財産の管理や処分にとどまらず、身のまわりの手続きも誰かにやってもらいたいはずです。つまり、家族信託だけでは不十分ということになります。
家族信託と任意後見の両方を利用すると安心

- 財産管理に加えて身上監護の必要性が高い場合
- 信託財産のみならず、全面的な財産の管理が必要な場合
上で説明してきたとおり、家族信託と任意後見は、カバーできる範囲が違います。それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらか一方のみでは対応できないケースもあります。
家族信託は、財産管理に特化した制度であり、柔軟に財産管理の方法を設計できますが、身上監護(医療・介護の手続きや施設への入所手続きなど)には対応することができません。一方で、任意後見は、財産管理だけではなく、身上監護もサポートできますが、財産管理に一定の制限があります。
そのため、認知症に対する備えや老後対策をできるだけ完全にしたいなら、家族信託と任意後見を併用するのがおすすめです。特に、財産管理に加えて身上監護の必要性が高い場合や、信託財産のみならず、全面的な財産の管理が必要な場合は、併用すべきでしょう。
家族信託と任意後見を併用することで、お互いの足りない部分を補完することができるのです。
まとめ
任意後見は法律にもとづき厳格な運用がされており、裁判所の監督も受けるため融通が利きにくくなっています。一方、家族信託では任意後見のような制限がなく、柔軟な財産管理を実現できるという違いがあります。
家族信託には身上監護を任せられないというデメリットもあります。家族信託の方が良いというわけではなく、目的に応じて使い分けたり、両者を併用したりするのがおすすめです。

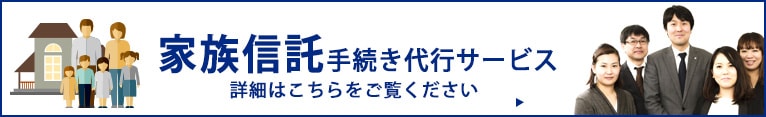
お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2026/01/20
代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?