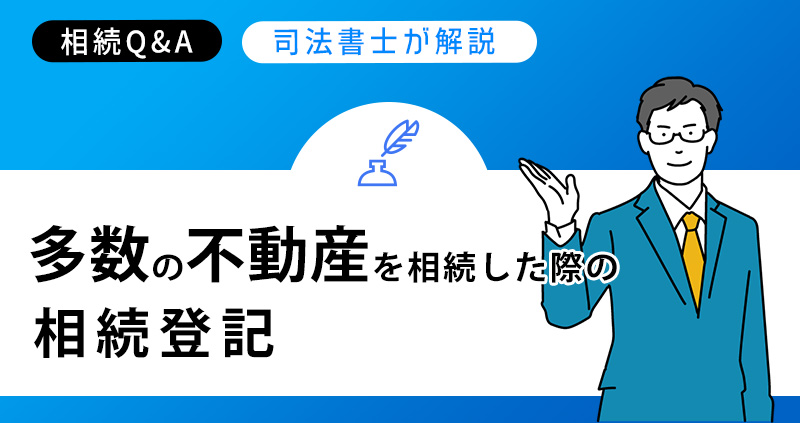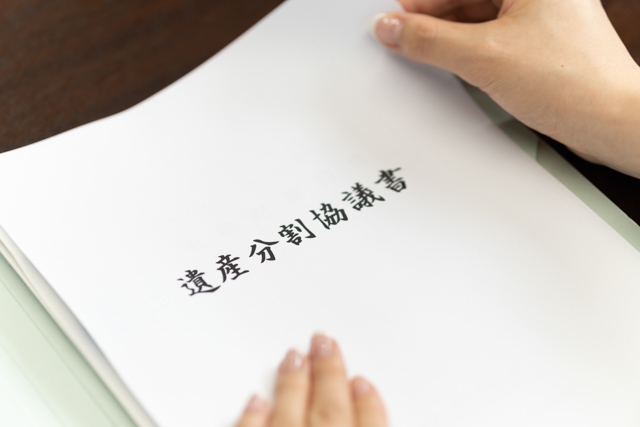【司法書士監修】相続手続きの全期限一覧|3ヶ月・3年・10ヶ月
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
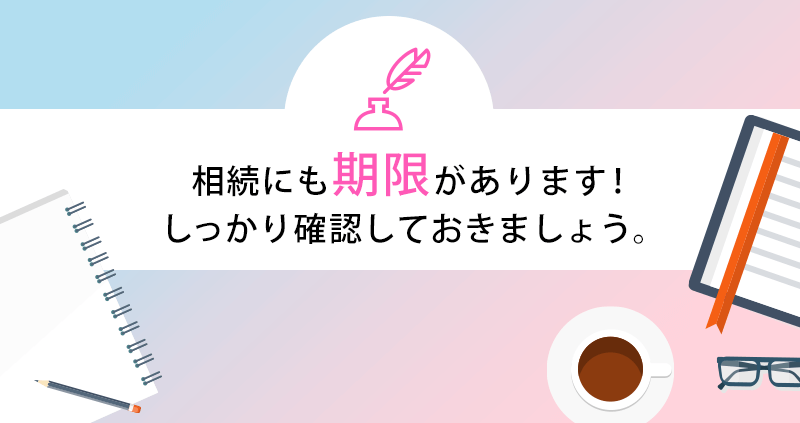

しかし、相続手続きの中には厳格な「期限」が定められているものが多く、「いつかやろう」と後回しにしていると、取り返しのつかない不利益を被る可能性があります。
そこで、この記事では、あなたが絶対に遅れてはいけない相続手続きの期限を、一つひとつ明確に解説します。手遅れになる前に、今すぐ期限を確認しておきましょう。
相続放棄(3ヶ月)や相続税申告(10ヶ月)の期限を過ぎると、大きな不利益が生じます。
不動産の相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きをしない場合、過料(罰金)の対象となります。
遺産分割協議自体に期限はありませんが、不動産登記の義務や相続税の優遇措置の適用を考えると、できるだけ早く成立させる必要があります。
期限が迫った場合、相続放棄の期間伸長や相続登記の暫定措置(相続人申告登記)といった対応策があります。


目次
相続手続きの期限とは?

相続手続きとは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利義務を、ご家族などの相続人へ正式に引き継ぐための手続きです。
以前は「相続そのものに期限はない」と言われていましたが、現在は不動産を相続した場合、3年以内に名義変更(相続登記)を行うことが義務化され、期限を過ぎると過料が科される可能性があります。そのため、「放置しても問題ない」とは言えません。
その他にも、相続放棄や相続税の申告のように、法律で厳格な期限が定められている手続きが複数あります。これらの期限に遅れると、借金を引き継いだり、余分な税金を払うことになったりと、取り返しのつかない不利益を被る可能性があります。
また、たとえ期限がない手続きであっても、先延ばしにすると、次の相続が発生して手続きが複雑化したり、後々思わぬトラブルに発展したりすることが多いため、できるだけ早く済ませておくことが大切です。
相続手続きの期限の一覧


以下に、相続手続きの一般的な流れと、それぞれの手続きの期限について説明します。
1.被相続人の死亡

相続は、被相続人が亡くなったらすぐに開始します。相続手続きの期限は、相続開始時もしくは相続開始を知ったときから起算することになります。
2.遺言書の有無の確認
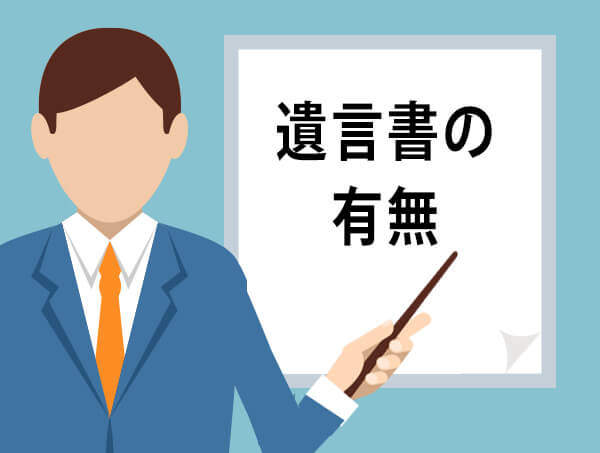
相続財産を分けるには、法律で定められているとおり分ける方法(法定相続)以外に、遺言によって分け方を指定する方法があります。被相続人が遺言書を残していれば遺言書による指定が優先しますから、相続手続きでは、まず、遺言書の有無を確認します。遺言書は単なる「遺書」とは違い、財産上のことだけを書いたものになります。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった種類があります。このうち、自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合には、原則として家庭裁判所で検認を受けなければなりません。ただし、法務局の遺言書保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言は、検認が不要となります。
検認に明確な期限は定められておらず、相続開始を知った後もしくは遺言書を発見した後「遅滞なく」行うべきものとされています。
3.相続人・相続財産の調査及び確定
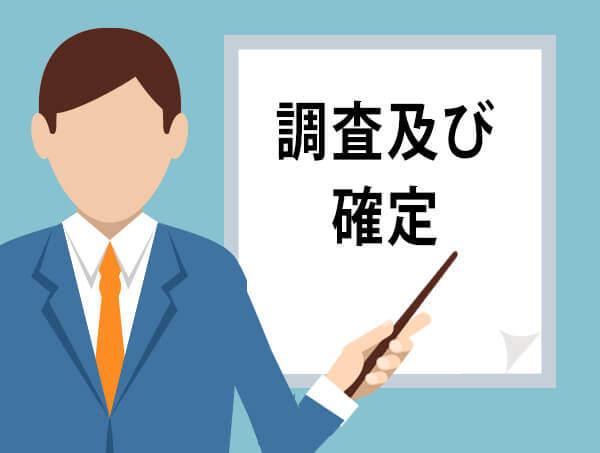
被相続人の亡くなるまでの戸籍を取り寄せ、法律上、誰が相続人になるのかを確定します。また、被相続人の財産には具体的にどんなものがあるのかを調査し、財産目録を作成します。
戸籍謄本の取り寄せや相続財産の調査には時間がかかることがありますので、なるべく早く取り掛かりましょう。
4.相続放棄又は限定承認の期限(※3ヶ月以内)
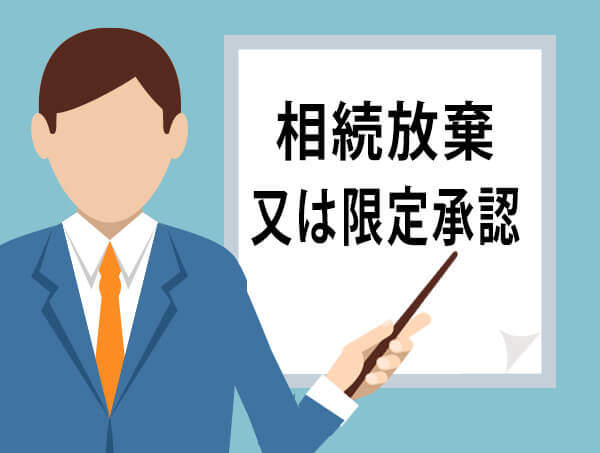
相続が起こった際、何もしなければ「単純承認」と言って、被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産である借金も受け継ぐことになります。
借金を相続したくない場合には、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所において「相続放棄」又は「限定承認」の手続きをする必要があります。相続放棄と限定承認には、次のような違いがあります。
相続放棄

相続放棄すれば、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになり、相続人ではなくなります。相続放棄は、相続人が複数いる場合にも1人だけで手続きできます。
限定承認

限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で借金などの債務を受け継ぐ方法です。相続人が複数いる場合には、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。
相続放棄や限定承認をする期間は延長することもできますが、この場合にも必ず本来の期限までに家庭裁判所に申し立てしなければなりません。期限に遅れた場合には、有無を言わさず借金を相続することにもなってしまいますからくれぐれも注意しておきましょう。
5.所得税の準確定申告の期限(※4ヶ月以内)
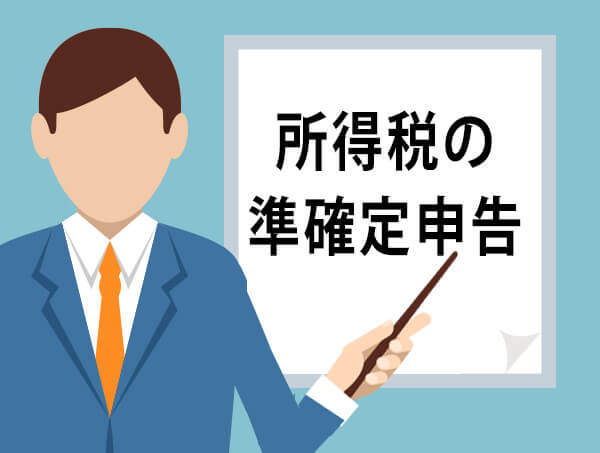
被相続人が年の途中で亡くなった場合には、1月1日から死亡日までの所得に対して所得税が発生している可能性があります。亡くなった人は自分で確定申告できませんから、相続人被相続人の所得について「準確定申告」を行って所得税を納付します。
準確定申告は、相続開始から4ヶ月以内に、被相続人が亡くなった当時の納税地の税務署で手続きしなければなりません。
なお、サラリーマンが在職中に亡くなった場合には、死亡退職時までの給与等について年末調整されるため、通常は準確定申告は不要です。
6.遺産分割協議の期限

相続人全員で、相続財産の分け方について話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」と言います。遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議そのものに法的な期限はありませんが、実質的には期限が存在します。
特に、相続財産に不動産が含まれる場合、遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、協議が成立した日から3年以内に相続登記を申請することが法律で義務化されています。この期限に遅れると10万円以下の過料が科される可能性があるため、遺産分割協議は成立次第、速やかに登記申請に進む必要があります。
また、相続税の優遇措置(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減の特例など)を受けるためには、従来どおりり相続税の申告期限(相続開始を知ったときから10ヶ月以内)までに遺産分割協議が成立していることが前提となります。
これらの理由から、遺産分割協議もできるだけ早めに終わらせておくことが重要です。
7.相続税の申告及び納付の期限(※10ヶ月以内)
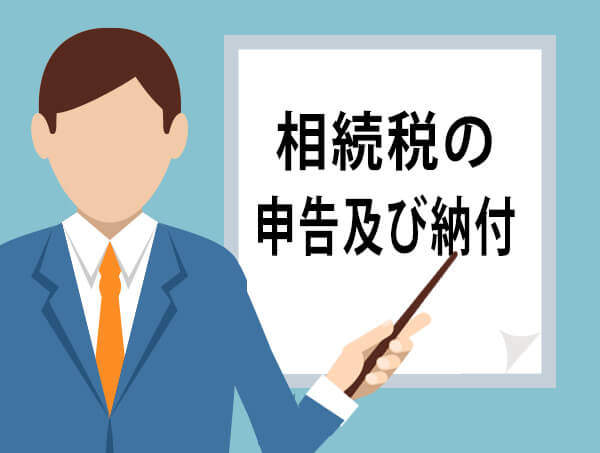
相続財産の額が一定規模を上回ると、各相続人に相続税の申告・納付義務が発生します。また、配偶者の税額軽減等の優遇措置を受ける場合にも、申告が必要です。
相続税の申告・納付は、相続開始を知ったときから10ヶ月以内に、被相続人が亡くなった当時の住所地の税務署で行わなければなりません。もし期限内に申告しなかった場合には、無申告加算税などのペナルティが課せられます。
なお、期限までに相続税を一括納付できないときには、延納(分割納付)や物納(金銭以外での納付)という方法もあります。この場合にも、本来の申告期限までに税務署で手続きして許可を受けなければなりません。
8.相続財産の名義変更の期限(※相続登記は3年以内)
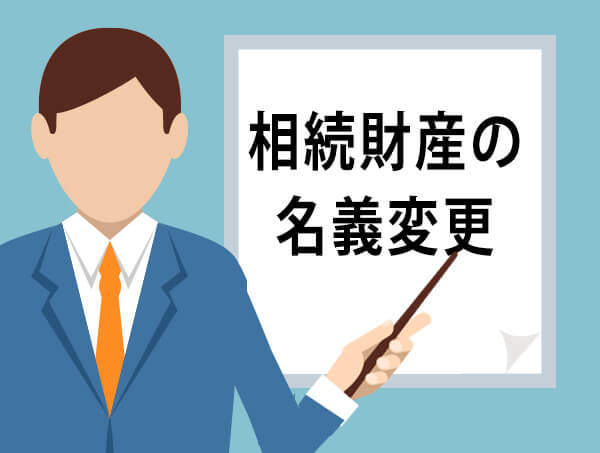
相続財産について、名義変更や解約等の手続きを行います。
相続財産の中に不動産がある場合には、相続登記(名義変更)をする必要があります。この相続登記は、2024年4月1日から義務化され、期限が設定されました。
不動産の名義変更(※3年以内)
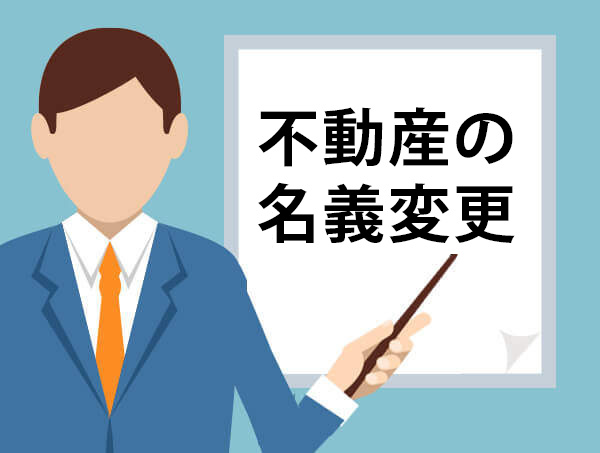
被相続人の所有していた土地や建物を相続した人は、不動産の名義を変更する手続きが必要です。相続による不動産の名義変更は、相続登記と呼ばれます。
相続登記をするには、登記申請書と添付書類を法務局に提出しなければなりません。添付書類としては、戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要になります。
相続登記は義務化されましたので、所有権の取得を知った日から3年以内という期限が設定されました。期限を過ぎると10万円以下の過料の対象となる可能性がありますので、速やかに手続きしましょう。
預貯金の名義変更
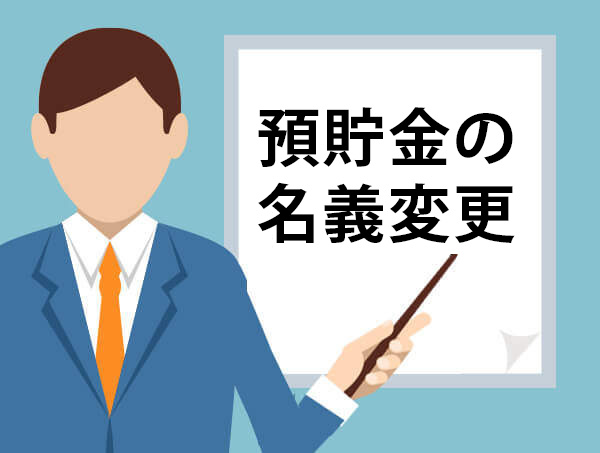
預貯金を相続する人が決まったら、預貯金口座の名義変更が必要です。被相続人名義の銀行口座や郵便貯金口座は凍結されているので、そのままでは払い戻しができません。
金融機関の窓口に遺産分割協議書などの必要書類を提出して手続きすれば、口座の凍結が解除され、預貯金の払い戻しが可能になります。払い戻した預貯金は、相続人名義の口座に預け替えることもできますが、現金で受け取ってもかまいません。
預貯金の名義変更に期限はありませんが、現金が必要になったときに手続きが済んでいないと払い戻しができず困ることがあります。
株式の名義変更
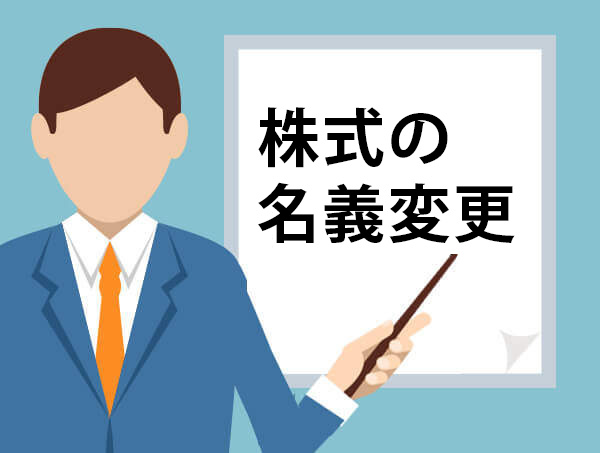
被相続人名義の株式は、相続人名義に変更する必要があります。
「上場株式」については、証券会社の窓口で手続きします。上場株式は電子化されており、株式を保有するには証券口座が必要です。株式を相続する人が証券口座を持っていない場合には、証券口座の開設も行わなければなりません。
「非上場株式」については、発行会社に株主名簿記載変更申請書を提出して名義変更します。
株式の名義変更にも期限はありませんが、名義変更しておかないと配当金を受け取れません。名義変更が済んでいなければ、株式の売却もすぐにはできないことになります。
車の名義変更
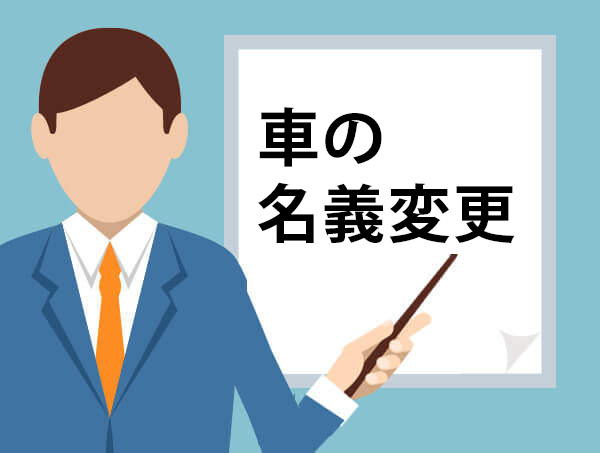
車の名義変更は、相続した人の住所地を管轄する陸運局(運輸支局または自動車検査登録事務所)に移転登録申請書を提出して行います。
申請書には遺産分割協議書、戸籍謄本、手数料納付書、自動車税申告書、自動車検査証、自動車保管場所証明書(車庫証明書)などを添付します。100万円以下の車を相続人の1人が取得する場合、遺産分割協議成立申立書を提出すれば遺産分割協議書は不要です。
車を売却する場合や廃車にする場合でも、一旦相続人名義に変更しなければなりません。名義変更の期限はありませんが、速やかに手続きしましょう。
相続期限が過ぎたらどうなるの?

相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認の手続きをしなければ、相続を単純承認したことになってしまいます。被相続人に借金があれば支払義務を引き継いでしまうため注意が必要です。
所得税の準確定申告(相続開始を知ったときから4か月以内)や相続税の申告(相続開始を知ったときから10か月以内)に遅れると、延滞税や無申告加算税が追加され、より多くの税金を払わなければならなくなってしまいます。
相続登記には新たに3年という期限が設定され、正当な理由なく遅れると過料の対象になる可能性があります。
また、期限が設けられていない手続きも、早めに終わらせないと次の相続が発生して手続きが複雑になることが考えられます。
相続の期限延長が認められるケースとは

相続放棄・限定承認の期限については、当初の3か月の期限までの間(熟慮期間)に、家庭裁判所に期間伸長の申立てをすることにより、延長が可能です。いつまで延長するかは、事情によって家庭裁判所が決めますが、一般には3~6か月程度の延長になります。相続財産の状況がわからず、相続放棄すべきかどうか判断できないなら、期間伸長の申立てをしておくのが安心です。
準確定申告や相続税の申告は、期限の延長ができません。相続税の申告については、遺産分割が終わっていなくても、法定相続分で相続したと仮定して申告が必要です。
相続登記にも、原則として「期間を延長する」という制度はありません。しかし、遺産分割協議がまとまらないなど、正当な理由がある場合には、過料の対象とならないための代替措置が設けられています。
- 不動産を相続した相続人は、遺産分割が未了で正式な登記ができなくても、「自分が相続人である」という事実を法務局に申告する相続人申告登記を行うことができます。 この申告を行うことで、相続登記の義務(3年期限)を果たしたとみなされ、過料の対象となることを避けることができます。 ただし、これはあくまで一時的な措置であり、遺産分割協議が成立した日から改めて3年以内に、その内容に応じた正式な相続登記をする義務が生じます。
まとめ

上記1~8の手続きは、同時並行して可能なものもあります。また、必ず全てをやらなければならないわけではなく、どの手続きが必要かはケースバイケースになります。
なお、期限の設定されている手続きについては、遅れることで大きな不利益を被ることもありますから、くれぐれも注意しておかなければなりません。
相続手続きについて不安な場合は、専門家にご相談されることをおすすめします。


お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2026/01/20
代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?