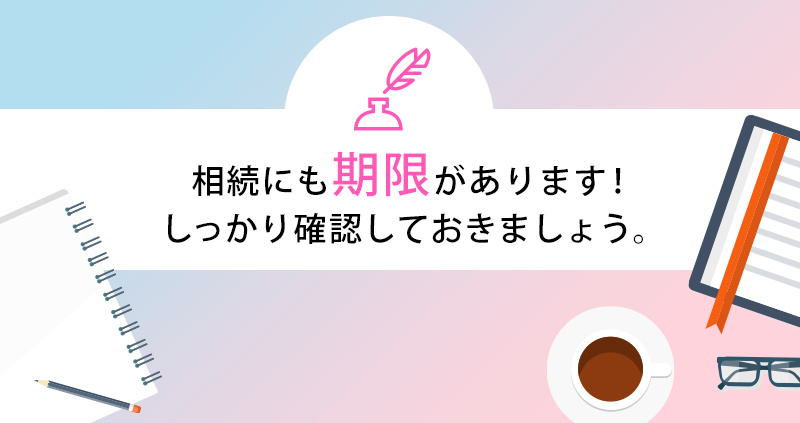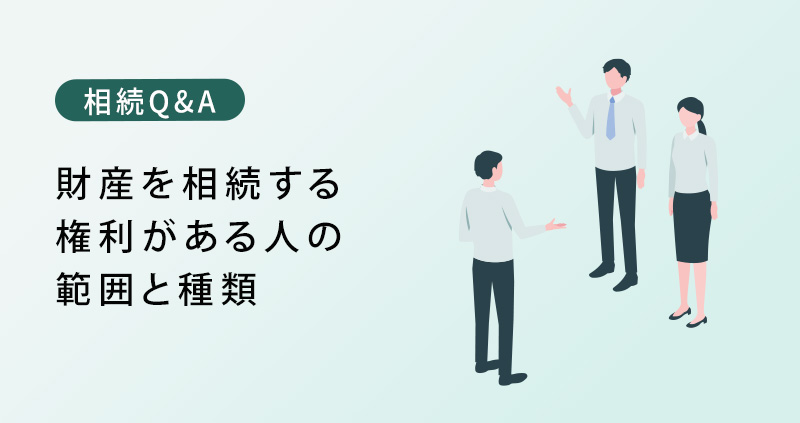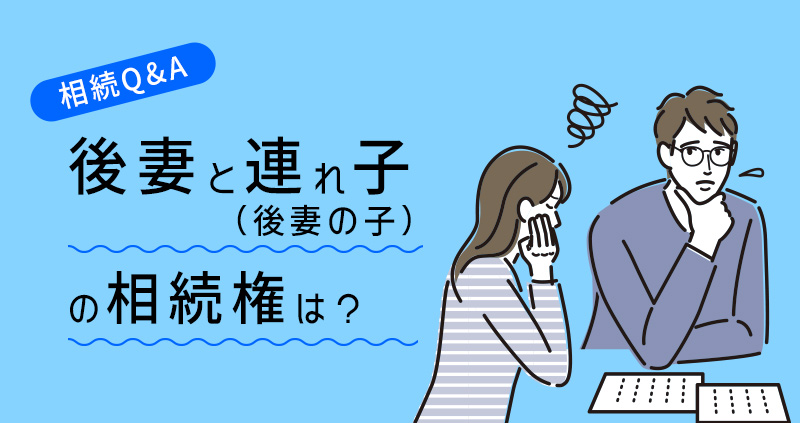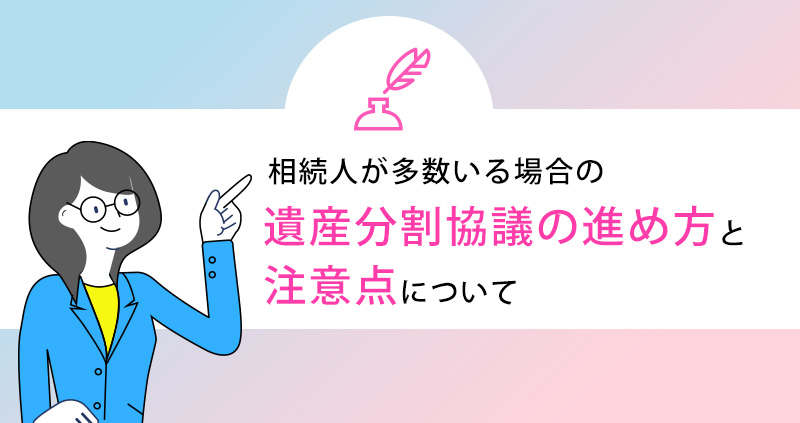法改正で義務化!不動産の相続登記とは?手続きの流れと司法書士に依頼するメリット
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

義務化の開始:相続登記が義務化され、不動産取得を知った日から3年以内に申請が必要です。遅れると10万円以下の過料の対象になります。
手続きの基本:名義変更するには、まず相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するか決める必要があります。
必要書類:戸籍謄本一式(出生から死亡まで)、遺産分割協議書、印鑑証明書など、手間のかかる書類収集が必要です。
専門家の活用:手続きが複雑で期限もあるため、司法書士に早めに相談し、迅速かつ正確な手続きを目指しましょう。


目次
相続登記とは?不動産の名義変更の基本


相続登記の役割
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産について、その所有権を相続人の名義に変更するための登記手続きです。一般に「不動産の名義変更」とも呼ばれます。
不動産に関する情報は、所在地や所有者が誰であるかを含め、法務局で登記され、公開されています。
相続登記を行うことで、この登記簿上の所有者情報を最新の状態に更新し、第三者に対して自分が新たな所有者であることを主張できるようになります。
相続登記の義務化と罰則(法改正の重要ポイント)
旧法下では相続登記に期限や罰則はありませんでしたが、2024年4月1日の法改正により、以下の通り義務化されました。「知らなかった」では済まされないため、不動産を相続した際は迅速な対応が求められます。
| 義務化の開始日 | 2024年(令和6年)4月1日 |
|---|---|
| 申請期限 | 不動産の取得を知った日から3年以内 |
| 対象となる相続 | 施行日(2024年4月1日)以降の相続に加え、施行日以前に開始した相続も対象となります。 |
| 過去の相続の期限 | 施行日以前に開始した相続については、2027年(令和9年)3月31日までに登記が必要です。 |
| 罰則(過料) | 正当な理由なく期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 |
相続登記をしないことのデメリット

⑴ 不動産を自由に処分できない
相続登記をしていないと、登記簿上の名義は亡くなった人のままです。この状態では、不動産の売却はもちろん、不動産を担保にして金融機関からお金を借りることもできません。自分の不動産だと主張しても、登記がなければ第三者には信用してもらえないからです。
⑵ 手続きが複雑化・長期化する
相続登記を放置する間に、さらに次の相続(数次相続)が発生してしまうと、必要な相続人の人数が増え、手続きが複雑になります。必要な戸籍謄本などの書類も増え、手間や費用、時間が大幅にかかってしまいます。
⑶ トラブルのリスクが高まる
時間が経つと、相続人同士の連絡が取りづらくなったり、遺産分割協議が難航したりするリスクが高まります。また、相続人の誰かの債権者が、その相続人の持分を差し押さえる危険性も生じます。


相続登記手続きの具体的な流れ


⑴ 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
相続人全員で、どの財産を誰が相続するかを話し合って決定します。不動産を特定の相続人が単独で相続する場合も、この協議で定めます。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。この書類には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
遺産分割協議書には、不動産を特定するために登記事項証明書(登記簿謄本)を確認し、正確な表示を記載しなければなりません。
⑵ 登記申請書の作成と必要書類の準備
登記申請書は、A4の用紙に横書きで作成します。パソコンで作成しても手書きでもかまいませんが、手書きの場合には黒インクを使う必要があります。内容については、決められたルールに従って記載しなければならないため、自分で作成する場合には法務省のホームページなどを参考にすると良いでしょう。
また、登記申請書には、以下のような書類を添付する必要がありますから、足りないものは取り寄せるなどして準備しておきましょう。
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在の戸籍のほか、被相続人と相続人との関係がわかる戸籍もすべて必要ですから、各本籍地の役所から取り寄せて準備します。
被相続人の最後の住所地で住民票(除票)を取得します。
不動産を相続する人の現在の住民票が必要です。
上述の遺産分割協議書になります。相続人全員の印鑑証明書も添付します。
登録免許税算定のために必要になるので、不動産の住所地の役所に請求します。
相続人の代表者に手続きを委任する場合や司法書士に手続きを委任する場合には委任状が必要です。
⑶ 登記申請と登録免許税の納付
作成した登記申請書と添付書類を、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。提出時には、不動産の価格に応じた登録免許税を収入印紙で納付します。登記が完了するまでにかかる期間は、法務局や時期によって異なりますが、およそ1週間から10日程度が目安です。
【新制度】遺産分割が間に合わない場合の「相続人申告登記」
「3年以内」の期限内に遺産分割協議がまとまらない場合でも、過料を避けるための簡易な手続きとして相続人申告登記が新設されました。
- 相続が開始したこと
- 自分がその不動産の相続人であること
を法務局に申し出ることで、義務を履行したものとみなされる制度です。
この登記をしても、その後に改めて遺産分割が成立した場合は、その成立から3年以内に遺産分割の内容を反映した本登記をする義務が生じることに注意が必要です。
なぜ相続登記は司法書士に依頼すべきか?


⑴ 煩雑な書類の収集・作成を任せられる
相続登記に必要な戸籍謄本一式の収集は非常に手間がかかります。司法書士は職務上、これらの公的書類の収集を代行できます。また、法的に有効な遺産分割協議書の作成も任せられるため、書類の不備による申請のやり直しを防げます。
⑵ 期限内の迅速かつ正確な手続きが可能
3年という期限が設けられた今、手続きの遅延は過料のリスクに直結します。登記申請の専門家である司法書士に依頼することで、複雑な手続きや税金の計算をスピーディーかつ正確に進め、期限内に完了させることができます。
⑶ 遠方の不動産でも安心
登記申請は管轄法務局への提出が必要ですが、司法書士はオンライン申請に対応していることが多く、全国各地にある不動産の登記手続きも問題なく代行可能です。遠方にお住まいの場合や、相続した不動産が複数地域に点在している場合でも安心です。
まとめ:義務化された相続登記は速やかな対応を
2024年4月1日から相続登記は義務化され、期限(原則3年以内)を過ぎると過料が科されるリスクが生じました。
相続登記を放置することは、不動産の売却ができないといったデメリットだけでなく、将来の世代に大きな負担を残すことにも繋がります。
不動産の相続登記が必要になった際は、国家資格を持った登記手続きの専門家である司法書士に、まずはお気軽にご相談ください。面倒な戸籍収集から登記申請まで全て代行し、スピーディーかつスムーズに手続きを完了させます。


お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?