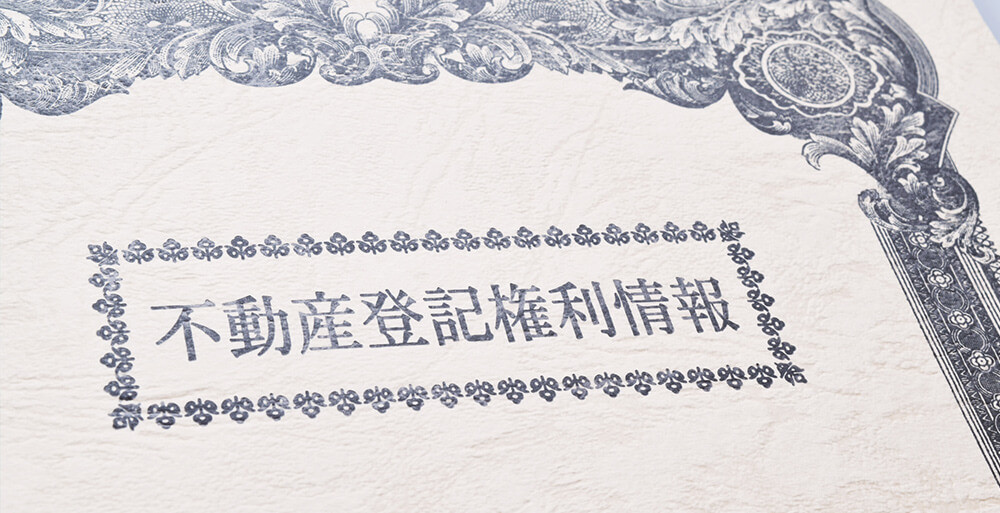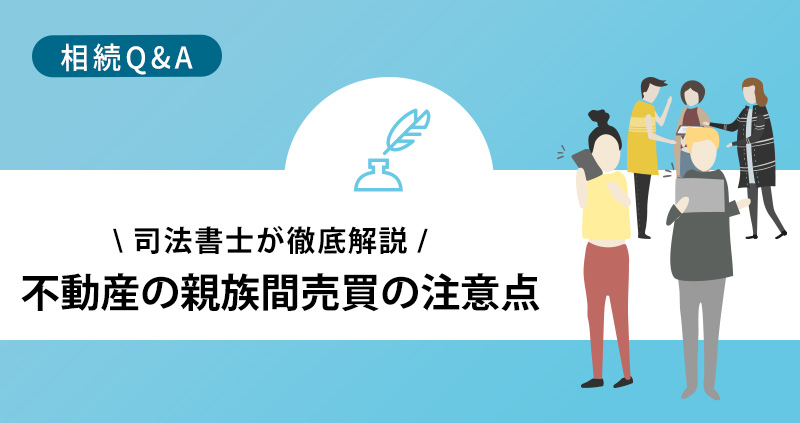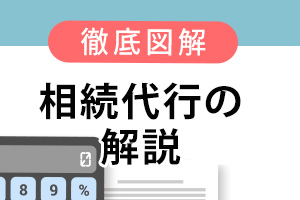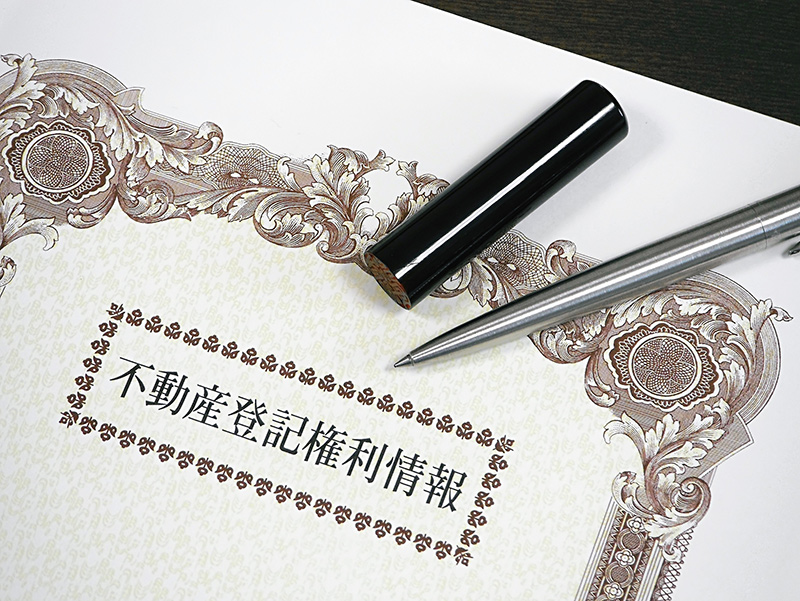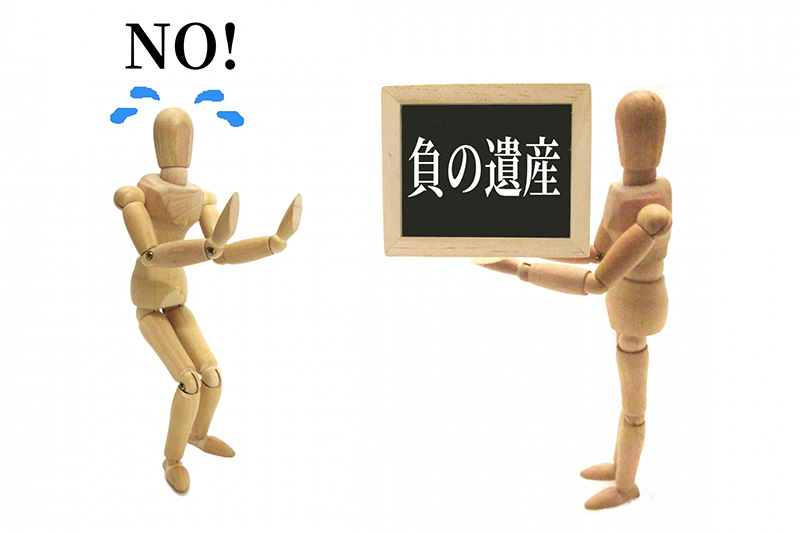土地の相続放棄で重要なこと | 土地を手放す手続きの方法からその後まで
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

選択肢は大きく2つ:不要な土地を手放す方法は、従来の「相続放棄」に加え、2023年施行の「相続土地国庫帰属制度」があります。
最大の注意点:相続登記が義務化!2024年4月以降、相続を知ってから3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料が科されるリスクがあります。
相続放棄の落とし穴:相続放棄をしても、その土地を現に占有している場合は、次に管理する人が現れるまで管理義務が残ります。
国庫帰属の条件:国に土地を引き取ってもらうには、建物がない、境界が明確など厳しい要件があり、承認後には10年分の管理費相当額の負担金を一括で納める必要があります。


使わない土地を所有し続けるデメリット


土地を所有していれば、いろいろな負担が発生します。まず、土地の所有者には、固定資産税や都市計画税が課税されます。使っていない土地でも、持っているだけで毎年税金を払わなければなりません。
また、土地の所有者には、土地を管理する責任があります。誰かがゴミを不法投棄したり、植物が伸び放題になって周りに迷惑をかけたりしないよう、常に気を付けておかなければなりません。土地の管理が不十分だったため他人に損害を及ぼした場合には、損害賠償責任が発生します。
なお、2024年(令和6年)4月1日から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。不動産を相続で取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。この義務に正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。この義務は、改正法施行日(2024年4月1日)以前に発生した相続にも適用されます。
「相続放棄」という選択肢


相続放棄をすれば一切の財産を相続できない
上記のようなデメリットを回避するために、相続放棄をすることにより、土地の所有権を引き継がない選択をすることができます。
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金などを一切引き継がず、相続人としての立場を放棄する方法です。相続放棄をすると、最初から相続人でなかった扱いになるため、被相続人の土地を引き継ぐこともありません。
相続放棄をすれば、土地以外の財産もすべて相続できなくなります。他の財産は相続したいけれど、土地の相続だけを放棄するということはできません。
相続放棄の手続きと期限
相続放棄をしたい場合には、相続開始を知ったときから3か月の「熟慮期間」内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をする必要があります。何もしないまま熟慮期間が経過してしまうと、相続放棄できなくなってしまいます。
相続放棄の申述は、相続放棄申述書、戸籍謄本、被相続人の除票または戸籍附票を提出して行います。申述の手数料(収入印紙代)は800円です。このほかに、連絡用の郵便切手代として数百円程度が必要になります。
なお、熟慮期間内に家庭裁判所に対し相続放棄の期間伸長の申し立てをすれば、期間延長が可能です。土地以外の財産がどれくらいあるかわからない場合などは、とりあえず期間伸長の手続きをしておくのがおすすめです。
| 相続放棄の期間 | 相続開始を知ったときから3か月 |
|---|---|
| 家庭裁判所の管轄 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 必要書類 | 相続放棄申述書・戸籍謄本・被相続人の除票または戸籍附票 |
- 共同相続人がいる場合には、「遺産分割」により相続財産を分ける必要があります。この場合、話し合い(遺産分割協議)により他の相続人に土地を相続してもらい、自分は土地以外の財産を相続するということも可能です。 ただし、有益でない土地は誰も欲しがりませんから、遺産分割の際に争いになる可能性があります。いらない土地を相続させられそうな場合には、相続放棄をした方がよいケースもあります。 相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内しかできませんから、早めに対処方法を検討しましょう。


相続放棄後の土地の管理義務


相続放棄した人の土地の管理義務
被相続人が所有していた土地は、相続の際に相続放棄をすることにより、所有権を引き継がずにすみます。
ただし、相続放棄をした人は、その財産を「現に占有しているとき」に限り、次に相続人になった人や相続財産清算人が管理を始めることができるようになるまで、「善良な管理者としての注意(善管注意義務)」をもって土地の管理を継続しなければならないと民法に規定されています。
つまり、相続放棄をしても、その土地に住んでいたり、何らかの形で利用したりして「現に占有」している状態であれば、勝手に土地を放置することはできず、代わりに管理する人が現れるまで、引き続き責任を持って管理する義務があるということです。
次に相続人になる人とは?
法定相続人になるのは、配偶者と血族相続人(血の繋がった親族)です。血族相続人については、次の表のとおり、第1順位から第3順位まで規定されているため、相続放棄をすれば次順位の人に相続権が移ることがあります。
【血族相続人の順位】
| 第1順位 | 子(先に亡くなっていれば孫等が代襲相続) |
|---|---|
| 第2順位 | 直系血族(父母、祖父母等のうち最も世代が近い人) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(先に亡くなっていれば甥姪が代襲相続) |
相続放棄によって新たに相続人になる人には、連絡をしておくべきでしょう。次順位の人に連絡して土地の管理を引き継がないと、自分がいつまでも土地の管理義務を負うことになります。
相続人不存在の場合には相続財産清算人に管理義務を引き継ぐ
被相続人の配偶者及び第3順位までの相続人全員が相続放棄をした場合には、相続人が1人もいないことになってしまいます。次に相続人になる人がいなければ、土地の管理義務を引き継ぐことができません。
相続人が誰もいない場合に、相続人が土地の管理義務を逃れるためには、家庭裁判所に申し立て、相続財産清算人を選任してもらう必要があります。相続財産清算人とは、相続人のいない相続財産を管理し、債権や債務の清算を行う役割を担う人です。
一般には、家庭裁判所の名簿に登録されている弁護士や司法書士などの専門家が相続財産清算人に選任されます。
相続財産清算人選任申立ての方法
相続財産清算人の選任は、利害関係人(相続放棄した相続人)または検察官が申立て可能です。申立の際には、申立書、戸籍謄本、被相続人の除票または戸籍附票、財産を証明する資料、利害関係人であることがわかる資料などが必要です。
相続財産清算人の候補者を指定して申立することもできます。この場合には、候補者の住民票または戸籍附票も添付します。
申立時にかかる費用は、収入印紙代が800円、このほかに官報広告料と予納郵便切手代で数千円程度がかかります。さらに、相続財産清算人の報酬に充てるために、裁判所から数十万円~100万円程度の予納金を求められるのが一般的です。
相続財産清算人選任後の大まかな流れ
相続財産清算人が選任されたら、選任されたことを知らせるための公告、債権者・受遺者を確認するための公告、相続人を捜すための公告が行われます。その後、相続財産清算人は必要に応じて相続財産を換金し、債権者等への弁済を行います。
最終的に相続財産が残った場合には、国庫に帰属します。国庫に帰属とは、国のものになるということです。
相続放棄ができないケース

1.相続財産を処分してしまった場合
被相続人の財産を一部でも処分してしまった場合、相続を承認したものとみなされるため、相続放棄ができません。遺品の一部を廃棄してしまった場合や、一部を売却してそのお金を使ってしまった場合などが該当します。
2.相続財産を持ち帰った場合
形見分け程度であれば大丈夫ですが、財産的価値のある物を持ち帰った場合には相続放棄できなくなる可能性があります。
3.被相続人宛の請求書の支払いをしてしまった場合
被相続人宛に届いた請求書の代金を、被相続人の財産の中から支払ってしまうと相続放棄ができなくなる可能性があります。注意しましょう。
4.相続放棄をしないまま3か月を過ぎてしまった場合
相続放棄は相続開始を知った後3か月以内に家庭裁判所で手続きしなければできません。手続きの上で期限を延長することは可能ですが、何も手続きしないまま3か月過ぎると相続放棄はできなくなります。
「相続土地国庫帰属制度」という選択肢


土地所有権の単独放棄は原則不可能
登記された不動産の所有権は、原則として所有者が一方的に放棄して手放すことはできませんでした。これが「負動産」問題の根源でした。
しかし、相続土地国庫帰属法の施行により、この原則に大きな例外が設けられました。
制度の概要と適用条件
2023年(令和5年)4月27日に施行された相続土地国庫帰属法により、相続や遺贈によって取得した土地に限り、国に所有権を帰属させる(国のものにする)ことができるようになりました。
この制度は、相続放棄の期間が過ぎた後でも、不要な土地を手放したい場合に利用できる画期的な制度です。ただし、この制度を利用するためには、法務大臣の承認を得る必要があり、土地の状態について厳格な要件が定められています。
【承認されない主な土地の例】
- 建物や工作物が存在する土地(更地である必要がある)
- 担保権や使用収益を目的とする権利(地上権など)が設定されている土地
- 境界が明らかでない土地や、所有権の存否・範囲に争いがある土地
- 土壌汚染や埋設物がある土地
- 通常の管理または処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 管理に過度な費用・労力がかかる崖地などの土地
申請の流れと費用の負担

申請と手数料納付
申請地の所在地を管轄する法務局に申請書を提出し、審査手数料を納付します(事前相談は任意)。
審査と実地調査
法務局が書類審査のほか、現地調査を行い、土地が国庫帰属の要件を満たしているかを厳格に確認します。
承認と負担金納付
審査の結果、法務大臣による承認が得られた後、通知された負担金(10年分の管理費相当額)を一括で納付します。
国庫への帰属
負担金の納付完了をもって、土地の所有権が国(国庫)に移転し、申請者の責任が終了します。

| 審査手数料 | 申請時に納付する手数料 |
|---|---|
| 負担金 | 承認後、土地の性質に応じて算定される、10年分の土地管理費相当額を一括で納付する必要があります。 |
- この負担金は、土地の面積や種類に応じて高額になる可能性があるため、制度を利用する際は、売却や寄付といった他の処分方法も含めて費用対効果を慎重に検討する必要があります。
まとめ
不要な土地を手放す手段として、相続放棄と相続土地国庫帰属制度の2つを解説してきました。どちらの手段も選択せず放置した場合は、2024年4月からの相続登記義務化により、過料のリスクを負うことになります。
土地の所有者として管理責任を負い続けることも含め、不要な土地がある場合は、できるだけ早急に専門家に相談し、対処法を決定することが重要です。


お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
コラムカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報
新着情報
2026/01/20
代表速水が書籍『人はこんなことで破産してしまうのか!』の監修をしました。2025/12/25
減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説2025/12/25
年末年始のお知らせ2025/12/21
【司法書士が警告】実家の相続で「絶対にやってはいけない」3つの失敗とは?